死刑または無期
もしくは5年以上の拘禁刑
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
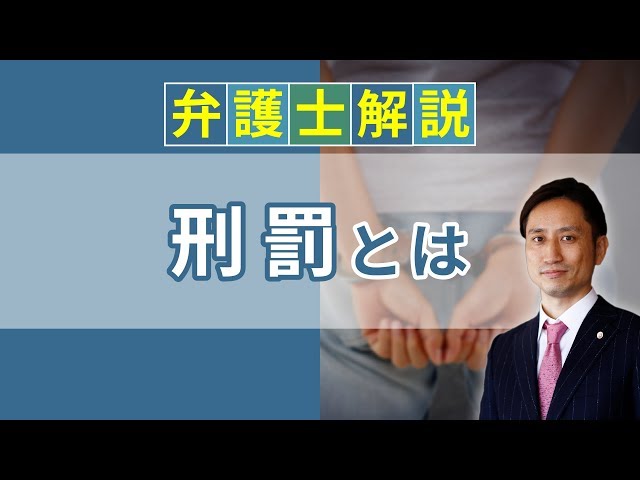
放火は態様により、現住建築物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火などの罪に問われ得ます。
現住建築物等放火は、刑法の中でも特に重い刑罰が規定されています。
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
直接火を放つ以外に、すでに燃えているところに油を注ぐ行為も放火と見なされます。
人が日常的に寝食に使っているような場所や、人がいる場所に放火をすると、この罪によって処罰されます。
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
人が住居に使用していない建物とは、具体的には物置小屋や掘立小屋などのことです。
自身が所有するものに対する放火は、所有していないものに対する放火よりも法定刑が軽く規定されています。
さらに、不特定または多数の人の生命・身体・財産に脅威を及ぼさなかった場合には、罪にも問われません。
第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
上記2つの条文に規定されたもの以外のものを放火し、かつ公共の危険が生じたときには、この罪に問われます。
具体的には、人が乗っていない自動車や電車のほか、家具や建具などです。
放火事件では、警察の捜査で被疑者が特定され、任意で取調べを受けたり、逮捕される場合があります。
また、目撃者やパトロール中の警察に現行犯逮捕されるケースもあります。
火災調査等により、出火原因が放火であることが判明すると、警察は防犯カメラの解析や聞き込み調査などで被疑者の特定に努めます。
被疑者が特定されると、逮捕されて取調べを受けることになるでしょう。
放火は重大犯罪であるため、証拠隠滅や逃走のおそれがあるとして、逮捕に引き続く勾留により長期間身柄拘束される可能性も高いです。
放火準備中や放火中に、目撃者や警察官に犯行が見つかり現行犯逮捕されるケースがあります。
その後は警察署へ連行され、取調べを受けることとなります。
現住建造物等放火の場合は、殺人罪も視野に入れて捜査される可能性があります。
放火の罪においては、現住建造物等放火罪が最も重大な犯罪とされています。
ここでは、現住建造物か否か争われた判例と、複数の建物が回廊で接続する社殿が1個の現住建造物であるとされた判例についてご紹介します。

「本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、右沖縄旅行中の本件犯行時においても、その使用形態に変更はなかったものと認められる」
「本件家屋は、本件犯行時においても、平成七年法律第九一号による改正前の刑法一〇八条にいう「現ニ人ノ住居ニ使用」する建造物に当たると認めるのが相当である」
本件は、被告人が競売手続きの妨害目的で、従業員を交替で泊まり込ませていた家屋で、さらに、保険金目当てで放火前に従業員を旅行に連れ出すなどした上で、放火したという事案です。
こうした事案についても、従業員は旅行後再び家屋への交替宿泊が継続されると認識していたことなどの事情から、寝起きのため日常使用されるという使用形態に変更はなかったとして、現住建造物として認定されました。

「社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険が及ぶと考えられる一体の構造であり、また、全体が一体として日夜人の起居に利用されていたものと認められる」
「右社殿は、物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が一個の現住建造物であつたと認めるのが相当である」
本殿・拝殿・社務所等の建物が回廊等で接続され、夜間も神職等が社務所等で宿直していた平安神宮社殿が放火された事案で、全体として一個の現住建造物であるとした判例です。
弁護側は、人が実際に宿直していた社務所について火の手が及んでいないので、非現住建造物放火罪になると主張していました。
物理的・機能的に見て一体であると判断されれば、一個の建造物であると判断されます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。