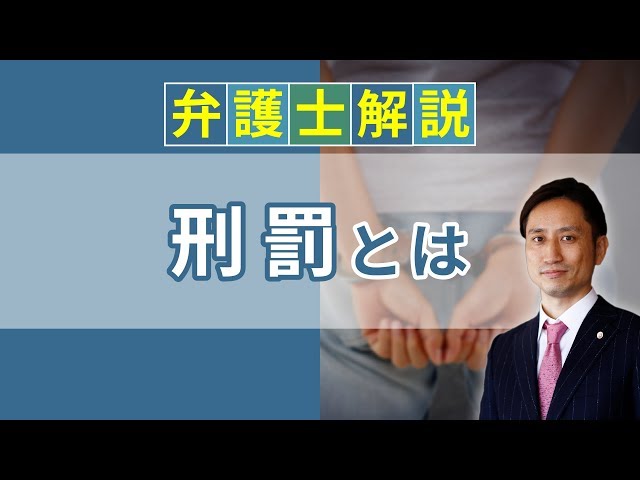- アトム弁護士相談
» - 法令データベース
» - 売春勧誘・あっせん
売春勧誘・あっせんの刑罰・捜査の流れ・裁判例
売春勧誘・あっせんで適用される刑罰
売春の勧誘やあっせんは、売春防止法によって処罰されます。
ここで言う売春とは、「報酬金などの対価を受けたり対価を受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を指します。
売春行為そのものに対する罰則はありませんが、売春の勧誘やあっせんを行った者は、罪に問われ得ます。
売春防止法5条 売春の勧誘等
6か月以下の拘禁刑
または2万円以下の罰金
第五条 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
売春の相手方、つまり、買春するよう勧誘したりキャッチ行為をしたり広告掲示等をすると、この条文により処罰されます。
男女問わず処罰の対象になるため、ネット上で不特定多数の人に対し、自身を買春するよう持ち掛けた女性なども、処罰の対象になり得ます。
売春防止法6条 売春の周旋等
2年以下の拘禁刑
または5万円以下の罰金
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
周旋とは、「仲立ち」「あっせん」「仲介等」を指し、具体的には実際に売春する人と買春をする人両者の間に立って、両者を引き合わせたりなどすることを指します。
これも男女を問わず、処罰の対象になり得ます。
売春防止法7条、8条 困惑等による売春、対償の収受等
3年以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
※態様により、さらに重い刑罰もあり得る。
1項条文中の「欺き」「困惑させ」というのは、「人に嘘を言ったり真実を隠して誤信させたりする行為」を言います。
保護者であるという立場を利用して「生活費を入れろ」などと要求し、売春をさせる態様などは、1項後段の典型例です。
また、2項の脅迫については、「人を畏怖させるに足りる害悪の告知」と解されています。
売春勧誘・あっせんの捜査の流れ
売春勧誘や売春のあっせんにおける検挙の状況について、かつては「路上で勧誘活動等を行っているのをパトロール中の警察官が検挙する」といった態様が典型例でした。
昨今は、サイバーパトロールにより、ネット上の売春勧誘等について取締りが行われるケースも増えています。
ネットの書き込みがバレた場合
1
警察官がネット上を巡回
2
売春関連の書き込み等を発見
3
刑事事件化
昨今、警察は、ネット上の交流を起点とする犯罪を抑制、検挙するためサイバーパトロールによる取り締まりを強化しています。
そのため、SNSや掲示板などで買春相手を募集するような書き込みを行ったりした場合、警察の取調べを受ける可能性があります。
警察官に現場を見られた場合
1
警察官がパトロール
2
売春勧誘の場面を目撃
3
取調べ、刑事事件化
路上等で、いわゆるポン引きやキャッチを行っているところをパトロール中の警察官が目撃し、検挙されるケースもあります。
具体的に、売春、つまりは本番行為が行われているという事実があった場合、売春防止法によって処罰され得ます。
被害者が被害を申告した場合
1
被害者が警察に相談
2
警察が事件を認知
3
捜査
人に無理強いするような形で売春をさせていた、させようとした場合は、被害者が警察に相談、被害届を提出したり告訴をしたりする場合があります。
その後、事件を把握した警察は、態様により捜査が開始され、検挙される可能性もあります。
売春勧誘・あっせんの有名裁判例
売春防止法において、「脅迫したり暴行を加えたりして人に売春をさせた者」について、特に重い処罰を下す規定となっています。
ここでは、条文に示された「人を脅迫し」という言葉の定義について、判示された裁判例をご紹介します。
売春防止法7条2項における「人を脅迫し」の定義について判示された裁判例

裁判所名:
静岡家庭裁判所浜松支部 事件番号:
昭和52年(少イ)3号 判決年月日:
昭和53年3月27日
判決文抜粋
「売春防止法第七条第二項違反の点については、同罪の成立には、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をして売春させることを要する」