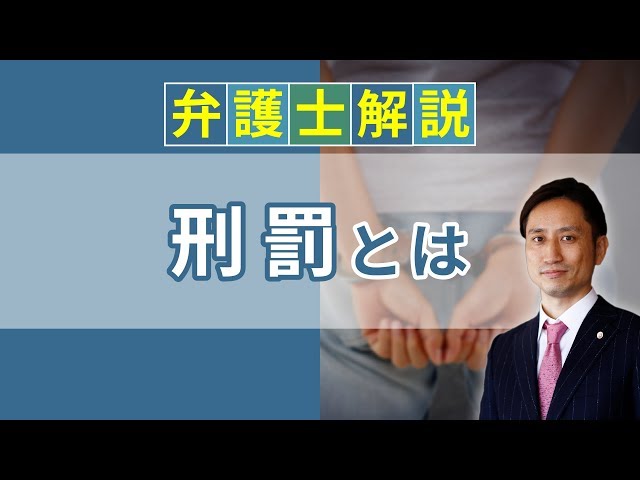- アトム弁護士相談
» - 法令データベース
» - のぞき
のぞきの刑罰・捜査の流れ・裁判例
のぞきで適用される刑罰
のぞき行為は、たとえば刑法などに「のぞき見罪」といった形で刑罰が制定されているわけではありません。
実際には、「迷惑防止条例」「刑法の住居侵入等罪」「軽犯罪法の窃視の罪」などが、犯行の行われた地域・態様などによって選択されたり併科されたりします。
迷惑防止条例(のぞき見)
1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見(略)ること。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、(略)衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見(略)てはならない。
※神奈川県の場合
※常習の場合さらに重い刑罰が科される可能性もある
迷惑防止条例は、各都道府県が独自に制定している条例です。
特に、のぞき見については条例の内容が都道府県ごとで大きく違うため、注意が必要です。
規制の対象となる場所のほか、そもそものぞき見行為について条文内で明言されているかどうかにも違いがあります。
刑法130条 住居侵入等
3年以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
地域によっては、住宅のトイレや風呂などでののぞき見について、迷惑防止条例に問えない場合もあります。
そのような場合は、住居・建造物侵入罪として検挙が行われることもあります。
のぞき見目的の住居や建造物への進入は「正当な理由」にはならないため、この罪が該当します。
軽犯罪法1条23号 窃視
拘留または科料
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
※態様により併科もあり得る
拘留・科料とは、それぞれ「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑」「1000円以上1万円以下のお金を取りあげる刑」です。
人の住居、浴場、更衣場、便所などののぞき見で、迷惑防止条例の適用範囲外のものについては、この罪も適用され得ます。
のぞきの捜査の流れ
のぞきの犯行態様の代表例としては、ドアポストや窓などからのぞく、公共の個室トイレをのぞくなどの行為が挙げられます。
また、のぞきに加えて盗撮まで行う場合も多いです。仮に、盗撮まで行った場合には、余罪捜査のために盗撮機器やスマホ、PCなどが押収されることも考えられます。
現場で通報された場合
1
犯行が露見
2
現場で拘束
3
警察官に引渡し
被害者自身や現場付近にいた目撃者が、のぞきに気づくなどして現場で拘束されるケースが考えられます。
その後は、警察に通報され、警察署に連行されて取調べを受けることになります。
被害届が提出された場合
1
被害届等提出
2
捜査開始
3
被疑者特定
「目撃者の通報」「被害者による被害届提出、告訴」などをきっかけに、警察側がのぞき事件を認知するケースがあります。
そして、防犯カメラの解析などといった捜査活動から被疑者が特定されると、事情聴取などが行われます。
のぞきの有名裁判例
のぞきは犯行態様により、住居侵入等罪に問われます。
ここでは、住居侵入等罪の未遂と既遂の分かれ目について判示された裁判例を解説します。
また、住居侵入で有罪となった後、職場を解雇された原告が解雇の取り消しを求めたという民事裁判についてもご紹介します。
住居侵入等罪の未遂と既遂の分かれ目について参考となる裁判例

裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
平成20年(あ)第835号 判決年月日:
平成21年7月13日
判決文抜粋
「(警察署の敷地と道路とを隔てる高さ約2.4m幅約22cmのコンクリート製の塀は)刑法130条にいう「建造物」の一部を構成するものとして,建造物侵入罪の客体に当たると解するのが相当」
住居侵入等罪で有罪判決となった事による解雇について争われた裁判例

裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和44年(オ)第204号 判決年月日:
昭和45年7月28日
判決文抜粋
「(被告人の住居侵入等罪の行為は)私生活の範囲内で行なわれたものであること、(略:刑罰も)罰金二、五〇〇円の程度に止まつたこと、(略:被告人の仕事上の立場も)指導的なものでないことなど原判示の諸事情を勘案すれば、(略)会社の体面を著しく汚したとまで評価するのは、当たらない」