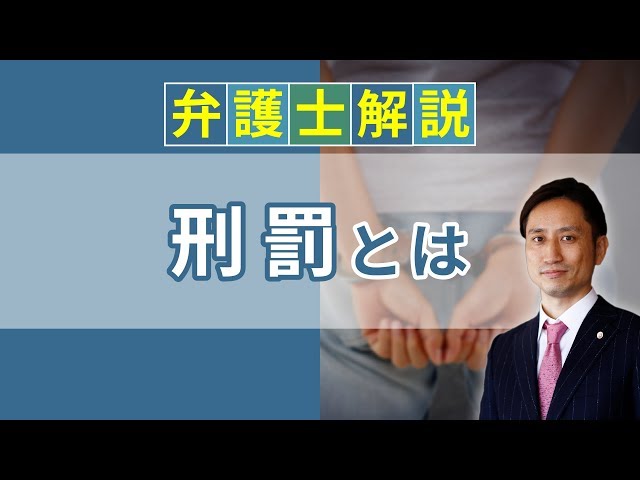- アトム弁護士相談
» - 法令データベース
» - 文書/証書偽造等
文書/証書偽造等の刑罰・捜査の流れ・裁判例
文書/証書偽造等で適用される刑罰
公文書や私文書を偽造した場合、公文書偽造罪や私文書偽造罪として処罰されます。
偽造公文書や偽造私文書を実際に行使したら、偽造公文書行使罪や偽造私文書行使罪となります。
他にも、電磁的記録不正作出罪や、支払用カード電磁的記録不正作出罪など、デジタル犯罪に対応した刑罰もあります。
刑法155条1項 公文書偽造
1年以上10年以下の拘禁刑
第百五十五条 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為
「行使の目的」とは、偽造文書を正式に作成された文書として人に誤信させる目的をいいます。
「偽造」とは、その文書に記された名義人と実際の作成者が同一でないのに、これを偽って文書を作成することをいいます。
刑法159条1項 私文書偽造罪
3か月以上5年以下の拘禁刑
第百五十九条 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいい、履歴書などがこれにあたります。
刑法161条の2第1項 電磁的記録不正作出
5年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
※公務所や公務員に対してこの犯罪を行った場合、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
システムの管理者や使用者の意思に反するようなデータの改ざん、変造、虚偽記入等をするとこの条文によって処罰され得ます。
また、公務員に対しての犯罪は、さらに重い罪に問われることになります。
刑法163条の2第1項 支払用カード電磁的記録不正作出
10年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
クレジットカード、プリペイドカード、カード型電子マネー、キャッシュカードなどを不正に作った場合、この罪に問われ得ます。
単なるポイントカード等は割引特典を蓄積するものでありこれにあたりません。
文書/証書偽造等の捜査の流れ
文書・証書偽造の事案においては、偽造文書が使われることで犯行が発覚し、検挙されるケースがあります。
詐欺の手段として文書偽造がされた場合、詐欺の被害届により文書偽造について発覚する場合も多いです。
犯行が露見した場合
1
偽造文書使用
2
犯行が発覚
3
検挙
偽造文書が使用され、被害者等に犯行が発覚して被害届が提出されるケースがあります。
被害届提出後、警察は被害者からの聞き込み等の捜査をし被疑者の特定に努めます。
文書/証書偽造等の有名裁判例
文書偽造罪においては、「偽造」にあたるか否かがしばしば争われます。
ここでは、同姓同名の弁護士の名義で文書を作成した行為が偽造にあたるとされた判例をご紹介します。
また、郵便送達報告書の受領者の署名押印欄に他人の氏名を署名する行為が私文書偽造罪にあたるとした判例もご紹介します。
同姓同名であることを利用した弁護士の名義での文書作成は私文書偽造罪に当たるとした判例

裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
平成5年(あ)第135号 判決年月日:
平成5年10月5日
判決文抜粋
「たとえ名義人として表示された者の氏名が被告人の氏名と同一であったとしても、本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容のものである以上、本件各文書に表示された名義人は、第二東京弁護士会に所属する弁護士(略)であって、弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であることが明らかである」
郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為が有印私文書偽造罪にあたるとした判例

裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
平成16年(あ)第761号 判決年月日:
平成16年11月30日
判決文抜粋
「郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成すると解するのが相当である」