10年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
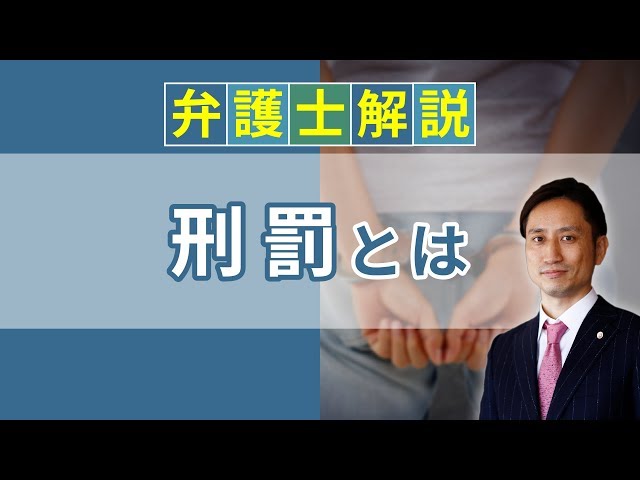
置き引きは、一般に、置いてある他人の物を持ち去ることを言いいますが、どのような罪に当たるかは、事案によります。
例えば、被害品に持ち主等の占有が及んでいる場合は窃盗、及んでいない場合には占有離脱物横領として処罰される可能性があります。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは、他人の占有する財物を言い、置き引きの場合、持ち主が被害品から時間的・場所的に大きく離れていない場合は、持ち主に占有が及んでいると認められやすいです。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為を言います。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「占有を離れた」と言えるためには、持ち主のみならず、たとえば物が置かれた施設の管理者の占有も及んでいないことが必要です。
「横領」とは、不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配下に置くことを言います。
置き引き事案では、被害届の提出により、警察が捜査を開始して被疑者を特定するケースがあります。
また、犯行を目撃されて現行犯逮捕される場合もあります。
被害者が被害届を提出すると、警察が防犯カメラなどを捜査して被疑者の特定に努めます。
被疑者が特定されると、逮捕や任意同行、出頭要請などにより警察署で取調べを受けることになります。
被害者や目撃者に犯行が露見して、現場で取り押さえられるケースもあります。
その後は、警察官に引き渡されて取調べを受けることになるでしょう。
置き引きは、被害品に持ち主等の占有が及んでいる場合には窃盗罪、及んでいない場合には占有離脱物横領罪として処罰されます。
ここでは、窃盗罪が成立するとされた判例をご紹介します。

「被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では,その時点において,被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても,被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず,被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきである」
被害者がベンチに被害品を置き忘れて約27メートル離れ、その隙に被害品を置き引きした事案において、被害品に被害者の占有が及んでいるとして窃盗罪に当たるとした裁判例です。
被害者が被害品について失念していたとしても、その時間や場所が近ければ、占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立するとされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。