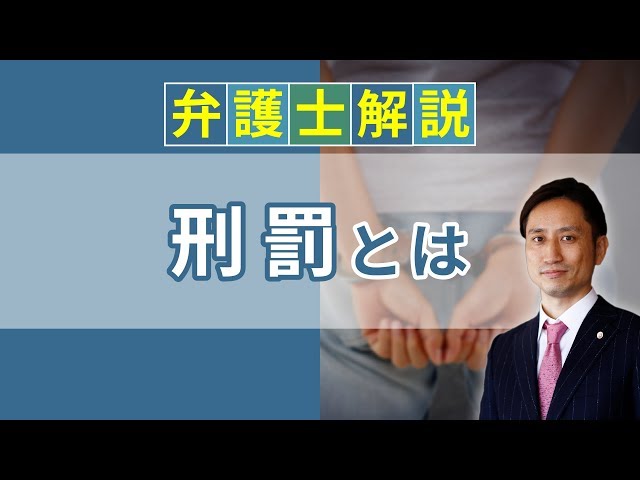- アトム弁護士相談
» - 法令データベース
» - ストーカー
ストーカーの刑罰・捜査の流れ・裁判例
ストーカーで適用される刑罰
ストーカーやつきまとい行為は、「迷惑防止条例」「ストーカー規制法」「軽犯罪法のつきまとい行為の禁止」などによって処罰されます。
これらの刑罰は、それぞれ処罰の対象となる内容が違い、その犯罪の犯行態様によって適切なものが選択されます。
迷惑防止条例(つきまとい行為の禁止)
1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
第5条の2 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で(略)次の各号のいずれかに掲げるもの(略)を反復して行つてはならない。(略)
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4) 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(5) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(6) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物を(略:送付等する)こと。
※東京都の場合
※常習の場合、さらに重い刑罰が科される可能性もある
迷惑防止条例は、各都道府県が独自に制定している条例であり、都道府県ごとに条例の内容が異なるため、注意が必要です。
恨みや妬み、悪意の感情を元に反復してつきまとい行為をすると、迷惑防止条例によって処罰され得ます。
ストーカー規制法
1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
※禁止命令がない場合
第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
「恋愛感情、好意の感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」をもとに反復してつきまとい行為をすると、ストーカー規制法によって処罰されます。
規制の対象となるつきまとい行為の内容は、おおむね先に挙げた迷惑防止条例の条文と同じです。
軽犯罪法1条28項 つきまとい行為の禁止
拘留または科料
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
拘留・科料とは、それぞれ「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑」「1000円以上1万円以下のお金を取りあげる刑」です。
反復して行われていない、単一のつきまとい行為については、軽犯罪法の処罰の対象となります。
ストーカーの捜査の流れ
ストーカーやつきまといの代表例は、「元交際相手やアイドル、顔見知りにつきまといをしたり、LINEやSNS等へ執拗にメッセージを送信する」といったものなどで、脅迫罪にあたる行為が伴うことも多いです。
なお、逮捕・勾留され、長期間身体拘束されるケースも少なくありません。
被害者が警察に相談した場合
1
被害者が警察に相談
2
警察からの事情聴取
3
刑事事件化
被害者がストーカー被害について相談する、被害届の提出や告訴をするなどして、警察が事件を認知するケースがあります。
そのような場合、態様によっては警察から接触等を禁じる命令を受けることになります。
態様がさらに悪質な場合は、そのまま刑事事件として手続きが進むケースもあり得ます。
禁止命令を無視した場合
1
禁止命令を無視
2
被害者が警察に相談
3
刑事事件化
警察官から言い渡された、接触等の禁止命令に違反した場合、刑事手続きをとられる可能性は大きくなります。
ストーカー規制法では、禁止命令に違反した上でのつきまとい行為は、より厳罰に処される規定となっています。
その場合、過去のつきまとい行為も含めて取調べを受けることになるでしょう。
ストーカーの有名裁判例
ストーカー規制法は、規制範囲の広さや規制の手段について、合憲性が争われたことがあります。
ここでは、合憲性が争われた裁判例を解説するほか、またストーカー行為のうち「見張り」する行為や「押し掛ける」行為の定義について判示された裁判例についてもご紹介します。
ストーカー規制法の合憲性が争われた裁判例

裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
平成15年(あ)第520号 判決年月日:
平成15年12月11日
判決文抜粋
「ストーカー規制法は,(略)刑罰による抑制が必要な場合に限って,相手方の処罰意思に基づき刑罰を科すこととしたもの」
「(ストーカー規制法の)法定刑は,刑法,軽犯罪法等の関係法令と比較しても特に過酷ではない」
ストーカー規制法における「見張り」「押しかける」の定義について参考となる裁判例

裁判所名:
東京高等裁判所 事件番号:
平成23年(う)第1654号 判決年月日:
平成24年1月18日
判決文抜粋
「(見張りについて)短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり(略)観察時間が短いことのみを理由に「見張り」に当たらない(略)とすべき理由はない。」
「「押し掛ける」行為については,住居等に相手方が現に存在する必要があるとは解されない」