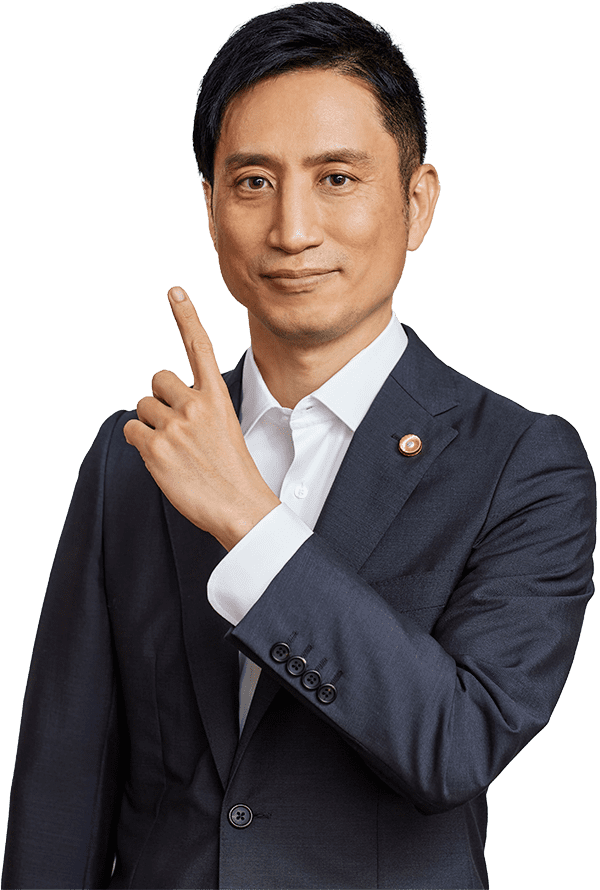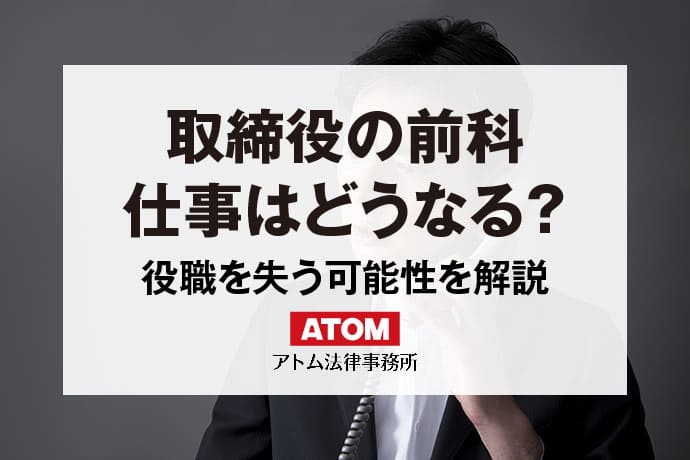
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
「取締役として働いているが、罪に問われたことで前科がつくかもしれない。役職を失うのか」
この記事では、取締役として働かれている方が罪を犯し前科がついてしまった場合の、このような疑問に詳しくお答えしていきます。また、不起訴処分を得て前科がつくことを回避するためにすべきことなどについても解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
取締役は前科がついたら役職を失う?
取締役が罪を犯し逮捕された場合、役職を失う可能性があります。
取締役には禁錮以上の前科がつくと就くことができない
取締役に関する規定は、主に会社法に定められています。同法331条は、取締役になるための資格を欠くとされる条件である欠格事由(けっかくじゆう)として、次のような者は「取締役となることができない」と定めています。
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(中略)又は金融商品取引法(中略)民事再生法(中略)外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(中略)会社更生法(中略)破産法(中略)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
会社法331条
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
また、取締役が不祥事を犯した場合、刑事罰とは別に社内での処分が行われますが、取締役は法律で定められた労働者ではないため、基本的には就業規則ではなく役員規程が適用されます。
前科があっても会社を設立することは可能
「前科があっても、会社を設立することはできるのか?」と思う人もいるかもしれません。
結論から言えば、上記の欠格事由に該当しなくなれば、前科があっても会社を設立し取締役に就任すること自体は可能です。ただし、取締役の欠格事由をクリアしていても、業種によっては事業を行うために必要な許可が下りないことがあるため、注意が必要です。
前科とは?罰金や執行猶予も前科になる?
前科とは、「刑事裁判で有罪判決が確定すること」であり、裁判になっても無罪判決を獲得できれば前科はつきません。
裁判以外で前科を回避する方法として、不起訴処分を獲得し、刑事裁判を開くことなく事件を解決に導く、という方法があります。
前科とは懲役刑や罰金刑が裁判で確定すること
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、その判決が確定した際につくものです。
逮捕後は、一定の勾留期間を経て、検察官が起訴か不起訴かの判断を下し、起訴されて裁判で有罪判決が確定した場合、前科がつくことになります。
したがって、検察官が裁判を行わないという「不起訴処分」の判断を下せば、その人が刑罰に問われることはなく、前科はつかないということになります。
執行猶予や略式罰金も前科になる
裁判において「執行猶予つき判決」や「略式罰金」の判決が出た場合でも、前科になります。執行猶予や罰金は懲役刑に比べると軽いイメージがありますが、注意する必要があります。
一度ついた前科は消えないが、法的な効力は一定期間で消失する
罪を犯し前科がついた場合、事件記録が検察庁や裁判所に保管されます。そのため、前科がついたという事実は消えることはありません。
しかし、前科の事実は消えなくても、その法的な効力は失効することがあります。具体的には、禁固以上の刑の場合は10年、罰金以下の刑の場合は5年の間、刑の執行を終えてから新たに何らかの刑に処せられなかった場合、前科としての法的な効力が失効するのです。
取締役が前科で役職を失わないために弁護士へ早期相談
取締役が何らかの罪を犯したことにより前科がついた場合、役職を失う可能性があることがわかりました。
前科により役職を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要となります。
不起訴処分を獲得し前科を回避する
検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けることがなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。
すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。
示談で不起訴の可能性を高める
被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。
被害者と示談するためには弁護士に相談する
被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は、最大で23日間となっています。起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。
逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。