2年以下の拘禁刑
もしくは30万円以下の罰金
または拘留もしくは科料
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
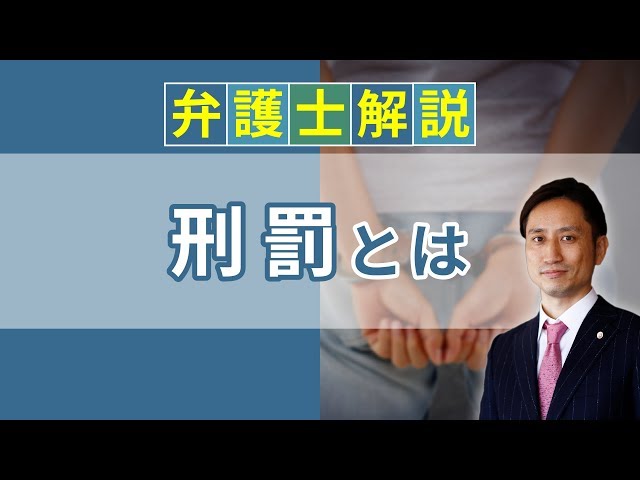
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」では、DVについて、配偶者や事実婚者、過去配偶者や事実婚関係にあった者から加えられる「身体に対する暴力」「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されています。
実務上は、刑法の暴行や傷害によって検挙されるケースが多いです。
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
たとえ夫婦間であっても、相手を殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどすれば、暴行罪が成立します。
判例上は、服をつかんで引っ張る、物を投げつけるといった行為も暴行に該当し得ます。
暴行の結果、相手が怪我をすれば、そのケガがどれだけ軽微でも、後述の傷害罪に問われ得ます。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
相手にケガを負わせた場合は、傷害罪に問われ得ます。
基本的には、どれだけ軽微なケガであっても、傷害罪は成立し得ると考えるべきでしょう。
DV事案では、DV防止法に基づく保護命令違反をして、被害者に通報され検挙されるケースがあります。
暴行や傷害事件として通報や被害届が提出され、検挙されるケースもあります。
DV防止法は、保護命令として付きまとい行為やメール送信等を禁止しています。
保護命令違反をした場合、被害者に通報されて検挙にいたる場合も考えられます。
DV防止法による保護命令が出ていなくとも、被害者が通報したり被害届を提出、告訴したりするケースも考えられます。
その場合、通報を受け駆け付けた警察官によって警察署に連行され、取調べを受けることになるでしょう。
なお、態様によっては、現行犯逮捕される可能性もあります。
DV防止法は、被害者への接触等がなされないよう、配偶者が保護命令に違反した場合に罰則を定めています。
ここでは、禁止行為とされている「徘徊」にあたらないとされた裁判例と、被害者の同意がある場合の保護命令違反罪の成否について、判示した裁判例をご紹介します。

「「徘徊」とは,理由もなく被害者の子の住居,就学する学校その他通常所在する場所の付近をうろつく行為,をいうものと解するのが相当である」
「(子や被害者への接近の目的)以外の目的で,子の通常所在する場所の付近に赴き,当該目的に必要と認められる限度で同所に所在する行為は,「はいかい」には当たらないというべきである」
被害者の子の就学する学校の校長宛ての手紙を渡す目的で来訪したことはDV防止法10条3項の「はいかい」にはあたらないとした裁判例です。
そもそも徘徊とは、目的もなくうろつくことを意味すると法案の国会審議等で説明されていたことや、DV防止法の趣旨から被害者等への接近目的以外での来訪は「はいかい」にあたらないとされました。

「(DV防止法)は,その経緯,事情の如何を問わず,形式的に保護命令に違反すれば処罰する趣旨の規定と解すべきである」
「被害者の同意の有無は本罪の成立には関係がないと考えられ,被告人において,形式的に保護命令に違反する行為をしていると認識している以上,本罪の故意としてはそれで十分であ(る)」
保護命令に違反して、妻に電話やメールをした事案で、命令違反行為につき、たとえ被害者の同意があっても犯罪の成否に関係しないと判示した裁判例です。
被害者が容認していれば罪にならないとすると、被害者に意に沿わない同意を求める事態を招きかねないため、このような判断がされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。