死刑または無期
もしくは5年以上の拘禁刑
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
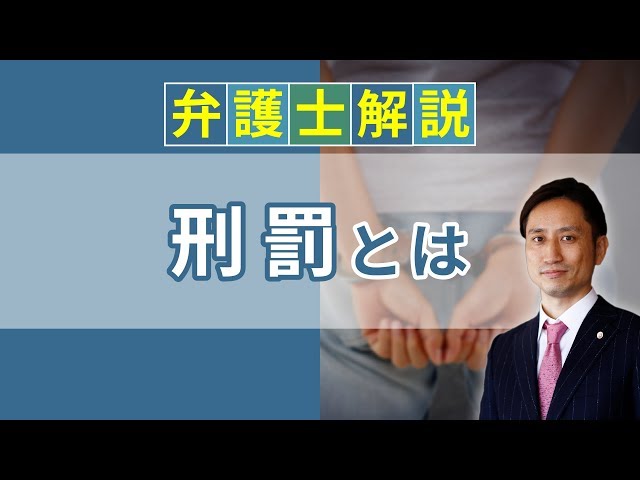
殺人は、強盗殺人や嘱託・同意殺人(被害者から依頼されて被害者を殺す、被害者の同意を得た上で殺す殺人)を除き、基本的には刑法199条の殺人罪に問われます。
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
殺人罪は、故意に人を殺したときに適用されます。
殺すつもりはなく、人に暴行をふるった結果として死亡させた場合には、後述の傷害致死罪に問われるでしょう。
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
殺意はなくとも、暴行や傷害によって相手を死に至らしめた場合には、傷害致死罪が成立し得ます。
暴行や傷害と、被害者の死との間に因果関係があれば本罪は成立し、たとえば、被害者が暴行を避けようとして転び岩に頭をぶつけて死亡した場合で傷害致死の成立が認められた判例もあります。
殺人事件においては、他殺体が発見されて捜査が開始されるケースが多いです。
殺人未遂の場合は、被害者等の通報を受けて、臨場した警察官に現行犯逮捕されるケースもあります。
警察は通報等により他殺体が発見すると死因、被害者の交友関係、周辺の防犯カメラなどを捜査して、被疑者の検挙に努めます。
殺人は重大犯罪であるため、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして逮捕・勾留により長期間身柄拘束がされる可能性が高いです。
被害者の家族などの通報により、警察官が駆けつけるケースがあります。
その後は現行犯逮捕や緊急逮捕により警察署へ連行され、取調べを受けることになります。
殺人は重大犯罪であるため、逮捕に引き続く勾留により、長期間身柄拘束されることになるでしょう。
ここでは、第2行為で殺害するつもりが、第1行為で死亡していた可能性がある場合に、第1行為の時点で殺人罪の実行の着手を認めた判例をご紹介します。
このほか、致死量以下の空気を静脈に注射した行為に、殺人未遂罪の成立が認められた判例についてもご紹介します。

「第1行為は第2行為に密接な行為であり,実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である」
被害者を薬品で失神させた上、自動車ごと海中に転落させて溺死させようとするも、薬品の吸引時点で被害者が死亡している可能性があったという事案で、失神の時点で殺人罪の実行の着手があるとした判例です。
弁護側は、薬品の吸入はあくまで気絶させるためであったから、殺人の故意も実行行為もないため、殺人罪は成立しない旨を主張していました。

「本件のように静脈内に注射された空気の量が致死量以下であつても被注射者の身体的条件その他の事情の如何によつては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないと判示しており、右判断は、原判示挙示の各鑑定書に照らし肯認するに十分である」
本件は、被害者の静脈内に致死量以下の空気を注射した事案ですが、たとえ致死量以下であっても、死の結果発生の危険が絶対にないは言えないとされ、殺人罪の実行の着手があったとされました。
犯罪をしようとした際、その行為からは結果の発生は到底不可能だったという場合を「不能犯」と言います。
殺人罪では、弁護側から「不能犯であるため殺人罪は成立しない」という主張がされることが多いですが、実務上、こうした主張が認められるケースは少ないようです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。