10年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
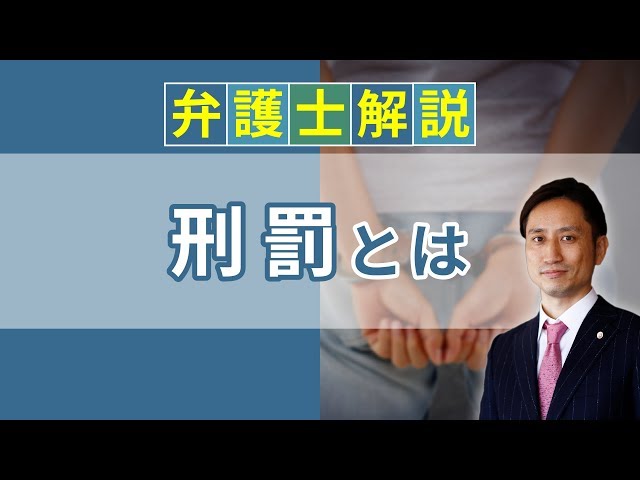
他人の占有する財物を、占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己または第三者の占有下に移転した場合、窃盗罪として処罰されます。
ここにいう占有とは、物を事実上支配・管理している状態をいいます。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは他人の占有する財物を言い、自分の物でも他人の占有する物は「他人の財物」とみなされます。
住居に侵入しての窃盗のほか、いわゆる万引きやスリなども窃盗にあたります。
窃盗の典型例は、万引きや置き引き、空き巣などです。
いずれも現行犯逮捕や、被害届提出を受けて警察の捜査がなされるケースが多いです。
なお、家宅捜索で余罪が発覚するケースもあります。
被害者や目撃者に犯行が露見し、取り押さえられるケースがあります。
その後は、警察官に引き渡されて取調べを受けることになるでしょう。
余罪が疑われる場合は、家宅捜索されることもあります。
被害者が被害届を提出し、捜査が行われるケースもあります。
警察は、巡回強化や防犯カメラの解析などを行い、被疑者の特定に努めます。
被疑者が特定されると、任意で取調べを受けたり、逮捕・家宅捜索がされることになるでしょう。
ここでは、窃盗罪の実行の着手時期や既遂時期について判示した判例をご紹介します。
また、死んだ人から物を盗んでも、原則として占有離脱物横領罪が成立するにすぎませんが、例外的に窃盗罪が成立すると判示した判例についてもご紹介します。

「電気器具商たる本件被害者方店舗内において(略)なるべく金を盗りたいので自己の左側に認めた煙草売場の方に行きかけた際、本件被害者らが帰宅した事実が認められるというのであるから、原判決が被告人に窃盗の着手行為があつたものと認め、刑法二三八条の「窃盗」犯人にあたるものと判断したのは相当である」
店舗内で、現金が置いてあると思われる場所を確かめてその方へ近づいた時点で窃盗罪の実行の着手があり、刑法238条(事後強盗罪)の「窃盗」犯人に当たるとした裁判例です。
被害品に触れていなくても、被害品が盗まれる現実的危険のある行為をした時点で、窃盗罪の実行の着手があるとされています。

「凡そ不法に領得する意思を以つて、事実上他人の支配内に存する物体を自己の支配内に移したときは、茲に窃盗罪は既遂の域に達するものであつて、必らずしも犯人が之を自由に処分し得べき安全なる位置にまで置くことを必要とするものではない」
車庫から木炭六俵を担ぎ出して柵外に持出した時点で、管理者の支配を排して自己の支配下に移したものといえ、窃盗罪の既遂にあたるとした判例です。
被害品を自由に処分できるような安全な場所に置かずとも、占有が侵害された時点で既遂にあたるとされています。

「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である」
被害者を殺害後、被害品を盗る犯意を生じてこれを盗んだ事案において、窃盗罪が成立するとした判例です。
殺人犯との関係では、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうとして、例外的に窃盗罪が成立するとされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。