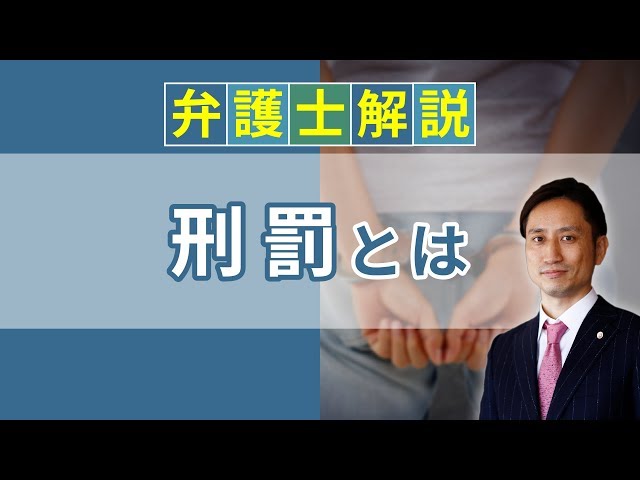- アトム弁護士相談
» - 法令データベース
» - 飲酒運転
飲酒運転の刑罰・捜査の流れ・裁判例
飲酒運転で適用される刑罰
飲酒運転は、道路交通法において「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」として処罰されます。
酒気帯び運転かどうかはアルコールの検出値によって、酒酔い運転かどうかは本人の運転等の状況によって判断されます。
そのため、「酒気帯び運転」にあたらずとも「酒酔い運転」にあたる可能性はあり、しかも酒酔い運転のほうが罪は重くなります。
道路交通法117条の2の2第3号
3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の二の二
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、血液1ml中0.3㎎または呼気1リットル中0.15ml以上のアルコールが検知されることを言います。
軽車両は規制対象外であるため、基準を超えるアルコールを体内に保有して自転車を運転しても、この罪には該当しません。
道路交通法117条の2第1号
5年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
「酒に酔った状態」とは、たとえば蛇行運転や標識が守れないような状態で運転するような場合です。
検知されたアルコールの数値は関係がないため、酒気帯び運転に至らない場合でも、この罪に当たる可能性があります。
また、酒気帯び運転と異なり、酒に酔った状態での自転車の運転は処罰対象となります。
飲酒運転の捜査の流れ
飲酒運転をしている事実が露呈する流れとしては、パトロール中の警察官による職務質問や検問が挙げられます。
また、飲酒運転中に交通事故を起こし、捜査の過程で飲酒の事実が発覚するケースもあります。
職務質問される場合
1
職務質問、検問
2
アルコール検査を受ける
3
検挙
警察は幹線道路を定期的にパトロールし、怪しい車両に対しては職務質問を行っています。
また検問所を設けて交通違反の取り締まりを行っているケースもあります。
飲酒が疑われる運転者にはアルコール検査を実施し、酒気帯び/酒酔い運転に該当していた場合にはそのまま検挙します。
交通事故を起こした場合
1
交通事故を起こす
2
警察が捜査を開始
3
飲酒運転発覚
飲酒運転の最中に交通事故を起こしてしまった場合は、その後、臨場する警察官に飲酒の事実についても把握されるでしょう。
飲酒運転の有名裁判例
酒気帯び運転ないし酒酔い運転をすると、道路交通法により処罰されます。
ここでは、酒気帯び運転における故意が問題となった判例と、酒酔い運転を理由とした免職処分が取り消された裁判例をご紹介します。
旧道路交通法119条1項7号の2に規定する酒気帯び運転の罪の故意について判示した判例

裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和52年(あ)第834号 判決年月日:
昭和52年9月19日
判決文抜粋
「道路交通法一一九条一項七号の二に規定する酒気帯び運転の罪の故意が成立するためには、行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、同法施行令四四条の三所定のアルコール保有量の数値まで認識している必要はないとした原判断は、相当である」
飲酒運転を理由とした免職について原告の事情等を鑑み違法であると示された裁判例

裁判所名:
東京地方裁判所 事件番号:
平成24年(行ウ)第675号 判決年月日:
平成26年2月12日
判決文抜粋
「原告を停職ではなく免職とした本件処分は,本件酒酔い運転に対する処分量定として重きに失するというべきであり,社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用した違法があるものと認めるのが相当である」