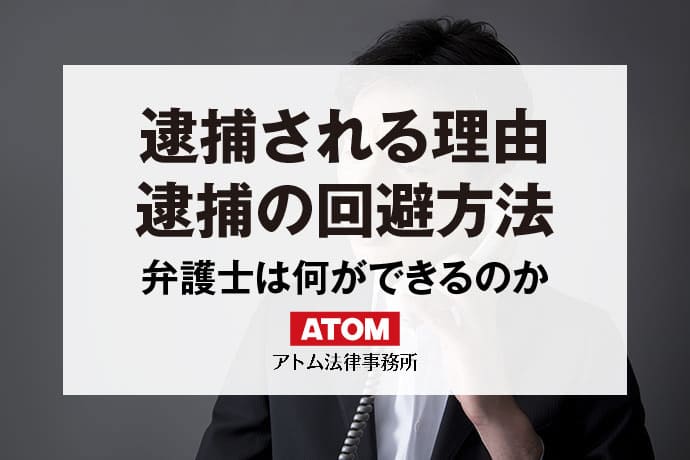
刑事事件における「逮捕の理由」は、法律で厳格に定められています。
逮捕の要件は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)が存在し、かつ被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれ(逮捕の必要性)が認められることです。
刑事事件をおこしてしまった人の多くが「逮捕されるのでは」と不安に感じますが、実際にはこの2つの要件を満たさなければ逮捕されることはありません。
逮捕の要件を正しく知ることは、逮捕を回避することにも繋がります。
この記事では、逮捕についての不安を抱えている方に向けて、まずは警察が被疑者を逮捕するために必要な「逮捕の理由」を詳しく解説します。さらに、逮捕後の刑事手続きと逮捕の回避方法についても分かりやすくご説明します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の要件
逮捕には、通常逮捕(後日逮捕)、緊急逮捕、現行犯逮捕の3つの種類があります。ここでは、それぞれの逮捕の要件や違いを解説します。
通常逮捕について
通常逮捕の要件
通常逮捕の要件は、①逮捕の理由、②逮捕の必要性です。
なお、通常逮捕は、捜査の結果、事件発生の後日に要件がそろって逮捕されることが多いため「後日逮捕」とも呼ばれます。
①逮捕の理由
「逮捕の理由」とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです(刑訴法199条1項本文)。「相当な理由がある」というためには、被疑者が犯罪行為をしたことを肯定できる客観的かつ合理的な根拠が必要です。捜査機関の主観的な疑いがあるだけでは足りません。
なお、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪(軽犯罪法違反など)については、被疑者が定まった住居を有しないか、正当な理由なく出頭要求に応じない場合に限り逮捕することができます(刑訴法199条1項ただし書)。
②逮捕の必要性
被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、罪証隠滅のおそれがない等明らかに逮捕の必要がない場合、裁判官は逮捕状の請求を却下しなければなりません(刑事訴訟規則143条の3)。
逮捕の必要性は、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様等を考慮して判断されます。
無職である、同居家族がいないといった事情があると逮捕の必要性は高まります。
逮捕状の要否
通常逮捕は逮捕状がなければ行うことができません。通常逮捕は、憲法33条の令状主義の要請に対応した原則的な逮捕の形態です。
逮捕状は、裁判官が逮捕の要件を事前に審査しすべて充足していると判断したときにだけ発付されます。
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間等が記載されています。
なお、有効期間中(原則7日間)に逮捕状を執行できない場合はその逮捕状で被疑者を逮捕することはできなくなります。その場合は改めて逮捕状を請求する必要があります。
逮捕状請求権者
逮捕状を請求する権利を有するのは、検察官と司法警察員です。警察官である司法警察員は、公安委員会が指定する警部以上の者に限られます(刑訴法199条2項本文)。
逮捕権者
逮捕状によって逮捕できる者は、検察官・司法警察員に加え、検察事務官と司法巡査も含まれます(刑訴法199条1項本文)。
緊急逮捕について
緊急逮捕の要件
緊急逮捕の要件は、①法定刑が比較的重大な一定の罪(死刑または無期もしくは長期3年以上の長期3年以上の拘禁刑に当たる罪)について、②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときです(刑訴法210条1項前段)。
要件①に該当するのは、殺人罪、傷害罪、窃盗罪、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪等です。
逮捕状の要否
緊急逮捕は逮捕時に逮捕令状を必要としません。
逮捕後の手続
緊急逮捕をした場合、逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を請求する手続をしなければなりません。
迅速な令状請求が求められるため、逮捕状の請求権者に制限はありません。すなわち、逮捕行為者でなくてもよく、検察事務官や司法巡査も逮捕状を請求できます。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません(刑訴法210条1項後段)。
逮捕権者
緊急逮捕できるのは、検察官、検察事務官、司法警察職員です。緊急逮捕時は、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び急速を要することを告げなければなりません(刑訴法210条1項前段)。
現行犯逮捕について
現行犯逮捕の要件
現行犯逮捕の要件は、①現行犯人であること、または、②準現行犯人であること、③逮捕の必要性があることです。
①現行犯人
現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」をいいます(刑訴法212条1項)。
「現に罪を行い」とは、逮捕者の目の前で犯罪行為を行いつつある者をいいます。
「現に罪を行い終わった者」は犯罪行為を終了した直後の者をいいます。
②準現行犯人
準現行犯人とは、次のいずれかに該当する者で、罪を行い終わってから間もないと明らかに認められる者をいいます(刑訴法212条2項)。
ア 犯人として追呼されているとき
犯人として追われまたは呼びかけられている状態を指します。追呼している人は被害者だけでなく、目撃者など第三者でも構いません。
イ 贓物又は明らかに犯罪の要に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
「贓物(ぞうぶつ)」とは窃盗の被害品など不法に領得された財物をいいます。「兇器」はナイフなどの凶器のことです。
ウ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
返り血を浴びた服を着て歩いているなど犯罪を行ったことが明らかといえる 痕跡が身体や被服に認められる場合をいいます。
エ 誰何されて逃走しようとするとき
「誰何(すいか)」とは声をかけて名前を問いただすことです。犯人が警察を見て逃げ出した場合も含まれます。
③逮捕の必要性
現行犯逮捕も身体の自由を奪う強制処分であるため、逃亡または罪証隠滅のおそれ(逮捕の必要性)が要件になると考えられています。
逮捕状の要否
現行犯逮捕の場合、例外的に逮捕状は不要とされています。現行犯人は、身体拘束の正当な理由があることが明白なので、裁判官の事前チェックを受けなくても人権侵害のおそれが少ないからです。
逮捕権者
現行犯逮捕は、「何人でも」逮捕状なく行うことができます(刑訴法213条)。「何人でも」とは、捜査機関だけでなく私人も含むという意味です。
例えば、電車内の痴漢事件で被害者が現行犯逮捕したと扱われ、引き続き勾留されるケースがあります。
逮捕されやすい犯罪は?
逮捕されやすい犯罪は、覚醒剤や大麻などの薬物犯罪です。
令和元年における刑法犯と特別法犯(過失運転致死傷等及び道交法違反を除く)を合わせた全体の身柄率は35.7%でした。
これに対し、覚醒剤取締法違反の身柄率は70.8%、大麻取締法違反の身柄率は62.6%です(引用元:令和2年版犯罪白書)。
薬物犯が逮捕されやすい理由は、覚醒剤や大麻は処分が容易で証拠隠滅のおそれが高いためです。
逮捕されるケースとしては、職務質問で不審な粉末の所持が判明し簡易試験をした結果、覚醒剤反応が出て現行犯逮捕される場合や、大麻栽培が発覚し現行犯逮捕や通常逮捕される場合などがあります。
刑事手続きの流れ
ここでは、逮捕後の刑事手続の流れと逮捕されない場合(在宅事件)の刑事手続の流れをご説明します。
逮捕後の刑事手続の流れ
通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕のいずれの場合も、逮捕後の手続は共通です。大まかな流れは次の①~⑦のとおりです。
逮捕後の刑事手続の流れについて、さらに詳しく知りたい方は『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』も参考にしてみてください。

①警察署に連行され取調べを受ける(その後留置場で生活)
②逮捕後48時間以内に検察官へ送致
③送致後24時間以内に勾留請求
④勾留決定が出されると10日間勾留
⑤勾留期間が延長されると最長10日間勾留
⑥検察官による起訴・不起訴の決定(逮捕から最長23日後)
⑦起訴後は被告人として勾留が続く
大切なご家族が逮捕されたらいち早く面会して逮捕の理由を知りたいと思いますよね。
しかし、ご家族など一般の方が面会できるのは④以降に限られます。つまり、逮捕から最長3日間はご家族でも面会できないのです。警察からご家族に連絡がくる場合も、逮捕の理由まで詳しく教えてくれることは期待できません。
では、どうすればいち早く逮捕の理由を確認できるのでしょう?
おすすめは、私選弁護士に依頼することです。私選弁護士であれば逮捕直後の①の段階からご本人に接見できます。一方、国選弁護人は④以降に選任されます。逮捕されたらスピード勝負。逮捕の理由をいち早く把握して不起訴を目指すなら、私選弁護士に依頼するのが最善策です。
逮捕されない場合(在宅事件)の手続の流れ
逮捕理由があっても、逃亡・罪証隠滅のおそれがないケースでは、逮捕されません。
そのような刑事事件は、被疑者在宅のまま犯罪捜査が進む「在宅事件」として扱われます。在宅事件になれば職場や学校に通い日常生活を送ることができます。在宅事件の典型例としては、軽微な交通事故事案が挙げられます。
もっとも、在宅事件となっても無罪になるわけではありません。在宅事件では、捜査→書類送検→検察官による起訴・不起訴の決定という流れが一般的です。起訴後に裁判所で刑事裁判を受け有罪判決が下される可能性もあります。
在宅事件で注意していただきたいのが、警察署や検察庁からの呼び出しがあれば素直に応じるということです。正当な理由なく呼び出しに応じないと逃亡のおそれありと判断され逮捕されることになりかねません。実務上、3回程度呼び出しに応じないと逮捕のおそれがあるとされています。
逮捕を回避したいなら弁護士に相談!
ここでは、逮捕を回避する方法を詳しくご説明します。ポイントは、早期に弁護士に依頼すること。法律の専門家が逮捕の理由や逮捕の必要性がないことを説得的に主張することで、逮捕の回避が期待できます。
また、アトム法律事務所が過去に扱った事件の中から、早期に弁護士が介入したことによって逮捕を回避した事例もご紹介します。
逮捕の理由がないことを主張する
逮捕を避けるには、逮捕の要件がそろっていないと主張することが重要です。そのためには、弁護士に依頼して「逮捕の理由」がないことを主張しましょう。
弁護士は、逮捕の理由がないことを主張する意見書の提出など、逮捕を回避するための活動が可能です。
冤罪事件である場合には、被疑者が犯罪を行った客観的証拠がないことや今ある証拠の問題点などを指摘します。身に覚えのない犯罪の疑いをかけられている場合は、早急に弁護士にご相談ください。
住居に侵入して盗撮などをしたが、意見書を提出して逮捕を回避した事例
隣に住む女性宅に窓から侵入し、隠しカメラを設置。下着なども物色したが、窃取には至らず。盗撮、住居侵入、窃盗未遂の事案。
弁護活動の成果
逮捕回避意見書を提出し、逮捕を回避。また、被害者と示談を締結するなどの情状弁護を尽くし、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
早期に示談を成立させる
逮捕を回避するのに効果的なのが示談を成立させることです。示談の中で被害届を提出しない旨を合意すれば、警察が関与する前に紛争を解決することが可能です。
刑事事件になった場合でも、示談成立により逮捕を回避できる可能性が高まります。逃亡や被害者を脅すといった罪証隠滅のおそれはないと判断されやすくなるからです。
もし逮捕されてしまっても、示談が成立すれば早期釈放につながることが期待できます。被害者が加害者側を許すという宥恕の意思を示していれば、早期釈放の可能性はより高くなります。
示談の成立は不起訴の可能性も高めることにもつながります。不起訴になれば100%前科がつきません。
示談の成立には弁護活動の実績がものをいいます。アトム法律事務所は、窃盗、痴漢、傷害、交通事故など様々な事例で示談を成立させ逮捕を回避した豊富な実績があります。示談交渉ならアトム法律事務所にぜひお任せください。
任意出頭に付添い逮捕回避の説得を行う
「警察に任意出頭を求められたが逮捕されないか不安」という方にとっても弁護士は心強い味方になります。
弁護士は任意出頭に付き添って一緒に警察署に行くことが可能です。取り調べのアドバイスを行うことはもちろん、逮捕回避のため警察を説得することも弁護士の大切な役割です。
例えば、定職があることや扶養している同居家族がいることを書面で明らかにし、逃亡のおそれがないことを主張します。
さらに、弁護士が窓口となって必ず出頭させる旨の誓約書を提出することもあります。
説得の結果、逮捕が回避されれば在宅事件となって日常生活を送ることが可能です。
電車内での痴漢(条例違反)で、弁護士が出頭に同行し逮捕を回避した事例
電車内において、被害者女性のスカートや下着の中に手を入れたとされる痴漢事案。駅員室に連行される際に逃走するも、後のことが心配になり弁護士に相談するに至った。後に迷惑防止条例違反として検挙された。
弁護活動の成果
警察への出頭に同行し身柄拘束をしないよう要請したところ在宅事件となった。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
自首に同行して逮捕回避の説得を行う
「犯行後に逃走してしまったけれど、後日逮捕されないか不安」
そんな方は、自首を検討するのも一つの方法です。
自首が成立すると、裁判官の裁量によって刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。
一人で自首するのが不安な方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は自首に同行することが可能です。
弁護士は逮捕の必要がない事情を事前に聴き取ります。その内容を書面にまとめて警察に提出したり、担当捜査官と面談して直接説得します。
なお、犯人が特定されてしまった後は刑法上の自首は成立しません。自首するかどうかお悩みであれば早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当て逃げをしたが、自首と意見書の提出により逮捕を回避した事例
当て逃げの事案。車を運転中、ガードレールに接触。反動で対向車にも衝突した後、依頼者は現場を逃走。なお、対向車の乗員2名にケガはなかった。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
自首に同行して意見書を提出したところ、在宅事件となった。罪状としては当て逃げの報告義務の違反のみであり、情状弁護を尽くし、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴
まとめ
①逮捕の理由と②逮捕の必要性の2つの要件を満たさなければ、通常逮捕は認められません。そのため、逮捕を防ぐには、これらの要件を満たしていないことを適切に主張していくことが有効です。
弁護士は、意見書の提出や示談交渉、自首・出頭への同行など、逮捕の回避を目指した活動を行います。
逮捕を避けるための弁護活動は、どれだけ迅速かつ的確に行えるのかがポイントです。ご依頼のタイミングが早いほど、逮捕を避けるための選択肢の幅も広くなります。
刑事事件の加害者となってしまい、逮捕がご心配な方は、アトム法律事務所の24時間365日繋がる法律相談予約窓口に今すぐお電話ください。



