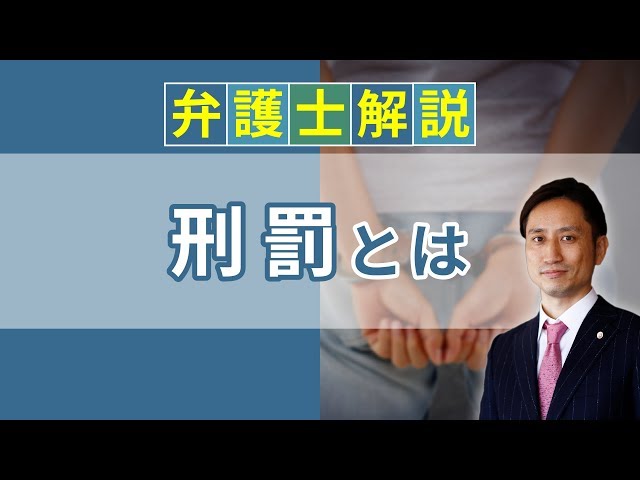- アトム弁護士相談
» - 法令データベース
» - ひき逃げ
ひき逃げの刑罰・捜査の流れ・裁判例
ひき逃げで適用される刑罰
ひき逃げとは、人身事故を起こした後に、負傷者を救護したり、道路上での危険防止など必要な措置を講じたりすることなく、その場から逃走することを言います。
ひき逃げをすると、道路交通法上の救護義務違反として処罰されます。
道路交通法117条1項
5年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
人身事故を起こしたにもかかわらず、停止して被害者の応急手当や救急車を呼ばず、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなかったときは、この罪に当たります。
なお、「人の死傷」が運転者の運転に起因する場合は、後述の条文でより重く処断されます。
道路交通法117条2項
10年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
第百十七条
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
被害者を車両等でひいて死亡させるなどした場合は、「人の死傷」が「運転者の運転に起因する」ものとして、この罪でより重く処断されます。
「ぶつかったのが人かもしれない」という認識があれば、明確な認識がなくとも故意があったとして処罰されます。
ひき逃げの捜査の流れ
ひき逃げは、「事故後に怖くなって現場から逃走する」という態様のケースが典型例です。
ただ、「ぶつかったことに気が付かなかった」「何かにあたった感覚があったものの事故が発生しているとは思わず現場を去った」という態様で、自ら警察に出頭するなどするケースも相当数あります。
通報された場合
1
目撃者や被害者が通報
2
警察官が認知
3
捜査
ひき逃げ事件は、通常事故の目撃者や被害者などによって通報が行われます。
警察は、防犯カメラの映像を解析したり聞き込みをしたりして、犯人の特定に努めます。
身元が特定された場合は、その後警察官が自宅に赴くなどして、取調べへの協力を迫られることになるでしょう。
自首する場合
1
車の傷に気が付く
2
自首や現場への出頭
3
取調べを受ける
ひき逃げでは、「事故の発生に気が付かなかった」「何かにぶつかった感覚はあったものの、事故が起きているとは思わなかった」という場合もあり、帰宅してから車の傷を確認し、ひき逃げをしてしまったと気付くこともあります。
その場合、自首をしたり事故現場に出頭するなどして、自ら警察の取調べを受ける方も多いようです。
ひき逃げの有名裁判例
ひき逃げは、道路交通法117条により救護義務違反として処罰されます。
人をひいたことに気付かず、そのまま走り去ったと弁解される事案がしばしばありますが、ここでは、人を死傷させたことについて未必の故意があれば足りるとした判例をご紹介します。
道路交通法117条の罪の成立に必要な事実の認識の程度について判示した判例

裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和45年(あ)第2031号 判決年月日:
昭和47年3月28日
判決文抜粋
「道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる旨の原審の判断は相当である」