10年以下の拘禁刑
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
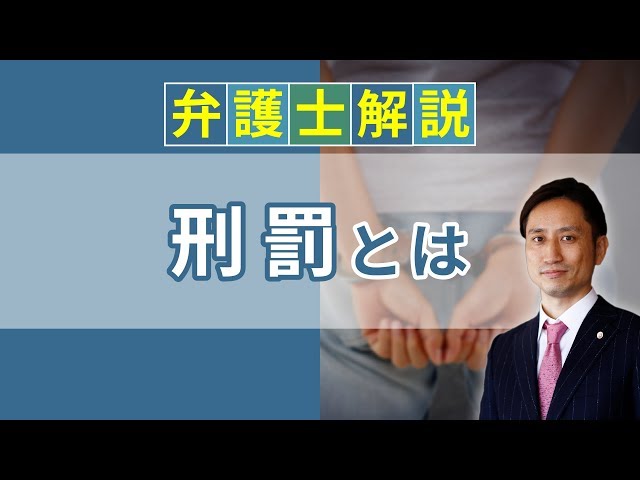
被害者の財物交付の判断の基礎となる重要な事実を偽って勘違いさせ、その勘違いに基づいて被害者から財物の交付を受けたり、財産上の利益を得た場合、詐欺罪・詐欺利得罪として処罰されます。
被害者がだまされなかったり、財物の交付等をしなかった場合でも、だまそうとする行為をした時点で詐欺未遂罪として処罰されます。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
「人を欺く」行為とは、被害者を誤解、勘違した状況にさせ財産を処分させるおそれのある行為でなければなりません。
例えば人をだまして注意をそらした隙に持ち去る行為などは、詐欺ではなく窃盗です。
なお詐欺罪は未遂の場合も罰せられるため、「人を騙そうとした」という段階で、罪に問われ得ます。
第二百四十六条
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「財産上の利益」とは、財物以外の財産的利益を意味し、たとえば債権を取得したり、労務・サービスの提供を受けることを言います。
人を欺いてこれらの利益を得た場合、本罪によって処罰され得ます。
詐欺といえば、いわゆる振り込め詐欺が典型例です。
被害届の提出で捜査が開始されるケースや、詐欺に気付いた被害者が警察と協力する「だまされたふり作戦」により検挙するケース、詐欺グループの1人が検挙され、グループ全体が芋づる式に検挙されるケースもあります。
被害者が被害届を提出した場合、警察は銀行等の防犯カメラなどを捜査し被疑者の特定に努めます。
被疑者の特定に至った場合、警察署において取調べを受けることになるでしょう。
被害者が自ら詐欺であることに気付いたり、銀行や郵便・宅配事業者が詐欺被害を発見するケースがあります。
そのような場合、通報を受けた警察が「だまされたふり作戦」を行う場合があります。
詐欺の受け子や出し子が現場に現れた際に、隠れていた警察がその場で検挙を行います。
警察は、詐欺グループの受け子や出し子などを検挙した際、詐欺グループ全体の検挙を目指して取調べを行います。
特定に至った被疑者について、芋づる式に検挙していく流れになります。
ここでは、詐欺罪の実行行為である欺罔行為(だます行為)について、判示した判例を2つご紹介します。
また、欺罔行為には直接関与していない、いわゆる受け子について詐欺罪の成立を認めた判例もご紹介します。

「誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する」
誤振込みであることを知りながら、これを黙って銀行員から払い戻しを受けた行為が詐欺罪の欺罔行為にあたるとして詐欺罪の成立を認めた判例です。
銀行にとって、誤振込みの事実は支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であり、誤振込みを受けた者は、その旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があるとされ、これに反する行為は欺罔行為にあたるとされました。
このように、積極的に虚偽の事実を述べなくても、詐欺罪にあたる可能性があります。

「本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる」
預金を下ろす必要があるとの嘘、警察に協力する必要があるとの嘘、警察官が訪問するとの嘘を述べた行為につき、詐欺罪の実行の着手を認めた判例です。
現金の交付を求める文言を述べていなくとも、嘘の内容が、交付の判断をする前提となる重要なものであり、交付を求める行為に直接つながる嘘を含み、被害者が被告人の求めに応じて即座に交付してしまう危険性を著しく高めるものであるとして、詐欺罪の実行の着手が認められました。

「被告人は,本件詐欺につき,共犯者による本件欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに,共犯者らと共謀の上,本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人は,その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき,詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である」
共犯者による欺罔行為後に、「だまされたふり作戦開始」を認識せず荷物を受け取った受け子に詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めた判例です。
欺罔行為に関与していなくとも、詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為へ関与すれば、共同正犯が成立するとされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。