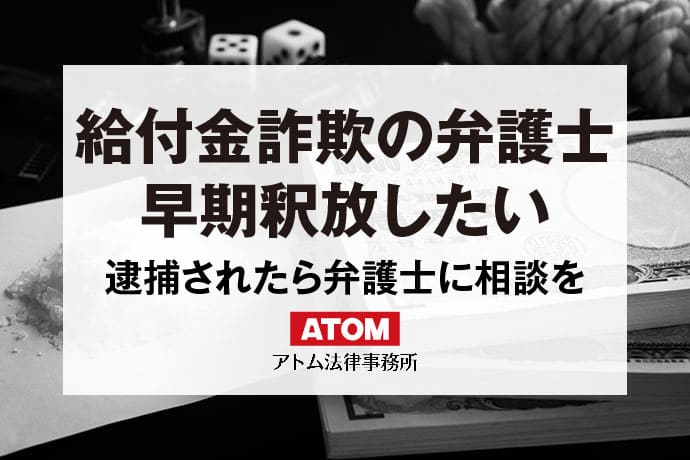
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
家族が給付金の不正受給で逮捕された場合、すぐに弁護士に相談してください。
給付金の不正受給は詐欺罪が成立し、10年以下の拘禁刑になります。詐欺罪には罰金刑がないため、有罪判決を受けると刑務所に入る実刑判決か、執行猶予付きの判決のどちらかとなります。
執行猶予付きの判決または不起訴を獲得するには法律に精通した弁護士の協力が重要です。
この記事では、給付金詐欺の刑罰や逮捕の可能性などの基本的な情報だけでなく、早期釈放や執行猶予の獲得のために、家族には何ができるかまでを刑事事件に詳しい弁護士が解説しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
給付金詐欺とは
給付金詐欺とは、国や地方自治体が支給する給付金や支援金を、ウソの申請(虚偽申請)をして不正に受給することをいいます。
給付金詐欺はコロナ禍で広く行われた「持続化給付金」や「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」などの大規模な給付金制度が開始されたことをきっかけに流行りだしました。
給付金や支援金は、その多くが国民の税金など、公的なお金で賄われています。
本来、新型コロナの影響などで本当に生活や事業に困っている人を助けるためのお金を、ウソをついてだまし取る行為は、社会的に悪質とみなされます。
そのため、「名義を貸しただけ」「誘われただけ」という軽い気持ちであったとしても、詐欺罪の共犯として逮捕され重い刑罰が科される可能性があります。
給付金詐欺には、個人を対象に、経済産業省の職員などを装って「給付金が受けられる」と騙し、手数料などの名目で金銭をだまし取るケースもあります。
このような手口は、いわゆる一般的な詐欺事件として扱われます。
なお、今回の記事では一般的な詐欺事件ではなく、実際には給付金の受給資格がないにもかかわらず、虚偽の申請を行って給付金を受け取る「不正受給型の詐欺」に焦点をあて、解説します。
給付金詐欺の特徴は?
逮捕される可能性がある
給付金の不正受給は逮捕される可能性があります。
すでに建設業の関係者や風俗店経営者が不正受給をしていた疑いで逮捕されたことが報道されています。消防士や警察官などの公務員も不正受給により逮捕されたことが話題になりました。
経済産業省をはじめ、総務省、警察庁など、国をあげて持続化給付金詐欺の取り締まりは強化されており、逮捕の可能性が十分にある犯罪です。
不正受給の具体的な内容は、「事業を実施していないにもかかわらず、事業をしていると虚偽の申請をし給付金の交付を受ける」などが挙げられます。
他にも、「各月の売上げや名義を偽って申請し給付金を受け取る」というケースも典型的です。国に対して虚偽の申請を行い、それにより給付金を交付させます。
未遂でも逮捕の可能性がある
ウソがバレて給付金の審査に通らなかった場合や、途中で申請を取り下げた場合でも逮捕される可能性があります。
詐欺罪には未遂罪が定められており、ウソの申請書やデータを事務局に送信・提出した時点で「詐欺の実行に着手した」とみなされます。
たとえ1円もだまし取れなかったとしても、証拠があれば詐欺未遂罪として逮捕・処罰される可能性は十分あります。
一方で、自ら取り下げた場合は、刑が免除されることもあります。
審査で不正が発覚する前に、自らの意思で申請を取り下げた場合、中止犯(刑法43条ただし書)が成立する可能性があります。
中止犯と認められると、法律上、刑が必ず軽くなるか、または免除(刑罰が科されない)されます。
実名公表のリスクがある
給付金の中でも、持続化給付金の不正受給者は、持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき、経済産業省公式サイトにおいて法人名や個人名(個人事業主)が公表されることがあります。
全国に詐欺を行ったことを知られるのは身内に知られるリスクだけでなく、社会的信用を大きく下げることになります。
示談ができない
給付金詐欺の被害者は国です。 給付金事務局や検察庁といった国の機関は、国民の税金を原資とするお金をだまし取られた立場であり、一職員が私的な許し(宥恕)を与えることができません。
一方で、国側が許すことはしませんが、被害が回復されたという事実は、処分を決める上で重要視されます。
- 被害弁償(返金)を完了させること
- 深く反省している態度を示すこと
この2点が、示談ができない給付金詐欺において、不起訴(起訴猶予)や執行猶予付き判決を獲得するために、重要な意味を持ちます。
給付金詐欺で逮捕される際の罪名と刑罰
国の支援制度を利用し、給付金を騙し取る犯罪は悪質とされています。持続化給付金の不正受給が犯罪であることは、経済産業省の公式サイトにも明記されています。
給付金詐欺がどのような罪に問われるのかを以下で詳しく解説します。
給付金詐欺は詐欺罪にあたる
給付金詐欺は詐欺罪という刑事事件の一類型です。詐欺罪は刑法246条に規定されており、条文には「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と書かれています。
詐欺罪の成立要件
- 欺罔行為(人を欺く行為)
相手方が財物等の処分行為をするか否かを決する上で重要な事実について、虚偽の言語や動作を用いて人を錯誤に陥らせる行為のこと。
積極的な虚構、事実の歪曲・隠蔽、既に錯誤に陥っている状態の継続なども含まれる。 - 錯誤
欺罔行為によって相手方が誤信(錯誤)に陥ること。 - 交付行為(処分行為)
錯誤に基づき、相手方が財物や利益を交付する行為。 - 財物・利益の移転
行為者や第三者が財物の占有や財産上の利益を取得すること。 - 主観的要件
故意および(1項詐欺の場合)不法領得の意思。
これらの要件の間には因果関係が必要であり、「欺罔行為→錯誤→交付行為→受領行為」という特定の因果経路を経て結果が発生することが求められます。
給付金詐欺の刑罰
給付金詐欺で問われる詐欺罪の刑罰は「1ヶ月以上、10年以下の拘禁刑」が処罰として予定されており、罰金刑はありません。つまり、有罪判決になったら執行猶予がつかない限り刑務所に収容されることになります。
持続化給付金の不正受給は、初犯であっても裁判になり、実刑判決を受ける危険性が否定できません。
単独犯なのか、共犯なのか、共犯者がいる場合には詐欺グループの中でどのような立ち位置(役割)だったのかなどが精査され、罪の重さが決められます。
関連記事
・詐欺罪は逮捕されたら初犯でも実刑?懲役の平均・執行猶予の割合もわかる
給付金詐欺で逮捕された後の流れ

給付金詐欺による逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は最大で23日間であり、その間警察や検察などの捜査機関による事件の捜査がなされます。捜査が終了すると、起訴・不起訴の判断が下されます。
日本では起訴後の有罪率は99.9%に上るため、前科がつくことを防ぐには不起訴処分を目指すことが重要です。
前科がつけば、個人の社会生活や職業生活、名誉・信用、プライバシーなど多方面にわたるリスクを生じさせます。
ご家族や自身を守るためにも、起訴までの間に弁護士に相談し、適切な対応を取って不起訴の可能性を高めることをおすすめします。
関連記事
・刑事事件の裁判の実態は?裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?
給付金詐欺で逮捕された際に弁護士ができること
早期釈放を目指せる
家族が給付金詐欺で逮捕された場合、まず考えるべきは早期釈放です。逮捕されると本人は完全に身動きが取れないので家族や恋人など、本人と近しい関係にある方が弁護士にご相談いただく必要があります。
逮捕に続き勾留という段階に入ると、起訴・不起訴の判断が下るまで少なくとも10日間、延長されればさらに最大10日間は自宅に帰れません。
給付金詐欺では事前に裏取りが行われ逮捕令状が発せられることになります。いわゆる後日逮捕(通常逮捕)という形がとられ、勾留まで行われる可能性が高いといえます。
早期釈放を希望するには、逮捕直後から弁護士に活動をしてもらい、検察官や裁判官に働きかけてもらうことが必要です。
不起訴が主張できる(不正受給が無実の場合)
不正受給が無実だった場合は、不起訴を主張しなければ刑事裁判になってしまう可能性があります。しかし、法律に詳しくなければ法律の専門家である検察官に不起訴を説得的に主張することは難しいものです。
そこで、弁護士に対応してもらう必要が出てきます。弁護士は、被疑者本人から詳しく事情を聞き、証拠をもとに検察官に不起訴を訴えます。
起訴されると公開の法廷に立たされ裁判を受けなければなりません。たとえ無罪を勝ち取れたとしても、公の場に被告人として晒されること自体が社会的ダメージとなるでしょう。
実名報道される危険も考慮すれば、できる限り不起訴処分を目指すことが大切です。
不正受給が事実でも起訴猶予を目指せる
起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が認められる場合でも、検察官が「訴追の必要がない」と判断したときに不起訴とする処分です(刑事訴訟法248条)。
起訴猶予は、犯罪の軽重や被疑者の性格・年齢・境遇、犯行後の反省や被害弁償など、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。
執行猶予獲得に向けた弁護活動の展開
不正受給の事件で起訴された場合には、実刑を回避しなければいけません。執行猶予を獲得すれば、刑務所に入ることなく、普段の生活に戻ることができます。
ただし、3年を越える拘禁刑を言い渡されると執行猶予は絶対に付かないため、少しでも刑を軽くしてもらう弁護活動が必要となります。
給付金の不正受給をした場合には、刑事裁判になることも見越し先手を打つことが肝要です。漫然と逮捕を待ち、刑事手続きを受け身で考えていては実刑の可能性が高まってしまいます。
もし、自分が不正受給をしていた、家族が不正受給をしていた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。給付金の自主返還や警察への自首など、できることをして執行猶予の可能性を高めておくことが大切です。
アトムの弁護士が対応した給付金詐欺の事例
持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給
詐欺罪(不起訴処分)
交際相手と持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給した後、警察に自首をしたケース。詐欺罪の事案。
弁護活動の成果
依頼者が自ら進んで詐欺を行ったわけではなく、相手の指示に従った結果だったことを強調。依頼者が警察に自首していること、全額返金の意思を示していることが考慮された結果、不起訴を獲得。
給付金詐欺での逮捕についてよくある質問
名義を貸しただけで、お金は受け取っていません。それでも逮捕されますか?
はい、逮捕される可能性は十分にあります。
たとえ報酬を受け取っていなくても、名義を貸すという行為は、詐欺という犯罪計画の重要な部分(実行行為)を担ったとみなされます。
「自分はだまされた側だ」「言われた通りにしただけ」という言い分が認められず、詐欺の共犯として逮捕・処罰されるケースは非常に多いです。
不正受給したお金を全額返金したら、逮捕されませんか?
絶対に逮捕されないという保証はありません。しかし、返金(被害弁償)は、反省の態度を示す重要な証拠となります。
逮捕前に自主返還した場合は、捜査機関が逮捕の必要はないと判断し、逮捕を回避できる(在宅捜査になる)可能性が高まります。
逮捕後に返還した場合は、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性や、裁判になった場合に執行猶予がつく可能性を高めることができます。
いずれにせよ、返還は何もしない場合と比べて、ご自身にとって圧倒的に有利な事情となります。
給付金詐欺の時効は何年ですか?
詐欺罪の公訴時効は7年です。
公訴時効は一般的に、不正受給した給付金が口座に振り込まれた日(犯罪が完了した日)からカウントされます。未遂の場合は、ウソの申請をした日からカウントされます。
時効を待つのは、いつ警察の捜査が始まり逮捕されるか分からない、精神的に不安定な状態が続くことになりますので、得策ではありません。
また、時効を待っている間に逮捕されてしまえば反省していないとみなされ罪が重くなる可能性もあります。
家族が給付金詐欺で逮捕されてしまいました。今すぐ何をすべきですか?
なるべく早く弁護士に初回接見を依頼してください。
逮捕から最大72時間は、ご家族であっても面会できないことがほとんどです。しかし、弁護士はいつでも、誰の立ち会いもなく接見できます。
弁護士がすぐにご本人と面会し、取り調べのアドバイスや、その後の身柄拘束を防ぐための活動を始めることが、早期釈放と最終的な処分の軽減のために重要です。
給付金詐欺による逮捕でお困りの方へ
給付金詐欺の事件は、通常の詐欺事件と異なり被害者と示談をして解決するということができません。給付金詐欺の被害者は国であり、国とは示談ができないからです。
重要なポイントは事件後の行動や反省の程度、再犯防止策の有無です。検察官への事情の説明、裁判での立ち回りを考えたとき、できるだけ早く弁護士に相談し助言を求めることがお勧めです。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に力を入れて取り組んできました。詐欺事件も数多く扱い、様々なケースを経験しています。
弁護士は法律のプロフェッショナルですが、分野によって経験値も違えば得意・不得意もあります。給付金詐欺は刑事事件なので、刑事事件の実績があるアトムの弁護士にぜひご相談ください。
アトム法律事務所は24時間、年中無休で専属スタッフが対応します。家族が逮捕されたなどの緊急の場合は、いつでもお問い合わせください。



