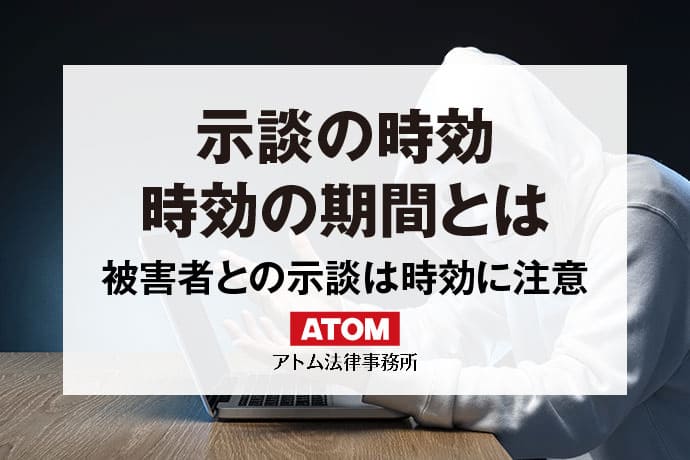
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
示談をするうえで、時効は注意しておくべき重要なことがらです。時効には、民事事件としての時効と、刑事事件としての時効があり、それぞれ全く意味が違います。
また、交通事故における損害賠償請求の場面では、その交通事故がどのようなものであったか、いつから時間の経過をカウントするのかで、「消滅時効」にかかるまでの期間は変わります。時効は示談の流れにも関係してくることですので、弁護士解説の中で正しい知識を押さえておいてください。
示談の時効は「消滅時効」に注意|交通事故の損害賠償請求権
示談をするときには、時効という概念に注意する必要があります。民法に定められた「消滅時効」について押さえておきましょう。一定期間、権利の行使がないことで、その権利が消滅することがあります。その時効のことを「消滅時効」といいます。加害者の場合は、被害者から損害賠償請求がされるかどうかに関係してくる重要な概念といえます。
交通事故の示談|加害者は被害者に損害賠償を請求される
例えば、交通事故の場合を考えます。交通事故が発生すると、加害者は被害者から損害賠償請求されることが予想されます。被害者は、交通事故という加害者の行った不法行為に基づいて、加害者に対して損害賠償請求権という権利を取得します。これを根拠に、加害者は被害者から示談金(保険金)の支払い請求を受けることになります。
交通事故の中でも、人身事故について考えてみます。仮に、被害者が損害賠償請求権を行使せず、5年が経過した場合には、被害者が持つ加害者への損害賠償請求権は消滅時効にかかります。すると、加害者はその時効を援用することで、損害賠償請求を受けることがなくなります。これが、交通事故の損害賠償に関する時効です。
弁護士が解説する示談についての「消滅時効」の意味
ある権利が消滅時効にかかると、その権利は行使できなくなってしまう可能性があります。つまり、犯罪の加害者は、被害者から慰謝料などの損害賠償請求を受けることがなくなる可能性が出てくるということです。民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権を定める規定があります。消滅時効では、被害者がこの権利を行使しないのであれば、法的に保護する必要がない、という考えが前提にあります。
窃盗や詐欺などの犯罪では、被害者は損害および加害者を知ったときから3年間、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないときは、その権利は消滅時効にかかるとされています。また、人身事故など、人の生命または身体を害する不法行為に基づくものの場合は、5年間が消滅時効完成までに要する期間となります。時効は、時間の経過で権利義務の立証が難しくなることや、法律関係を早期に安定させるべきという趣旨で認められた制度です。
加害者が被害者から請求される示談金とは|示談交渉の時効
加害者が被害者から請求される示談金には、被害者が怪我を治療するときに要した治療費や、通院費、休業損害に加え、精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料が含まれます。交通事故では保険会社が加害者に代わって被害者に示談交渉を進めます。任意保険の保険会社が被害者に支払う保険金は、「債務の承認」にあたり、時効を更新する事由になります。
加害者は被害者と示談交渉をする中で、時効に注意しながら示談金の支払いを検討します。消滅時効は被害者の損害賠償請求権の消滅にかかる問題であり、加害者が賠償義務から解放されるかどうかの問題ともいえます。厳密には、時効は加害者にとって「示談交渉できなくなるリミット」というわけではありません。
加害者側の弁護士が注意する示談の時効|3つの疑問
示談に関して、弁護士が加害者側からよく受ける質問をまとめました。ここでは、具体的に時効の期間、裁判に関する時効、時効の更新ケースについて、解説したいと思います。時効は、言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、実際に加害者になった場合には、法律上の意味を正確に押さえておく必要があります。
示談の時効① 被害者からの示談金・損害賠償請求は「3年」が期限?
加害者が被害者から示談金や損害賠償を請求されるにあたっては、その消滅時効の期間は、原因となる不法行為の内容やいつから時間の経過をカウントするかで異なります。不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条と724条の2に規定されています。
724条1号には「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」と定められています。窃盗、詐欺、横領、名誉毀損などの刑事事件が原因となる場面が想定できます。同条2号では「不法行為の時から二十年間行使しないとき」とあり、「3年」「20年」はどこを起算点(カウントのスタート地点)とするかで変わるということになります。また、724条の2には、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする」と規定されています。交通事故の人身事故のときには、これに注目することになります。
示談の時効② 加害者が裁判にかけられる時効は?
加害者が示談をする上で、時効は重要な概念です。民法上、時効には特定の権利を消滅させる効果があります。権利がなくなれば、加害者は民事裁判の被告になる危険がなくなります。民事裁判は、原告(被害者)が、損害賠償請求権に基づいて賠償金の支払いを被告(加害者)に求めるものです。つまり、裁判の前提になる権利が無くなると、裁判で損害賠償請求されるおそれがなくなることになります。
また、裁判には刑事裁判もあります。刑事裁判に関係する時効もあり、詳細は後述します。「公訴時効」という刑事事件に関する時効が成立すると、刑事裁判の被告人になることはなくなります。被告人にならず事件が終了すれば、前科がつくことはありません。
示談の時効③ 時効が更新・猶予されるケース
被害者の損害賠償請求権の時効については、「更新」という概念があります。令和2年の民法改正で「時効の中断」は改められました。時効が更新されるケースは、法定されています。加害者が損害賠償請求の金額の一部でも支払いをすると、「債務の承認」があったとして、時効が更新されることになります。
また、被害者が加害者に対して内容証明郵便を送り「催告」をした場合には、6ヶ月間時効の完成が猶予されます。時効の更新のためには、裁判上の請求や支払い督促の申立てを行う必要があります。加害者側の弁護士が被害者と示談交渉をする際には、被害者からの催告にも注意を払い、刑事手続きとの関係も総合的に考慮して活動を行います。
加害者が知っておくべき示談の期限|刑事・民事
加害者が知っておくべき時効には、刑事事件の時効と民事事件の時効があります。被害者と示談交渉を行うにあたっては、時効も意識しながら進めることが大切です。厳密には、示談交渉それ自体に「期限」はありませんが、示談は刑事処分にもかかわることですので、注意しておく必要があります。
示談の時効は刑事事件にも関係する
加害者が示談をする上で考えなければならないもう一つの時効が、刑事事件としての時効、「公訴時効」です。公訴時効は成立すると、起訴され刑事裁判にかけられることがなくなります。つまり、懲役刑などの刑罰を受けることがなくなります。予定される刑罰の重さによって、何年の公訴時効になるかが決まります。
公訴時効が成立すれば、その事件が捜査途中であっても捜査は打ち切られ、事件は終了します。弁護士が示談交渉を考える中では、この公訴時効についても注意しています。
示談の時効は交通事故では2種類ある(物損事故・人身事故)
先にもふれましたが、交通事故被害者の損害賠償請求権は時効により消滅することがあります。そのとき、物損事故か人身事故かで時効の期間は変わります。物損事故の場合は、事故日を起算点にして、3年の経過で消滅時効を迎えます。人身事故の場合は、事故日を起算点にして、5年の経過で消滅時効を迎えます。
なお、人身事故では、後遺障害が残った場合には、症状固定の日を起算点にして5年が経過すると時効が完成します。また、被害者が死亡した場合には、被害者遺族の加害者に対する損害賠償請求権は、被害者が死亡した日からカウントして5年の経過で消滅時効が完成します。
示談開始のタイミング|時効から逆算する弁護士の活動
弁護士が示談を行う際には、時効から逆算して活動計画をたてます。示談は民事上の解決手段でもあると同時に、刑事処分に影響する重要なことがらです。そのため、刑事事件の手続きとも併せ考えながら対応を進めます。
交通事故など、被害者が入院治療中であったり亡くなってしまった場合には、被害者やそのご家族の心情に十分配慮した対応が必要です。示談のタイミングや、接触の方法については慎重さが求められます。
示談の流れや開始すべきタイミングについて詳しく知りたい方は『刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?』の記事をご覧ください。
まとめ
最後にひとこと
加害者が被害者と示談交渉をする上で、時効は常に注意しておくべき重要なことです。とはいえ、示談は被害者との話し合いによる合意で解決を目指すもの。十分な経験値のある弁護士に相談して、被害者・加害者が互いに納得のいく解決を目指すことが望ましいといえます。無理に単独で動こうとするよりも、まずは法律の専門家である弁護士に意見を求めていみてはいかがでしょうか。
アトムの解決実績
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
窃盗(万引き):不起訴処分
古着店において、衣服5点(時価合計数万円相当)を万引きしたとされたケース。犯行直後に店員に見つかり、現場から逃亡したあと後日逮捕された。窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
不同意わいせつ:不起訴処分
路上において、背後から被害者女性に抱き着き、衣服の中に手を差し入れて胸を揉んだとされる強制わいせつの事案。依頼者は犯行後に逃亡したものの、後日逮捕された。
弁護活動の成果
裁判官に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分を獲得。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
殺人:不起訴処分
被害者に対して、友人らと共に、レンガで殴打するなどの暴行を加えたとされるケース。殺人未遂の事案。
弁護活動の成果
情状弁護を尽くし、不起訴処分を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
もっと多くの事案を知りたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
最初から最後まで、色々と教えて頂き、心の支えになりました。
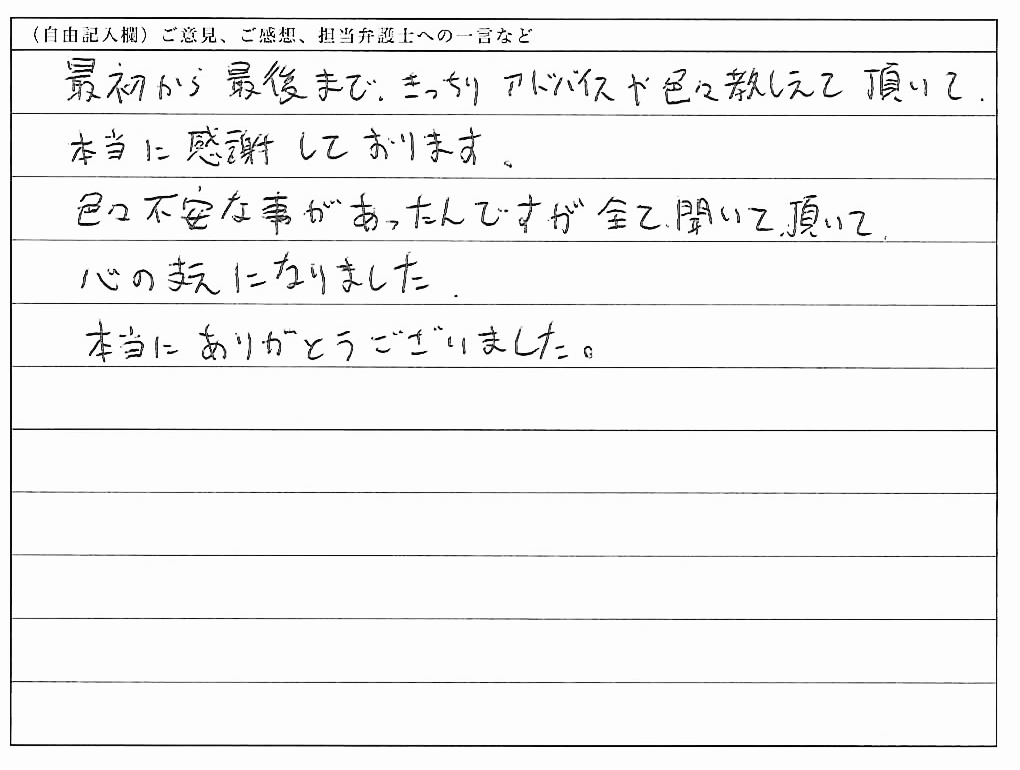
最初から最後まできっちりアドバイスや色々教しえて頂いて本当に感謝しております。色々不安な事があったんですが、全て聞いて頂いて心の支えになりました。本当にありがとうございました。
親身に話を聞いて頂けて、安心することができました。
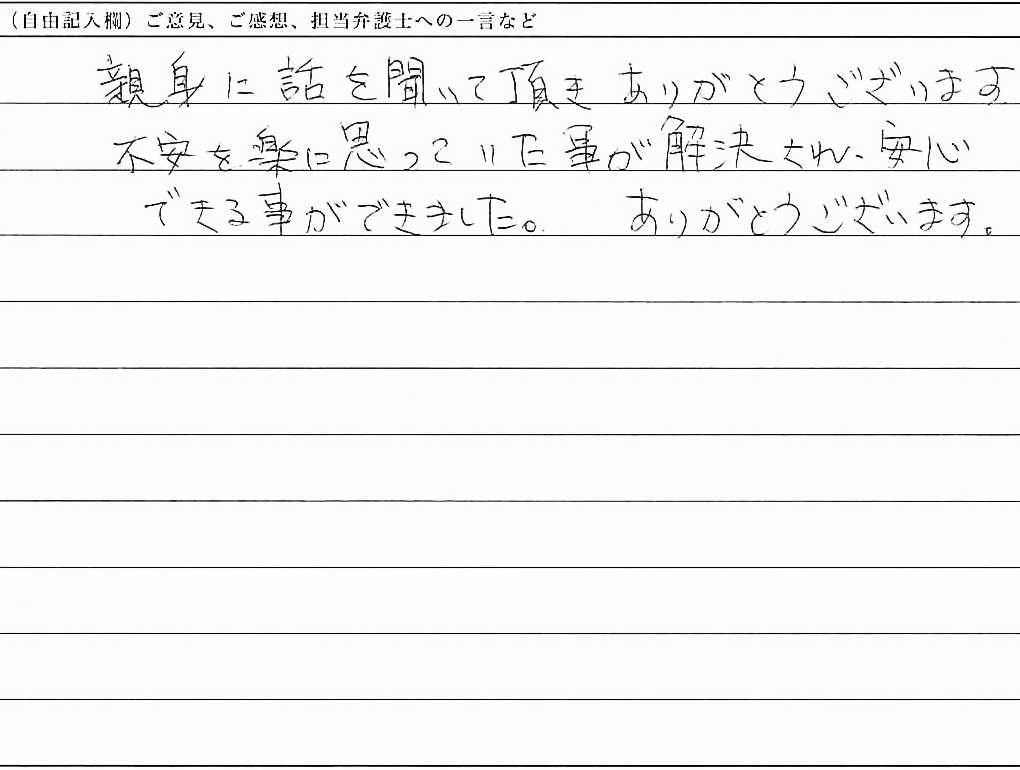
親身に話を聞いて頂き、ありがとうございます。不安を楽に思っていた事が解決され、安心できる事ができました。ありがとうございます。
ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。
在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。
刑事事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。
365日相談ご予約受付中
アトム法律事務所では現在、24時間365日、弁護士相談のご予約受付中です。
お急ぎの方は、お早目にご連絡いただき、ご都合のよろしい相談予約枠をおとりください。
ご連絡お待ちしています。



