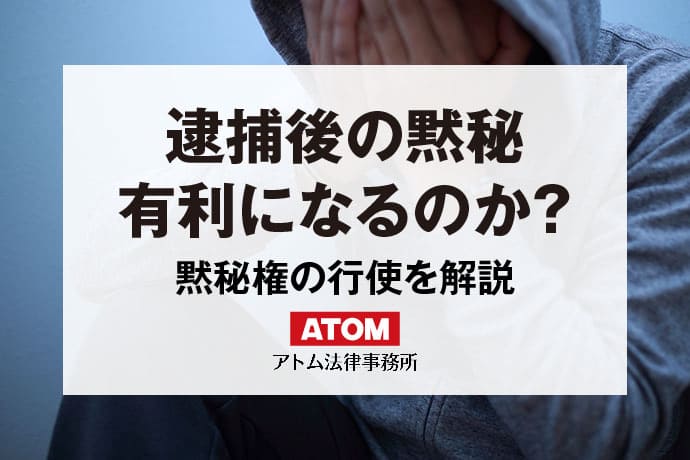
被疑者や被告人には、「黙秘権」という最大の武器があることをご存知ですか。黙秘権と聞くと「言いたくないことを言わなくていい権利」だと思いますよね。でも実は黙秘権はもっと強力な権利といえます。「何も言わずに最初から最後までずっと黙っていていい権利」なんです。
この記事では、黙秘権とはどのような権利なのか詳しくご説明します。そして、逮捕後に黙秘権を行使して有利になる場合と不利になる場合についても解説。実際にどのように黙秘権を行使すればいいのかもお伝えします。
この記事を読めば、自分の利益を守るにはどうすればよいか具体的に分かりますよ。早速見ていきましょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
黙秘権ってどんな権利なの?
刑事事件を起こしたのではないかと容疑をかけられた人を被疑者といいます。また、起訴された人を被告人といいます。黙秘権は、被疑者と被告人の利益を守るために保障されているのです。
ここでは、黙秘権の内容と目的、行使した場合の効果について解説します。
黙秘権の内容
刑事訴訟法は、被疑者について「自己の意思に反して供述する必要がない」ことを取調べの際、あらかじめ伝えなければならないと規定しています(刑事訴訟法198条2項)。
また、被告人について「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」権利を保障しています(刑事訴訟法311条1項)。
被疑者・被告人に認められたこのような全面的供述拒否権を黙秘権といいます。黙秘権は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という憲法38条1項の保障を拡張したものです。
黙秘権の目的
黙秘することを卑怯だと感じる方もいるかもしれません。でも、卑怯だと感じる必要は全くありません。なぜなら、黙秘権は「冤罪(えんざい)」を防ぐために生み出された人類の知恵であり、被疑者・被告人の正当な権利だからです。
想像してみてください。密室の取調室で取調官と一人で向き合わなければならないプレッシャーを。現在の日本では、取り調べへの弁護士の同席が認められていないため、被疑者が受けるプレッシャーは相当なものです。
このような場面で、もし何もかも話さなければならないという立場に置かれたら、果たして何人の人が自分の正当な主張を貫き通せるでしょうか。おそらく多くの人は、「早くこの状況から解放されたい」と願うことでしょう。そうなると、取調官の描いたストーリーのまま罪を認めることになりかねません。
黙秘権は、このような最悪の事態を防ぐために生み出された非常に重要な権利なのです。
黙秘権を行使した場合の効果
黙秘権を行使した場合、次のような効果が生じます。
- 強要により得られた不利益な供述は、有罪判決の証拠として用いることはできません。
- 黙秘したという事実から、不利益な推認をしてはいけません。
具体的には、以下のような効果が生じます。
勾留について
裁判官が、勾留の要件を判断する際、被疑者が黙秘しているからといって「証拠を隠しそうだ」「被害者を脅しそうだ」「逃亡しそうだ」と不利な推認することは許されません。
ただし、黙秘することで被疑者に有利な事情が裁判官に伝わらないことがあります。これに対し、正直に供述した場合は罪証隠滅や逃亡のおそれがないと判断され釈放されることはあり得ます。つまり、黙秘すると事実上不利になる可能性があることは否定できません。
保釈について
起訴後に被告人を釈放する制度を保釈といいます。保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の3種類があります。実務上多いのは①権利保釈と②裁量保釈です。
①権利保釈は除外事由に該当しない限り、原則として保釈を許可するというものです。実務上、保釈を却下する理由で最も多いのが、権利保釈の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」という除外事由に該当する場合です。
被告人が黙秘している場合、その事実から罪証隠滅の相当な理由があると推認することは許されません。
②裁量保釈は、裁判所が、刑事訴訟法90条記載の事情を考慮して適当と認めるときに職権によって許可するものです。考慮事情の一つに、被告人が「逃亡し又は罪証を隠滅するおそれ」があります。
被告人が黙秘している場合、その事実から、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると推認することは許されません。
ただ、勾留の判断と同様、黙秘することで被告人に有利な事情が裁判官に伝わらず、事実上不利になる可能性があることは否定できません。
犯罪事実の認定について
被告人が黙秘権を行使したことをもって、事実認定上、これを不利益に考慮することは許されません。
裁判例の中に、殺人事件の被告人が事実関係について一切黙秘し何の説明も弁明もしなかった事案で、被告人の黙秘の態度を不利益な事実の認定に用いることはできないと判示したものがあります(札幌高判平成14年3月19日判時1803号147頁)。この事案では、被告人が黙秘したことに加え、各情況証拠が殺意を認定するには不十分ないし不適当とされたことから、無罪が言い渡されました。
量刑について
被告人が黙秘権を行使したからといって、量刑上不利益に扱うことも許されません。
ただ、一貫して自白し反省の言葉を述べている場合、量刑上有利に考慮されるのが一般的です。黙秘した被告人が、このような場合に比べて結果的に不利になってしまうことは否定できません。
逮捕後、黙秘すると有利になる?不利になる?
黙秘権の行使が有利に働く場合もあれば不利に働く場合もあります。その両方について知っておくことが自分の身を守るために大切です。
黙秘権の行使が有利に働く場合
殺意や詐欺の故意など主観面に争いのある事件では、黙秘権を行使するメリットがあります。
人の心の中は外からは見えません。ですから、自白が重要な証拠となります。捜査機関は、自白を得るために手を変え品を変え質問してくるでしょう。例えば、殺人事件ならば、「死んでしまえと思っていなくても死んでも構わないと思っていたんじゃないか?」という風に。このような質問に対しあいまいな発言をすると、後で命取りになるおそれがあります。このようなケースでは、完全黙秘が一つの有効な手段となるでしょう。
また、客観的な証拠が少ない事件も黙秘権を行使するメリットは大きいです。このようなケースでは、被疑者の供述がなければ嫌疑不十分で不起訴となる可能性が高いです。
黙秘権の行使が不利に働く場合
被疑者が犯人であることが証拠上明らかな場合、黙秘することがかえって不利になることもあります。このようなケースでは、黙秘することで身体拘束が長期化してしまうおそれがあります。黙秘を選択しなくても、示談などによって不起訴を期待できるケースも多いので、弁護士とよく相談することをおすすめします。
また、量刑判断において、黙秘したことで反省していないと捉えられ不利な処分につながってしまう可能性もあります。
個々の事案によりますが、犯罪事実に争いがなく、早期釈放や起訴猶予を目指す場合は、素直に供述した方が利益になるケースも多いです。
黙秘するかどうか弁護士とよく相談しよう
黙秘権を行使するかどうか迷ったら、刑事弁護の経験方法な弁護士にぜひ相談しましょう。弁護士は、黙秘権を行使した場合のメリットとデメリットを本人が納得するまで何度でも説明します。また、法律のプロとして最適と考える弁護方針をお伝えします。黙秘権を行使する弁護方針が固まったら、頻繁に接見を行い、被疑者・被告人を全力でサポートします。
逮捕後、黙秘権はどのように行使したらいいの?
黙秘しようと思っても、実際どうすればよいのか不安ですよね。ここでは、黙秘権の行使の仕方や精神的に辛くなったときの対処法についてお伝えします。
さらに、黙秘権が侵害されている場合にとりうる対策についても解説します。
黙秘権の行使は何も言わなくてOK
黙秘権はどの時点でも行使できます。取調官が黙秘権を告知する前であっても構いません。
行使の際、何も言う必要はありません。もちろん、黙秘の理由も伝えなくて大丈夫です。何も言わないのが不安な方は「弁護士に相談します」と言ってあとは黙っていましょう。
やってはならないのが、「これは話しても大丈夫だろう」と自分で判断して供述してしまうことです。このような場合、後々不利な結果になるおそれがあります。完全黙秘にするか一部黙秘にするかは、必ず弁護士と相談の上決めましょう。
黙秘が辛くなったときの対処法を教えて!
被疑者が黙秘権を行使すると、取調べが厳しくなることが予想されます。もちろん、警察官や検察官は黙秘権について理解しているので、拷問のようにあからさまに責め立てることはないでしょう。
しかし、例えば「黙秘するなんて卑怯だと思わないか」というように精神的に追いつめてくることは十分あり得ます。
また、取調官の中には、弁護士の悪口を言って信頼をなくそうとする人もいます。雑談をもちかけて警戒心をやわらげた後で、それとなく自白に誘導し自白調書をとろうとすることもあるのです。
このような取調べを連日受けていると、黙秘を続けることが辛くなってしまうことがあると思います。そんなときこそ弁護士を頼ってください。弁護士は、できる限り頻繁に接見に行きしっかりサポートします。
どうしても黙秘が難しい場合、次のような対処法もあります。
対処法①署名押印を拒否しよう
一つ目の対処法として、供述調書への署名押印を拒否するという方法があります。供述調書は、取調べで話した内容が記載された書面です。供述者がこの書面に署名押印することで、裁判の証拠として扱うことが可能になります。しかし、署名押印がなければ調書はただの紙切れ。証拠として用いることはできません。
捜査機関が客観的な証拠を十分に集められず、署名押印のある供述調書もない場合、不起訴となる確率が高くなります。
「供述調書がないと自分の言い分を裁判官や裁判員に分かってもらえないのでは」と心配になる方もいると思います。大丈夫です。あなたの言いたいことは、法廷でしっかりと伝えればいいんです。書面よりも実際に話す態度を見た方が、裁判官や裁判員にあなたの言い分を理解してもらいやすいでしょう。
対処法②陳述書を作成しよう
二つ目の対処法として、陳述書を作成する方法があります。陳述書は、黙秘も署名押印拒否も難しく、被疑者に不利な内容の供述調書が作成されてしまった場合に有効です。陳述書は、被疑者が本当に言いたい内容を弁護士が聴き取り書面にしたものです。陳述書を作ったら被疑者の署名押印をもらい、公証役場等で確定日付をもらいます。こうすれば、陳述書を裁判の証拠として提出することが可能になります。
黙秘権行使が阻害されたときの対処法
黙秘権の行使が阻害されるような違法・不当な取調べが行われたときは、すぐに弁護士に教えてください。弁護士は、適切な対処を行い被疑者の利益を守ります。
具体的には、担当警察官、警察署長、担当検察官、検察庁などにすぐに抗議します。また、準抗告の申立てなど裁判所に対する手続きをとることもあります。



