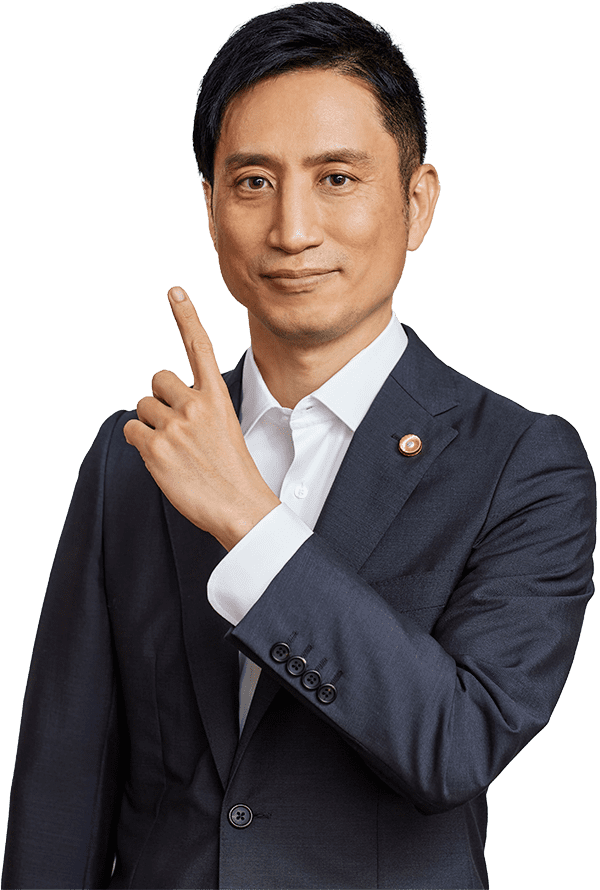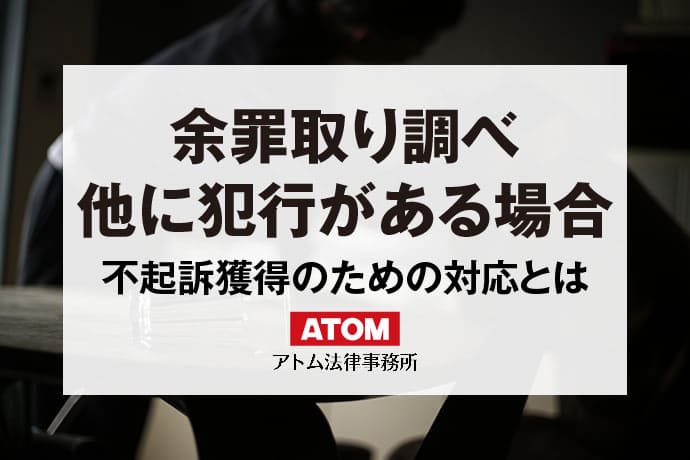
万引きや盗撮の事案では「実は他にも犯行を繰り返している」というケースが少なくありません。このような場合、「もし逮捕されたら、他の犯罪についても取り調べられるんだろうか」と不安ですよね。
逮捕勾留された犯罪事実以外の罪に関する取り調べを「余罪取り調べ」といいます。
この記事では、余罪取り調べについて不安な方のために適切な対処法について詳しくご説明します。
余罪がある場合の適切な対応方法を知れば、不起訴や刑の減軽につながりますよ。ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
余罪取り調べとは?
取り調べでは余罪のことも聞かれる?受忍義務はある?
実務上、取り調べで余罪について聞かれることはよくあります。
では、余罪取り調べは退去できるのでしょうか?これは「取り調べ受忍義務」の問題と呼ばれています。
ここでは、①逮捕勾留中の被疑者に取り調べ受忍義務があるか、②余罪取り調べにも受忍義務があるかという問題に分けて解説します。
逮捕勾留中の被疑者に取り調べ受忍義務はあるか?
学説上は肯定説・否定説があります。もっとも、捜査実務では、逮捕勾留されている被疑者について、取り調べ受忍義務があるという前提で運用されています。
簡単に言うと、身体拘束されている被疑者は、出頭を拒否したり、取調室から退去する自由が認められないということです。
この考え方の根拠は、刑事訴訟法の規定の仕方にあります。刑訴法198条1項但書は「逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定されています。
これを反対に解釈すると、逮捕勾留されている場合は、出頭を拒んだり、出頭後自由に退去することはできない、という結論になります。
余罪取り調べにも受忍義務がある?
取り調べ受忍義務を肯定する見解の中でも、余罪取り調べに関しては考え方が分かれています。様々な学説や裁判例があり、どれが正解というものはありません。ここではそれぞれの学説の内容を簡単に解説します。
①逮捕勾留された被疑事実に限定して受忍義務を認める立場(限定説)
この見解は、余罪取り調べに受忍義務はないと考えます。したがって、余罪取り調べは自由に退出できることになります。
②逮捕勾留された被疑事実以外(余罪)についても受忍義務を認める立場(非限定説)
この見解は、余罪取り調べにも受忍義務はあると考えます。したがって、余罪取り調べは自由に退出できないことになります。
③折衷的な立場
この見解は、余罪取り調べが具体的状況下において、実質的に令状主義を潜脱するといえるかどうか検討し、潜脱する場合はその取り調べは違法になると考えます。
折衷説は、以下の場合は余罪取り調べが許されると考えます。
・余罪が逮捕勾留された被疑事実と同種または密接に関連する場合
例)窃盗容疑で逮捕勾留されている被疑者を、同じ手口の別件の窃盗容疑で取り調べる場合
・被疑者が自ら進んで余罪を自白した場合
・余罪が、逮捕勾留された事実より相当軽微な場合
ポイント
余罪取り調べと受忍義務について様々な考え方があるので「実際の取り調べではどうすればいいの?」と不安になりますよね。
大切なのは「取り調べで余罪について聞かれたら、まず弁護士に相談する」ということです。弁護士は法律知識と豊富な弁護経験を生かし、ご本人の利益が最大限守られるよう活動します。
在宅事件でも余罪の取り調べはある?
在宅事件とは逮捕状による逮捕はされず、被疑者在宅のまま捜査が進められる事件のことです。
在宅事件の対象となる犯罪は明確に決まっているわけではありません。盗撮など比較的軽微な事件は在宅事件となる可能性があります。
在宅事件の場合、取り調べのために警察署等へ任意出頭を求められます。取り調べでは、逮捕された場合と同様、余罪について聞かれる可能性があります。
たとえ在宅事件でも、余罪多数の場合は逮捕につながるおそれがあります。在宅事件の場合も、早期に弁護士に依頼して余罪の対応について検討することが重要です。
(関連記事)
・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
起訴後も取り調べはあるの?
逮捕勾留後、検察官は起訴・不起訴の決定をします。では、起訴後も取り調べはあるのでしょうか?
起訴後の取り調べについて、①公訴事実(起訴された犯罪事実)に関係する取り調べと、②余罪の取り調べに分けて解説します。
公訴事実の取り調べ
起訴後に公訴事実について取り調べることは原則として許されません。例外的に、被告人が自ら供述する場合など必要最小限の範囲で許されると考えられています。
起訴後、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになります。被告人は裁判の当事者として、弁護人と入念な打ち合わせを行う必要があります。被告人の防御活動を妨げないため、起訴後の取り調べは原則禁止されているのです。
また、第1回の公判期日以降は、裁判所が被告人質問を通じて被告人の供述を直接聞くのが本来の刑事裁判の姿です。この点からも、起訴後の取り調べが原則として許されないと考えられています。
判例は、起訴後の取り調べによって作成された被告人の供述調書の証拠能力が問題になった事案で、「起訴後においても、捜査官はその公訴を維持するために必要な取調を行うことができる」としつつ、「起訴後においては被告人の当事者たる地位にかんがみ、捜査官が当該公訴事実について被告人を取り調べることはなるべく避けなければならない」と判示しています(最決昭和36年11月21日)。
なお、この事案で問題となった供述調書は起訴後第1回公判期日前の取り調べにおいて作成されたものであること、公判において、被告人と弁護人が証拠とすることに同意していることから、結果的に証拠能力は否定されないと判断されました。
余罪の取り調べ
起訴後であっても、余罪については刑訴法198条を根拠に適法に取り調べることができるとされています。
もっとも、起訴後は被告人として十分な防御活動を行う必要があります。この防御活動を妨げるような余罪取り調べは許されません。
起訴後の余罪取り調べで少しでも困ったことがあれば、すぐに弁護士に相談してください。
余罪が取り調べられるきっかけは?
実務上、余罪取り調べがされることはしばしばあります。特に、窃盗など犯行を繰り返す傾向が強い犯罪は、余罪取り調べがされることがされることが多いです。
余罪が発覚するきっかけは、以下のようなものがあります。
- 家宅捜索
- 防犯カメラ映像
- 被害届
- 自白
余罪は自白しないといけないの?
警察など捜査機関に余罪が発覚していない場合、自白しないといけないのでしょうか?
法律上、余罪について自白する義務はありません。
逮捕勾留されている事件について、被疑者は黙秘権を行使できます。そうである以上、逮捕勾留の理由となっていない余罪については、なおさら積極的に供述する義務はないのです。
黙秘権は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という憲法38条1項の保障を拡張したものです。冤罪を防ぐため被疑者・被告人に認められた正当な権利、それが黙秘権です。黙っていることを引け目に感じる必要はありません。
ただ、余罪について自白しないことが常にプラスに働くとは限りません。というのも、たとえ自白がなくても、防犯カメラなどの証拠で起訴されてしまうこともあるからです。
この場合、余罪について正直に自白しなかった態度から反省していないととらえられ、事実上量刑が重くなる可能性があります。
余罪の自白はとても難しい問題なので、ご本人が自分で対応を決めるのは避けるべきです。取り調べで余罪について聞かれたら即答するのはやめましょう。
余罪を自白するかどうかは、弁護士に相談してメリット・デメリットを十分に検討した上で決めることをおすすめします。
(関連記事)
・黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?
余罪があると勾留期間はどうなる?
余罪があると必ず勾留される?
逮捕後、さらに身体拘束の必要がある場合は勾留されます(逮捕後の刑事手続きの流れについて詳しくは『警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?』を参考になさってください)。
では、余罪がある場合は必ず勾留されてしまうのでしょうか?
結論から言うと、余罪があることを理由に必ず勾留されるわけではありません。しかし、勾留される可能性は高くなる場合が多いでしょう。
勾留は被疑者の人権を侵害する重大な処分なので、要件が法律で厳しく規定されています。具体的には、①勾留の理由と②勾留の必要性が必要です。勾留の要件を判断するのは裁判官です。
勾留の要件
①勾留の理由(アとイいずれも必要)
ア 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
イ 次のうち少なくとも1つの事由があること
・ 被疑者が定まった住居を有しないこと
・ 罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があること
・ 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
②勾留の必要性
これらの勾留の要件は、勾留の基礎となる犯罪事実ごとに判断しなければなりません。これを「事件単位の原則」といいます。
勾留の基礎となる犯罪事実(以下「本件」といいます)について、勾留の要件がないのに、余罪に勾留の要件があるため本件について勾留することは、事件単位の原則に反し許されません。
他方、本件について勾留の要件を検討するための一資料として余罪を考慮することは、事件単位の原則に反せず、許されます。
具体例
例えば、共犯者と一緒に窃盗容疑で逮捕された被疑者に、同じ共犯者と行った多数の同種余罪がある場合を考えてみましょう。
裁判官は次のように考える可能性があります。
「もし被疑者を自由の身にすると、共犯者と口裏合わせをして証拠隠滅するおそれがあるな」
「余罪の被害品を処分して、常習的な犯行であることを隠すかもしれない」
「余罪がたくさんあるということは、その分量刑が重くなると予想されるから逃亡のおそれは高いな」
このように、余罪の存在は、本件に関する逃亡・罪証隠滅のおそれを高める事情になります。そのため、余罪があると勾留される可能性が高くなる場合が多いでしょう。
余罪があると必ず勾留延長される?
逮捕後に勾留される場合、勾留期間は原則10日間です。もっとも、「やむを得ない事由」がある場合、勾留期間がさらに最長10日間延長される可能性があります(刑訴法208条2項)。
では、余罪があると必ず勾留延長されてしまうのでしょうか?
余罪があるからといって必ず勾留延長されるわけではありません。
しかし、実務上、余罪捜査が勾留事実の起訴・不起訴の判断に影響するときは、余罪捜査が終わっていないことを理由に勾留延長することが許されるとされています。
具体的には以下のとおりです。
勾留延長が許される場合
犯行態様や被害額等の点で、勾留事実だけでは起訴するに値しない軽微な事件だが、同種余罪を併せると起訴するに値するような場合
例)勾留事実は被害額が軽微な万引き1件だが、同種余罪が多数あり被害額を合計すると多額になる場合
勾留延長が許されない場合
・余罪があったとしても、それと併せて起訴することが到底考えられないような軽微なものである場合
例)勾留事実は軽犯罪法1件、余罪も軽犯罪法1件の場合
・余罪の刑事事件が複雑・重大である場合(最初から余罪について逮捕勾留すべき)
例)勾留事実は窃盗だが、殺人の余罪がある場合
余罪がある場合の量刑はどうなる?
余罪を理由に刑罰が重くなる?
余罪を処罰する目的で量刑を重くすることはできません。
刑事裁判は、起訴された犯罪事実の責任を問うものだからです。余罪は起訴されていない以上、その責任を直接負わせることはできないのです。
もっとも、量刑を決める一資料として余罪を考慮することは許されます。
量刑を決める際、犯情(犯行の動機、態様、結果等)や一般情状(被告人の性格等)も考慮する必要があり、余罪はこれらを推測する資料になるからです。
例えば、余罪が多数ある場合は常習性が高いと推測されます。したがって、犯罪を繰り返さないようにするため量刑が重くなることが考えられます。
余罪を自白した場合、量刑はどうなる?
では、余罪を自白すると量刑は重くなってしまうのでしょうか?
事案によるので一概には言えませんが、通常、「余罪を自白したこと」=「反省している」と判断される傾向があります。
余罪の自白に加え、示談や被害弁償の実施、家族による監督の誓約、初犯である等の事情が重なれば、罰金刑や執行猶予付き判決になる可能性が高くなるでしょう。
また、捜査機関に発覚していない余罪を犯人が自発的に述べた場合、自首が成立する可能性があります。自首が成立すると、刑法42条1項が適用され裁判官の裁量により刑が減軽されます。
余罪取り調べが不安なら弁護士に相談!
余罪について適切な対応を知らないまま刑事手続きが進むと、思いもよらない不利益を受けるおそれがあります。
そうならないために、早期に弁護士に相談することが重要です。余罪がある場合でも適切な弁護活動によって不起訴や刑の減軽が期待できます。
今後とるべき適切な対応がわかる
余罪がある場合、自白した方がよいか、示談はどう進めるべきかなど、考えなければならない問題がたくさんあります。
こうした問題に適切に対応するには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、接見で捜査状況を聴き取ったり、捜査機関に確認するなどして事件の見通しを立てます。
その見通しをもとに、ご本人の利益が最大限守られるよう弁護方針を立てます。そして、ご本人に対して今後とるべき適切な対応をわかりやすくご説明します。
不当な余罪取り調べや身体拘束からの解放が期待できる
余罪取り調べは無制限に許されるものではなく、事案ごとに限界があります。
余罪について取り調べで聞かれたら、まずは弁護士にご相談ください。
もし余罪について強制的に供述させられるなど不当な取り調べが行われた場合、弁護士が捜査機関に対しすぐに抗議します。
また、余罪を理由に勾留や勾留延長された場合、弁護士に相談すれば釈放される可能性があります。
弁護士は、準抗告を申立て不当な身体拘束から一日でも早く解放されるよう最善を尽くします。
示談によって不起訴や刑の減軽が期待できる
余罪を含めた示談をすることで、不起訴処分や刑が減軽される可能性が高まります。
余罪が多数ある場合の示談は、優先順位や示談金の割り当て方など特に慎重な配慮が必要です。全額弁償できない可能性もあるので、被害者に対するより一層丁寧な説明が求められます。
弁護士は、余罪が多数の案件でも、事案に応じてご本人に最も有利になるような示談交渉を行います。