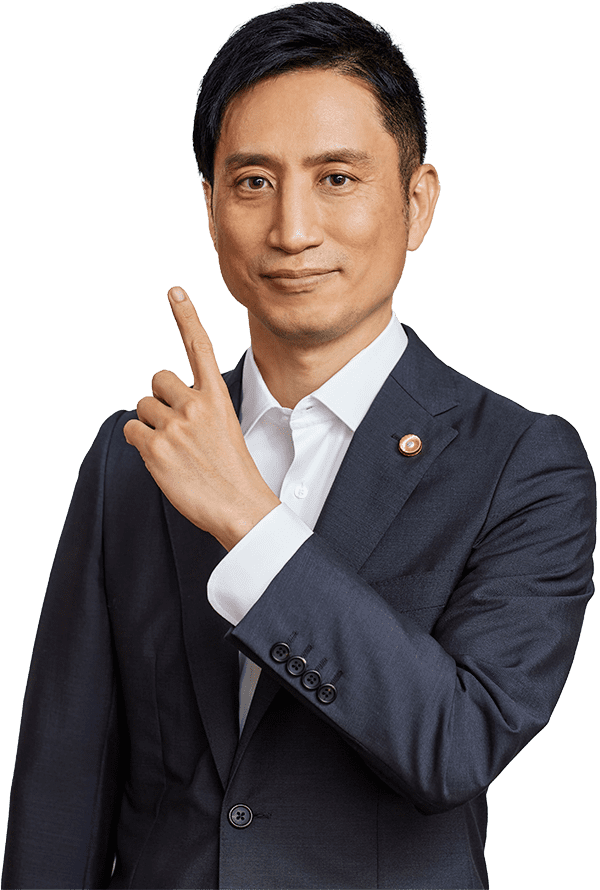2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
暴行を行ってしまったとしても、すぐに逮捕されるとは限りません。暴行事件からしばらく経っても警察の捜査が始まらない場合には、暴行罪の時効が気になるかもしれません。
暴行を行った場合に問題となる時効は刑事の時効だけではありません。
この記事では、暴行罪とはどのような罪なのか、暴行の時効の種類や時効成立の効果、暴行の時効期間などについて、解説を加えます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
暴行罪とは
暴行罪が成立する行為
暴行罪における暴行とは、人の身体に対して違法に何らかの物理的な力を加える行為のことを言います。他人を殴ったり蹴ったり物で叩いたりする行為が典型的な暴行です。この他にも、人に物を投げつけたが当たらなかった場合なども暴行に該当することがあります。
暴行の結果として他人にけがを負わせれば、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。裏を返せば、暴行罪が成立する場合とは、人を殴ったり蹴ったりしたもののけがを負わせるには至らなかった場合と言うこともできます。
暴行罪の法定刑
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです(刑法208条)。拘留とは30日未満の間自由を奪われる刑です。科料は1万円未満の金銭を支払を命じられる刑です。拘留や科料はいずれも犯罪の内容が軽いものであった場合に科せられる刑です。
同じ暴行罪でも、物を投げつけたが当たらなかった場合のように軽いものから殴った結果けがを負わせる一歩手前だった場合のように重いものまで、暴行にはさまざまな内容のものがあります。暴行には軽いものから重いものまでさまざまなものがあることから、法定刑の幅も広く設定されています。
暴行の結果けがを負わせてしまった場合に成立する傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています(刑法204条)。傷害罪は他人にけがを負わせてしまうという点で暴行罪よりも結果が重大であるために、暴行罪よりも重い法定刑が設定されているのです。
暴行によって民事上の責任を負うことも
暴行を働いてしまった場合には、暴行罪が成立して刑事上の責任を負わなければならないだけではありません。それとは別に民事上の責任を負うこともあります。
刑事上の責任とは、犯罪を行ったことに対して刑罰を科せられる責任のことを言います。これに対して、民事上の責任とは、違法な行為をしたことについて被害者に損害賠償金を支払わなければならない義務のことを言います。民事上の責任と刑事上の責任とは全く別の概念であるため、たとえ暴行罪で罰金を支払って刑事責任を果たしたとしても、民事責任である損害賠償金は別途支払わなければなりません。
暴行を働いた場合には、暴行によって被害者に精神的・身体的に苦痛を与えてしまっています。そのような苦痛に対して、民事上の責任としての損害賠償金を支払わなければならない場合があるのです。
暴行の時効とは|種類と効果を解説
時効の種類|刑事の時効と民事の時効
暴行の時効には、刑事の時効と民事の時効の2種類があります。刑事の時効は公訴時効とも言います。民事の時効は消滅時効とも言います。刑事の時効は刑事責任に、民事の時効は民事責任に関わるものです。いずれも時効が成立すれば刑事・民事の責任が消滅するという点では共通しますが、それぞれ時効の期間や効果が異なります。
時効の効果①|刑事の時効
刑事の時効(公訴時効)の期間が経過した場合、時効の効果として、問題となっている犯罪について公訴の提起(起訴)をすることができなくなります。暴行について公訴時効が成立すれば、もはや起訴されることがないため、捜査機関により逮捕されたり捜査をされたりすることもありません。また、起訴されない以上、前科がつくということもありません。
時効の効果②|民事の時効
民事の時効(消滅時効)の期間が経過した場合には、時効の効果として、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払う義務が消滅します。消滅時効の期間が経過した後であれば、被害者が損害賠償金を請求しても、裁判所は消滅時効の成立を理由として請求を認めません。このため、被害者から損害賠償金を請求されるということはありません。
暴行罪の時効は何年か
暴行罪の時効年数①|刑事の時効
刑事の時効年数は、各犯罪の法定刑の重さに応じて定められています。暴行の場合、刑事の時効年数は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。暴行を行ってから3年が経過すれば刑事上の責任は消滅します。
例えば、令和3年4月1日午後5時に暴行事件が発生した場合には、令和6年3月31日の24時に刑事の時効が成立します。この日を過ぎれば、暴行事件についての刑事上の責任は消滅し、逮捕や起訴をされたり有罪判決を下されることがなくなります。
暴行罪の時効年数②|民事の時効
民事の時効年数は、請求権の内容に応じて定められています。暴行の場合、民事の時効年数は、被害者が暴行による損害と加害者の両方を知った時から5年です(民法724条の2)。被害者が暴行による損害と加害者のいずれかを知らないまま20年が経過した時にも時効が成立します(民法724条2号)。
例えば、令和3年4月1日午後5時に暴行事件が発生した場合には、令和8年3月31日の24時に民事の時効が成立します。また、被害者が加害者を知らないままであれば、令和23年3月31日の24時に民事の時効が成立します。これらの日を過ぎれば、暴行についての民事上の責任は消滅し、加害者が被害者に対して暴行事件についての損害賠償金を支払う義務がなくなります。
公訴時効の停止と消滅時効の更新
刑事の時効(公訴時効)は、起訴された時に停止します。逮捕されただけでは時効は停止しません。また、犯人が国外逃亡や海外旅行によって国外にいる場合などにも公訴時効は停止します。一度停止した公訴時効はリセットされるのではなく停止の原因が消滅した時にあらためて続きから進行を開始することになります。
例えば、暴行事件を起こした直後に長期間海外に滞在していた場合には、海外に滞在している間は公訴時効の進行が停止し、帰国した時にあらためて公訴時効の進行が開始します。長期間の海外滞在などがあれば、暴行事件を起こした日から3年が経過しても時効がまだ成立していないということが起こり得るのです。
刑事の時効については海外旅行などによって時効が停止するということがありますが、民事の時効については海外旅行などによっても時効が停止しません。その代わり、損害賠償請求権について一部でも支払いをすることなどによって消滅時効が更新されてリセットされその時から新たに時効の進行が開始します。刑事の時効と民事の時効との間では、時効がリセットされるのか停止するだけなのかという違いやその原因にも違いがあるため、それぞれ分けて考える必要があります。
何もしないで時効成立を待つべきか
暴行罪を犯してしまったがまだ逮捕されていないという場合、前科がつかないようにするためには時効の成立を待つべきなのではないかと考えるかもしれません。
しかし、実際のところは、時効の成立を待つという方法はあまり適切ではありません。なぜなら、捜査機関は多くの場合、公訴時効を成立させないように公訴時効期間が経過するよりも前に捜査を遂げて起訴しようとするからです。捜査機関としても犯罪が行われたのに安易に処罰をしないで見逃すことはできません。そのため、簡単には公訴時効が成立することはないのです。
時効成立を待つ以外にできること
前科がつかないようにするためには、時効成立を待つことだけが取り得る手段ではありません。それ以外にもいくつかの方法があります。
例えば、被害者との間で示談を成立させるという方法があります。示談を成立させて被害者が加害者を許して処罰を求めないという内容の示談書を作成することができれば、不起訴とされて前科を回避できる可能性が高くなります。
示談金の支払いをすることができれば、示談金は損害賠償金を兼ねられるので、示談金とは別に損害賠償金を支払わなくても済むようにすることもできます。暴行罪における示談金の相場については『暴行罪の加害者になった場合の慰謝料・示談金の相場。金額はどう決まる?』の記事をご確認ください。
また、捜査機関に自首をして罪を認めて犯行について正直に自白し、取調べなどの捜査に積極的に協力すれば、逮捕されずに済む可能性が高くなります。
刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、逮捕や前科を回避するためにどのような手段を取るのが適切かをその時々の状況に応じて提案してくれます。示談については代理して行ってくれたり、自首については同行してくれたりといった活動もしてくれます。何もしないで時効成立を待つよりは、まず刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼をして、前科を回避するための活動をしてもらうのが良いでしょう。
関連記事