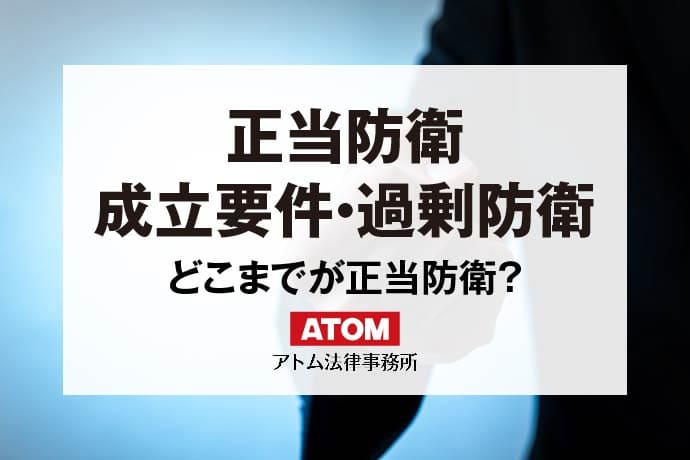
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分や第三者の生命・身体・財産などを守るために、やむを得ずにおこなう防衛行為のことです(刑法36条)。人に怪我をさせたりしても、正当防衛が成立すれば、処罰されません。
ただし、どこまでが正当防衛になるのかについて知っている方は少ないかもしれません。
正当防衛が成立するためには(1)急迫性があること(2)不正の侵害にあたること(3)防衛の意思を持って行われていること(4)やむを得ずにした行為であることの4つの要件を満たす必要があります。
正当防衛の程度を超えたものは過剰防衛となり、暴行罪・傷害罪として刑が科される可能性もあります。正当防衛のつもりでも法律上の要件を満たしておらず、犯罪として処罰されてしまうケースもあるのです。
この記事では正当防衛について疑問や不安をお持ちの方に向けて、正当防衛が成立するための要件、過剰防衛との違いなどについて詳しく解説しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
正当防衛とは?正当防衛が成立するための要件
正当防衛の意味
正当防衛とは、「自分や他人の身体・生命を危険から守るため、やむを得ずに行った行為」のことです。
正当防衛の範囲の中で行われた行為は、たとえそれが犯罪に該当するような行為であったとしても罰せられることはありません。
たとえば、「通りがかりにナイフで襲われた」といった緊急の状況のとき、加害者に対してやむを得ずした反撃を正当防衛といいます。
つまり、ナイフで襲ってきた相手に対して、殴る蹴るなどの反撃をして相手にケガを負わせたとしても、それが正当防衛の範囲内の行為であるなら、傷害罪として罰せられることはないわけです。
正当防衛は刑法36条に規定されている概念で、一般用語ではなく条文や判例によってかなり厳格に規定された法律用語となります。
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法36条1項(正当防衛)
なぜ正当防衛は処罰されないのか
法治国家では、違法行為への対処は本来、警察や裁判所など国家機関の役割です。しかし、緊急事態においては国家機関の助けを待つ余裕がありません。
そこで刑法は、「正は不正に譲歩する必要はない」という考え方に基づき、急迫不正の侵害に対する私人の防衛行為を例外的に許容しています。これが正当防衛制度の根拠です。
刑事上の正当防衛と民事上の正当防衛
正当防衛には刑事上の正当防衛と民事上の正当防衛の2種類があります。
刑事と民事における正当防衛の違い
民法720条1項は「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない」と定めています。
正当防衛の成立要件
正当防衛が認められるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
正当防衛の成立要件
- 急迫性があること
先制攻撃をすると正当防衛として認められない - 不正の侵害にあたること
相手が積極的に違法行為をしているわけではない場合は正当防衛として認められない - 防衛の意思を持って行われていること
防衛に名を借りて積極的に攻撃しに行くのは正当防衛として認められない - やむを得ずにした行為であること
必要性や相当性のない反撃をしたら正当防衛として認められない
それぞれどのような要件なのか、ひとつずつみていきましょう。
要件(1)急迫性があること
正当防衛が認められる一つ目の要件は、「相手の行為に急迫性があること」です。
たとえば、「相手が拳を振り上げて殴りかかってきそうな状況にある」とか「今まさに殴られている最中である」など、侵害が目前に差し迫っているか現在進行形であるときにこの要件が満たされます。
すでに終了している出来事やこれから発生する可能性のある出来事に対しては、急迫性が認められません。
そのため、先制攻撃をしてしまったような場合、正当防衛は認められないので注意してください。
たとえば、「怨恨のある相手が報復目的でナイフを持ってこちらを探していた」というような状況に鉢合わせたとき、「安全を確保するため先に倒そう」と考えて物陰から襲い掛かるのは正当防衛として認められません。
「相手がナイフを振り上げて迫ってきた」、「相手がナイフを振り上げて脅迫的な言動をしてきた」というような段階であれば急迫性が認められるでしょう。
要件(2)不正の侵害にあたること
正当防衛が認められる二つ目の要件は、「相手の行為が不正の侵害にあたること」です。 不正の侵害というのは、いわゆる違法行為のことで、相手が違法行為をしてきた場合のみに正当防衛は成立します。
暴行・傷害はもちろんのこと、痴漢行為などのわいせつ目的の行為、「赤の他人が自分の家に侵入してきて退去の勧告にも応じない(住居侵入・不退去)」、「置いていた財布を盗まれ逃亡されつつある(窃盗)」といった状況も不正の侵害として認められ得ます。
一方で「貸したお金を返してくれない」といった、相手が積極的に侵害行為に及んでおらず、かつ、あくまで民事上の侵害行為に過ぎないような場合については、不正の侵害には該当しません。
相手がお金を返してくれないからといって、無理やり押さえつけて財布から借りた分のお金を奪い取るなどしてしまうと、正当防衛が認められずに犯罪になってしまう可能性が高いわけです。
要件(3)防衛の意思を持って行われていること
正当防衛が認められる三つ目の要件は、「自分の反撃が防衛の意思を持って行われていること」です。
たとえば、「住宅に侵入してきた泥棒がお金を持って逃げようとしたので、取り押さえる目的で暴行した」ような場合、侵害を排除して権利を防衛したいという意思のもとに行われた行為として正当防衛が成立します。
一方、「防衛に名を借りて積極的に攻撃を加える行為」については防衛の意思を欠いたものとして正当防衛が認められません。
たとえば、「前から因縁のある相手なので、この機会に乗じて傷害を加えよう」と思っていたり、「危ない思いをして不快になったので、この機会に乗じて憂さ晴らし的に暴行を加えよう」と思っていたりした上での行為は、正当防衛として認められないわけです。
防衛の意思についての補足
たとえば、相手方からいきなり殴りかかってこられたようなとき、人間の生理的な反応として怒りを感じるのは当然のことでしょう。
そのため、正当防衛は反射的、本能的に行われるものであり、明確な意図までは不要であるとされています。怒りで逆上したために反撃行為したとしても、反射的な怒りだけで防衛の意思は否定されないのです。
判例上も、「怒りを感じていたから」「逆上していたから」といった理由で、直ちに正当防衛が認められないことはないとしています。
正当防衛は「攻撃の意思と防衛の意思が併存している場合は認められる」「もっぱら攻撃の意思のみで反撃している場合には認められない」というのが、判例上の通説です。
怒りを感じて「積極的に攻撃しよう」という意思が多少芽生えていたのだとしても、あくまで防衛の意思がメインである場合には正当防衛として認められるでしょう。
要件(4)やむを得ずにした行為であること
正当防衛が認められる四つ目の要件は、「その反撃行為がやむを得ずにした行為であること」です。防衛の必要性があり、防衛行為が社会通念上相当であるような場合に正当防衛として認められます。
どこまで正当防衛として認められるには、その行為をする必要性と相当性が求められるわけです。
具体的には、以下の4つの判断基準をフローチャート形式で進め、どこまで正当防衛に含まれるか検討する方法が提唱されています。
判断基準①その反撃が防御的なものか攻撃的なものか
反撃の内容があくまで被害の発生を防止するためだけの、防御的な行為である場合には原則的にやむを得ずにした行為であると認められます。
たとえば、「殴りかかってきた相手の拳をガードした、掴んだ」とか「鞄を盗まれそうになったので鞄の紐を引っ張って抵抗した」などの行為は防御的な行為なので、基本的にやむを得ずした行為だと認められます。
一方で、積極的に相手に反撃をしにいっているような攻撃的な行為については、さらに次の判断基準に進んで検討します。
判断基準②その攻撃的な反撃は、他に取り得る防衛手段がない状況で行われた行為か
その反撃が他に手段がないような状況において行われた行為である場合には、原則的にやむを得ずした行為であると認められます。
一方で、状況を検討した際に、もっと他に取り得る手段が見つかったような場合にはさらに次の判断基準に進んで検討します。
判断基準③他に取り得る防衛手段の危険性は、実際に行った反撃と比較して危険性が大きいか
他の手段を検討したときに、実際に行った反撃よりも他の手段の方が危険性が大きかったり、危険性が同等であるような場合には、実際に行った反撃についてやむを得ずした行為であると認められます。
一方で、もっと危険性の少ない他の手段が見つかったような場合には、さらに次の判断基準に進んで検討します。
判断基準④その危険性の少ない他の防衛手段を選ばなかったことは、状況的に不当といえるか
危険性の少ない他の手段について、それを採用することの困難さ、相手方の侵害行為の性質や程度、急迫性の程度などを総合的に検討します。
その結果、「他の手段を選ばなかったのも無理はない」「他の手段を選ばなかったことについて不当とはいえない」というようなときには、やむを得ずした行為であると認められます。
一方で色々な事情を検討しても「もっと危険性の少ない他の手段を選ぶことができた」「他の手段を選ばなかったのは不当といえる」ようなときには、やむを得ずした行為であるとは認められません。
どこまで正当防衛を判断するのは検察官・裁判官
実務上、正当防衛が成立するかどうかを判断するのは、検察官や裁判官です。
いくら「防衛の意思のもとでやった」、「やむを得なかった」などと主張したとしても、検察官や裁判官がそれを聞き入れてくれるかどうかはわかりません。
あくまで第三者が客観的に判断することなので、もし日常生活で正当防衛になるかどうか微妙な状況に出くわしたら、安直に予断を持って行動するのは避けるべきだといえるでしょう。
正当防衛を主張するために必要な証拠と行動
正当防衛を主張する場合、客観的な証拠と適切な初動対応が極めて重要です。
正当防衛の立証に有効な証拠
| 証拠の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 映像証拠 | 防犯カメラ映像、ドライブレコーダー、スマホ動画 |
| 人的証拠 | 目撃者の証言、同行者の証言 |
| 物的証拠 | 負傷部位の写真、破れた衣服、凶器 |
| 医療記録 | 診断書、カルテ |
特に映像(防犯カメラ等)や物的証拠(傷、着衣の破損)といった非供述証拠は、人の記憶に基づく供述証拠よりも一般に証明力が強いとされています。
特に防犯カメラ映像などは、事件当時の状況を客観的に確定するための出発点となります。
警察官に対する初動対応
正当防衛が問題となる事案では、警察への最初の説明が非常に重要です。
やるべきこと
- 落ち着いて事実を説明する
「相手から先に攻撃されたため、身を守るためにやむを得ず反撃しました」と明確に伝える - 被害状況を伝える
自分が受けた攻撃の内容、ケガの有無を説明する - 目撃者がいれば情報を確保する
氏名・連絡先を控えておく
避けるべきこと
- 感情的になって話す
冷静さを欠くと、攻撃意思があったと誤解される可能性がある - 曖昧な説明をする
「カッとなって」「つい」などの表現は不利に働く - 事実と異なることを言う
後で矛盾が発覚すると信用を失う
早期に弁護士に相談すべき理由
正当防衛が認められるかどうかは、具体的な事実関係と証拠に基づいて判断されます。
- 取調べでの供述内容が後の裁判に影響する
- 有利な証拠は時間が経つと散逸する
- 被害者との示談交渉が必要になる場合がある
逮捕された場合や、逮捕の可能性がある場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
正当防衛を超えた行為はどのように扱われる?
通常の犯罪と同じように処罰される
正当防衛が成立するための要件である「要件(1)急迫性があること」「要件(2)不正の侵害にあたること」「要件(3)防衛の意思を持って行われていること」のいずれかを満たさなかった場合、通常の犯罪と同じように処罰されることになります。これら3つのうち一つでも欠ければ、正当防衛は成立しません。
たとえば、「身の危険を感じ先制攻撃として殴る蹴るなどの暴行を加えた」というような場合、暴行罪や傷害罪として通常通りに処罰されます。
「相手が不正の侵害をしていないのに攻撃した」「防衛の意思なくもっぱら攻撃の意思のみで攻撃した」というような場合も、同じように暴行罪や傷害罪に問われることになり、通常通り処罰の対象となるのです。
関連記事
過剰防衛とみなされ処罰される
正当防衛が成立するための要件(1)~(3)は守っているものの、「要件(4)やむを得ずにした行為である」のみを満たさなかった場合、正当防衛は成立せず、過剰防衛として処罰されることになります。
過剰防衛と判断されれば処罰されることにはなりますが、刑の軽減や免除される可能性はあるでしょう。
たとえば、「相手が素手で殴りかかってきているのに、こちらはわざわざ刃物を取り出して抵抗した」というような状況は過剰防衛の典型例です。
正当防衛と過剰防衛・緊急避難の違い
正当防衛と過剰防衛の違い
正当防衛と過剰防衛の違いは、犯罪になるかどうかです。正当防衛は犯罪にはなりません。
一方、過剰防衛は犯罪になりますが、場合によっては処罰が軽くなったり、処罰されなかったりすることもあります。
過剰防衛について規定された条文を見てみましょう。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法36条2項
過剰防衛なら拘禁の長さが短くなったり、罰金の支払い額が少なくなったり、あるいはそもそもそういった刑が科されずに済んだりする可能性があるわけです。
正当防衛と緊急避難の違い
正当防衛は相手方からの違法行為に対して権利を守るためにする行為を指します。いわば「正」対「不正」の関係です。
一方で緊急避難は、誰かが違法行為を行っていたかどうかにかかわらず、権利の侵害を回避するため無関係の第三者の権利を侵害する行為を指します。いわば「正」対「正」の関係にあります。
たとえば、以下のような事例は緊急避難の典型例です。
- 津波が目前まで迫ってきていたので、やむを得ず駐輪されていた自転車を無断借用して避難した
- 洪水が目前まで迫ってきたので、仕方なくビルに不法侵入して上の階に避難した
- 駅から線路内に人が転落したので、自身も線路内に侵入して転落した人を助け出した
津波や洪水が迫ってきたのは自然現象であり、人が線路に転落したのもただの事故です。上記の例では誰かが違法行為をしたわけではないのに、自分や他人の生命が危険に晒されています。
こういった危険を回避するためにした自転車の無断借用(窃盗罪)やビルへの不法侵入(建造物侵入罪)、線路内への立ち入り(鉄道営業法違反)は、罰せられることがないわけです。
緊急避難も刑法で定められている概念です。
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法37条1項(緊急避難)
正当防衛は相手からの権利侵害に対する防衛行為としてその相手に対して権利を侵害する行為、緊急避難は危機回避のためにやむを得ず無関係の第三者の権利を侵害する行為という点で、それぞれ違いがあります。
こんなケースは正当防衛にあたる?
Q.小突いてきたケンカ相手にケガさせたら?
小突いてきたケンカ相手にケガさせたら、正当防衛は認められず、傷害罪として処罰されるのが通常です。正当防衛は、自分の身体や生命、財物を守るために行っている必要があります。
たとえ先に相手が攻撃を仕掛けてきたとしても、小突いた程度では身体や生命の危機があるとはいえません。状況によっては暴行罪や傷害罪となってしまいますので、正当防衛だろうと思って安易にやり返したりしない方がいいでしょう。
Q.鉢合わせた泥棒に暴行を加えたら?
鉢合わせた泥棒に暴行を加えたら、状況に応じて、正当防衛が認められる場合と認められない場合にわかれるでしょう。
正当防衛が認められる場合で考えられるのは、鉢合わせた泥棒に自分の身体や生命、財物を侵害されそうになっており、泥棒を取り抑える目的で取り押さえたら、結果的に暴行してしまったようなケースです。
正当防衛が認められない場合で考えられるのは、鉢合わせた泥棒が結局なにも盗まずに逃げようとしたため、取り押さえる目的でとっさに鈍器で殴って結果的にケガを負わせたようなケースでしょう。
なにも盗まずに逃げようとしたということは、自分の身体や生命、財物を侵害していないことになるので、過剰防衛や暴行罪、傷害罪が適用される可能性があります。
Q.ひったくり犯を追いかけて相手がケガしたら?
ひったくり犯を追いかけて相手がケガしたら、犯罪にはなりません。
ひったくりにより自分の財物を侵害されているわけなので、取り押さえる目的で追いかけて結果的にひったくり犯がケガを負ったとしても、罪に問われることはないでしょう。
正当防衛の成立が争われた有名な裁判例
判例(1)過剰防衛が認められた
「急迫性があったか」「防衛の意思があるか」という点で争いになった事件を紹介します。
最高裁判所 昭和46年11月16日判決 昭和45年(あ)第2563号
| 事件の概要 | 以前からトラブルを抱えていたAとB両名についての事件。 AがBの元へ謝罪しに訪問したところ、Bはまったく話を聞かず、Aの顔面をその場で2発殴りその後も殴りかかってきた。 Aは家の鴨居の上にクリ小刀を置いてあることを思い出してとっさにそれを取り出し、殴りかかってきたBの左胸に突き立てた。 Bは心臓を刺し貫かれて死亡した。 |
| 判決 | 過剰防衛が認められた。 |
まず、急迫性について「もともと喧嘩トラブルを抱えていた上での訪問だったのだから、何らかの暴力が振るわれる可能性は予見できたのだし、急迫性があったとは認められない」という意見がありました。
判決では「侵害があらかじめ予期されていたとしても、だからといってただちに急迫性が失われていたとすべきではない」と説示され、急迫性はあったとされました。
防衛の意思についても、判決では「相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといつて、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない」と説示され、防衛の意思はあったとされました。
一方で、素手で向かってきている相手に対してクリ小刀を持ち出して反撃するのは明らかに「やむを得ずした行為」であるとはいえないため、正当防衛ではなく過剰防衛が成立するとされました。
判例(2)正当防衛が認められた
「急迫性があったか」「不正の侵害があったか」という点で争いになった事件を紹介します。
最高裁判所 昭和26年3月9日判決 昭和25年(れ)第1856号
| 事件の概要 | 強暴な男であるとのうわさのある獰猛な人相をした男Aが私人の敷地内から薪を盗もうとしていたところ、その場に居合わせたBが見咎めた。 Aは逆上して手に持っていた生木で殴りかかってきたので、Bはとっさにその生木を奪った。 Aはそれでもなお襲い掛かってきたので、Bは奪った生木でAの頭部を1回殴打した。 結果、Aはその場で死亡した。 |
| 判決 | 正当防衛が認められた。 |
さらに細かくいうと「生木を奪われた時点で一連の犯行は終了しており、生木で頭を殴打した行為は正当防衛の要件を満たさないのではないか」という点について解釈がわかれました。
判決では「急迫性・不正の侵害はあった」とされています。
つまり、生木を奪われた後もAはBに組み付こうとしていたという点、さらにAはBよりもひと回り以上大きく、粗暴な人物であるという評判まであったという点に鑑み、依然として犯行は続いていたか再開されていた状況なので、生木で頭を叩いた行為についても正当防衛の要件を満たす、とされたわけです。
逆にいうと、同じ条件でもAが生木を奪われたあと組み付いたりせずにその場でおとなしくなっていたような場合には、追撃について正当防衛は認められなかった可能性が高いでしょう。
判例(3)正当防衛が認められた
反撃によって生じた被害の大きさを問わず、要件さえ満たされていれば正当防衛は成立すると判示された事例を紹介します。
最高裁判所 昭和44年12月4日 昭和44年(あ)第1165号
| 事件の概要 | 相手方Bから突如左手の指をねじ上げられたAが、痛さのあまりこれをふりほどこうとして、右手で相手方の胸のあたりを1回強く突いた。 Bは仰向けに倒れ、たまたま自動車のバンパーに頭を打ちつけ、加療約45日間を要する傷害を負った。 |
| 判決 | 正当防衛が認められた。 |
この事件では被害者Aは加害者Bから指をねじ上げられるという程度の暴行を受けただけであり、傷害を負うまでには至っていません。
他方、加害者BはAの反撃によって頭を打ち付けて相当重い傷害を負いました。
高裁の判決では「その因つて生じた傷害の結果にかんがみ防衛の程度を越えたいわゆる過剰防衛と見られる」として、Aを過剰防衛で有罪としました。
ただ、その後の最高裁判決では、正当防衛が成立するかどうかはあくまでその行為の内容自体を見るべきであって、防衛によって生じた結果については判断材料に入れるべきではないとして正当防衛の成立を認めました。
正当防衛のつもりが…お悩みの方は弁護士にご相談ください
ご自身の行為が正当防衛にあたるのか不安な方は弁護士に相談
「防衛の意思にもとづいて行なったやむを得ない行為」については正当防衛が認められます。
しかし、「殴られたから、殴り返した」といった単なる仕返し行為までは、正当防衛にはならず、当然ながら犯罪に問われます。
また、その行為が本当に正当防衛だったのか判断するのは検察官、裁判官です。いくら自分としては「防衛の意思があった」「やむを得なかった」「他に選択肢がなかった」などと主張しても、聞き入れてもらえるかどうかは分かりません。
もし万が一、危ない目に遭ったときには、「どこからどこまでが正当防衛なんだろう?」と考える余裕はありません。まずは何より事を穏便に済ませられないかを考えるべきといえるでしょう。
仮に反撃するとしても、絶対にやむを得ないレベルに抑えることを意識して、怒りに任せて積極的に攻撃しにいったりしないよう注意が必要です。
すでに相手方に反撃をしてしまい「自身の行為が正当防衛にあたるか知りたい」「この先刑事事件化してしまうか不安」といったお悩みをお持ちの方は、弁護士に相談されるのがおすすめです。
弁護士なら法的な知識と経験から正当防衛の成立の可否について客観的に判断することができますし、その後の逮捕や起訴を防ぐための手続きを迅速に実行することができます。
お悩みの方は以下の窓口からお問い合わせいただき、相談予約をお取りください。
アトムの解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った事案のうち、正当防衛を主張した事件について、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。
正当防衛を主張して不起訴になった事例(1)
路上で被害者男性ともめごとになり、腕を噛むなどの暴行を加え、被害者に怪我を負わせたとされるケース。傷害の事案。
弁護活動の成果
検察官に不起訴意見書を提出するなどの情状弁護を尽くし、不起訴処分を獲得した。
示談の有無
ー
最終処分
不起訴
正当防衛を主張して不起訴になった事例(2)
グループホームの利用者間でおきた傷害事件。ご本人は正当防衛を主張していた。
弁護活動の成果
目撃者の主張内容と、ご本人の認識が異なり、厳しい取り調べが予想されたため、弁護士から黙秘権の行使を提案。
弁護士から警察や検察へ説得をおこない弁護を尽くした結果、不起訴処分を獲得した。
示談の有無
ー
最終処分
不起訴
アトムの弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。
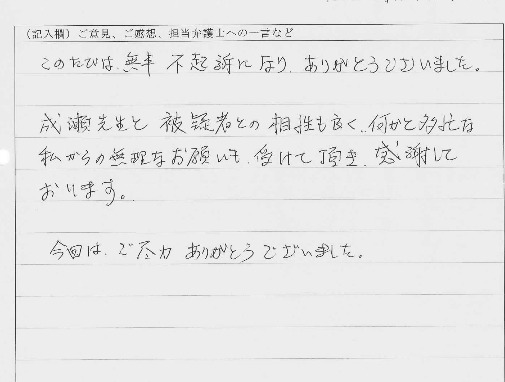
このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。
適切な助言や種々の配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。
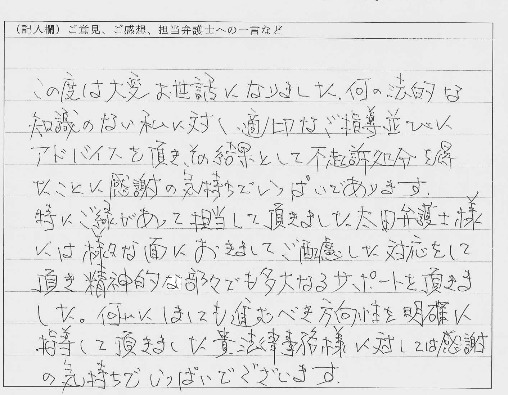
この度は大変お世話になりました。何の法的な知識のない私に対し、適切なご指導並びにアドバイスを頂き、その結果として不起訴処分を得られたことに感謝の気持ちでいっぱいであります。特にご縁があって担当して頂きました太田弁護士様には様々な面におきましてご配慮した対応をして頂き精神的な部分でも多大なるサポートを頂きました。何れにしましても進むべき方向性を明確に指導して頂きました貴法律事務所様に対しては感謝の気持ちでいっぱいでございます。
刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。
あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。
24時間体制の相談予約窓口はこちら
刑事事件に注力しているアトム法律事務所では24時間・365日対応の加害者側の相談予約受付窓口を開設しています。
突如逮捕されてしまった、警察から呼び出しを受けたなど警察介入事件の場合は初回30分無料での弁護士相談も実施しています。
- 自分のした行為は正当防衛になる?
- 正当防衛のつもりだったのに、逮捕された。今後どうすればいい?
上記のような正当防衛についての疑問やお悩みを抱えている方は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。お電話お待ちしております。




