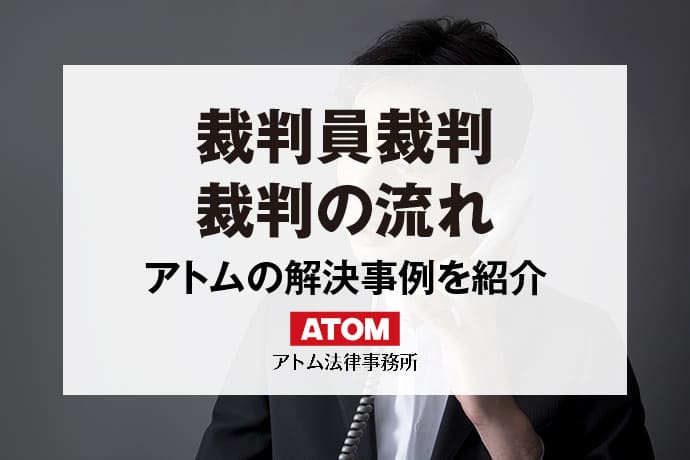
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
- 裁判員裁判とは?
- 裁判員裁判を回避するには?
- 裁判員裁判の流れは?どんな人が裁判員になる?
裁判員裁判とは、裁判官のほかに、一定数の国民が審理に参加する刑事裁判のことです。くじ引きや面談などの方法で、国民の中から6人の裁判員が選任され、裁判官3人と一緒に刑事裁判の審理をおこなうのが、裁判員制度です。
裁判員は、裁判官とともに事件を審理しますが、有罪にするか無罪にするかだけではなく、有罪の場合にはどのくらいの刑罰を与えるべきかについても、裁判官と一緒に議論して決めます。
このような裁判員裁判の制度は、刑事裁判に一般市民の社会経験や知識を反映させることを目的として、2009年につくられました。
それまでの刑事裁判では、犯人が自白しているから(やや不合理な言動や証拠があっても)有罪判決が出され、えん罪で収監されるケースが目立ちました。
そこで、犯人の言動がありうるものなのか、証人の証言が信用できるものなのかなど、まっさらな市民感覚で判断できるように導入されたのが、裁判員裁判です。
なお裁判員裁判になる事件は、すべての刑事事件ではありません。
一定の重大犯罪についてのみ、裁判員裁裁判の対象事件になるものです。殺人、放火、偽造通貨行使などの刑事事件で、裁判員裁判が開かれたニュースを聞いたことがある方も多いと思います。
この記事では裁判員裁判の概要について解説していきます。
この記事でわかること
- 裁判員裁判はどんな制度か
- 裁判員裁判の対象事件は何か
- 裁判員裁判の裁判員の選び方
- 裁判員裁判の審理の流れ
- 裁判員裁判の対象事件を起こしてしまった場合のその後の流れ
- アトム法律事務所で弁護した裁判員裁判の事例
etc.
裁判員裁判の対策、裁判員制度の全体像について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
裁判員裁判の不安について弁護士相談をご希望される方は、以下の相談予約受付窓口までご連絡ください。24時間体制で専属スタッフが相談予約受付中です。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
裁判員裁判とは?裁判員制度の目的は?
裁判員裁判とは?
裁判員裁判は、裁判官のほかに、裁判員も加わって刑事裁判の審理をおこなう制度です。
裁判員は、国民の中から選出され、裁判官とともに事件を審理し、有罪判決・無罪判決の判断や、刑罰の重さの判断をおこないます。
通常、刑事裁判は、裁判官、検察官、弁護士という法律の専門家が中心になり事件を審理する形が基本です。ですが、一部の重大な犯罪に限り、裁判員(法曹資格がない国民)が参加する「裁判員裁判」が実施されています。
裁判員裁判はいつ始まった?
裁判員制度は、2009年5月から開始されています。
裁判員裁判の目的は?
裁判員制度は、一般国民の知識や経験を裁判に反映させ、国民の裁判への理解を深めるという目的で作られた刑事事件の裁判制度です。
たしかに、裁判官、検察官、弁護士により高度な法的知識を用いて刑事裁判が行われることで、審理は緻密に行われることが期待できます。
しかし、国民の理解が追いつかなかったり、一般社会の認識とかけ離れたりするおそれもあります。
そこで、国民を裁判に参加させることで、より裁判内容を国民の感覚・理解に近づけようとして設計されたのが、この裁判員制度です。
裁判員裁判の裁判員ってどんな人?
裁判員はどうやって選ばれる?
裁判員裁判の裁判員に選出されるまでには、厳正な手続が行われます。
裁判員裁判の候補者選びの流れ
- 裁判員候補者名簿の作成
(くじ引きで裁判員候補者に選ばれる。裁判員候補者名簿に名前がのる) - 名簿記載通知・調査票が到着
(辞退事由などの申告etc.) - 事件ごとに裁判員候補者を選定
(再度くじ引きがおこなわれ、事件ごとに候補者が振り分けられる) - 呼出状・質問票が到着
(不公平な裁判になるおそれや、辞退希望の有無・理由などを確認etc.) - 選任手続期日
(裁判員6人が選ばれる。必要であれば補充裁判員も選ばれる)
①裁判員候補者名簿の作成
まず毎年秋ごろ、衆議院議員選挙の有権者の中から、翌年1年間の裁判員候補者がくじ引きで選ばれ、裁判員候補者名簿が作成されます。
②名簿記載通知・調査票が到着
名簿に登録された人には、裁判所から「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」(名簿記載通知)が届きます。
この段階では、裁判員になる可能性があるというだけで、まだ正式に裁判員になることが決定したわけではありません。
職業などの関係で絶対に裁判員になれない人や、裁判員裁判の辞退事由に該当する人は、この名簿記載通知とともに送られてくる「調査票」に回答します。
そうするとその後の選任手続きに進むことなく、この時点で裁判員候補者から除外されます。
③事件ごとに裁判員候補者を選定
そしてその後、次の段階として、各事件ごとに、裁判員候補者が選ばれることになります。再度、名簿の中から裁判員候補者をくじ引きがおこなわれます。
④呼出状・質問票が到着
具体的な事件について裁判員候補者に選ばれたら、今度は「裁判員等選任手続き期日のお知らせ」(呼び出し状)という通知書類が届きます。
このとき同封されている質問票を返送し、やむを得ない事情があれば裁判員を辞退することもできます。
裁判員候補者のうち、辞退を希望しなかった人や辞退が認められなかった人は、選任手続きの期日に裁判所に出頭します。
⑤選任手続期日を経て裁判員6人が選ばれる
上記のプロセスを経て、最終的に事件ごとに6人の裁判員が選出されます。
これに加えて必要な場合は補充裁判員も選ばれます。
補充裁判員とは、裁判員に欠員が生じてしまった場合に、その裁判員と交代するための予備の裁判員のことです。
補充裁判員は、ひとつの事件につき最大6人まで選ばれます。
裁判員裁判を辞退できるのはどんなとき?
裁判員裁判を辞退できるのは、主に次のような場合です。
- 裁判員の候補者が70歳以上の場合
- 裁判員の候補者が学生の場合
- 裁判員の候補者が親族の介護を必要とする場合
- 裁判員の候補者が仕事をしなければ事業に著しい損害が生じる恐れがある場合
ただ仕事が忙しいという理由では裁判員を辞退することは認められないので注意が必要です。
一方、株主総会の開催月という理由であれば辞退できるケースもあるようです。
あくまでケースバイケースということでしょう。
裁判員の辞退事由については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律16条に規定されています。
裁判員裁判の裁判員に求められること
裁判員裁判では、その制度趣旨からもわかるように、この制度は一般の国民の知見を裁判に反映させることが重視されます。
したがって、裁判員は、裁判員裁判に参加するにあたって、事前に法律を学び一定の知識を身につけなければいけないということはありません。
むしろ、社会生活を営む一個人の常識的感覚が大切です。裁判員に選ばれたからといって、特別に用意しなければいけないことはありません。裁判員に必要なのは、審理に参加する心の準備です。
裁判員裁判の評議ではある程度、裁判官が司会になり、「こういう場合は、こんなふうに考えるんだよ」という助言をしてくれることもあるでしょう。
ですが「裁判官から言われたから、そういうものなんだろう」とか、あるいは「多数派の意見に従おう。長いものには巻かれて、賛成しておけば無難だ」などというスタンスではいけません。
疑問に思ったことは、積極的に裁判員から発言し、意見を出したり、意見を求めたりしていくべきです。
裁判官であろうと裁判員であろうと、審議のかかわった全員の意見が、裁判の結論に直接反映されます。裁判員裁判に参加することになったら、自信をもって結論を出せるように、議論を重ねてください。
裁判員裁判の裁判員が絶対に守るべきこと
裁判員は、判決を導くに当たり、非公開の場で意見を述べるという場に参加します。裁判官やほかの裁判員と議論をかわしますが、これを「評議」といいます。
裁判員裁判の評議で議論されたことや、裁判員が職務上知りえたことは口外してはいけません。裁判員には守秘義務が課されます。
守秘義務は、裁判が終わったあとであっても守らなければならず、これに違反すれば「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることもあります。
裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律108条
裁判員裁判の対象事件
裁判員裁判の対象になる犯罪名(一覧)
裁判員裁判の対象となる事件は、刑の上限として無期懲役や死刑が予定されているような重大犯罪や故意の犯罪行為により人を死亡させた罪です。
たとえば、殺人、強盗致傷などを含む以下のような罪を犯した場合に、検察官に起訴されると、裁判員裁判が開かれます。
- 殺人
- 強盗致傷
- 覚醒剤取締法違反(営利目的の輸入)
- 現住建造物放火
- 傷害致死
- 不同意わいせつ致傷
裁判員裁判の対象事件はどのくらいあるのか?
令和3年に新たに受理された、裁判員裁判対象事件の人員数は793人でした。終局した裁判員裁判対象事件の人員数は928人です。
裁判員裁判対象事件の中で最も数が多いのは、殺人(新規受理136人、終局226人)で、その次に強盗致傷(新規受理136人、終局226人)が続きます。
なお、裁判員裁判で判決を受けた人員904人のうち、無罪判決となったのはわずか9人のみでした。
※参照:令和4年版犯罪白書
裁判員裁判の審理の流れ
裁判員裁判は次のような流れで審理されていきます。
- 公判前整理手続き
- 公判手続き
- 評議・評決
- 判決
それぞれ、詳しく説明していきます。
裁判員裁判の公判前整理手続き
公判前整理手続きとは、公開の法廷での審理(公判)が始まる前に、裁判官、検察官、弁護士が打合せを重ね、公判で何を明らかにするかを決める手続きのことです。
裁判員裁判の公判前整理手続きに、裁判員が参加することはありません。公判前整理手続きは、裁判官と検察官、弁護士(場合によっては被告人も参加)で実施されます。
裁判員裁判の公判手続き
裁判員は公判手続きから審理に参加します。公判手続きは、刑事裁判と聞いたときにイメージする、裁判所での裁判期日のことです。
裁判員裁判の公判手続きでは、冒頭手続きと証拠調べ手続きが行われます。
裁判員裁判の冒頭手続きでは、被告人の本人確認や、検察官による起訴状の朗読、被告人に対して黙秘権の告知などが行われます。
裁判員裁判の証拠調べ手続きでは、証人尋問や被告人質問が行われます。裁判員は、検察官と弁護人の主張を聞いて、証拠に基づいて事実を認定しなければなりません。
最後に、検察官の論告・求刑と弁護人の最終弁論となります。
裁判員裁判の評議・評決
裁判員裁判の公判手続きが終わると、裁判官と裁判員は証拠をもとに、判決を決めるための評議を行います。
評議をおこなったうえで、評決をとります。評決では、有罪か無罪かを決めたり、有罪の場合は量刑を決定したりします。
全員の意見がまとまらなかった場合は、多数決で結論が導かれます。ただし、この多数決での多数意見の中に、1名以上の裁判官が含まれていなければいけません。
裁判体は裁判官3名、裁判員6名で構成されるのが原則です。多数決で結論を決めるには、最低でも5名が同じ意見を持っている必要があります。
ただし例えば5名の裁判員が「有罪」と意見を表明しても、その中に1名も裁判官が含まれていない場合もあるでしょう。そのような場合は「無罪」という判決が導かれます。
裁判員裁判の判決
評決の内容が決定されると、裁判長が判決の宣告を行います。
裁判員裁判の判決は必ず有罪?
殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪などの重大犯罪に裁判員制度は適用されますが、必ず有罪になるとは限りません。
裁判とは、有罪無罪を決するために「審理」をするステージです。有罪判決が言い渡されるまでは、被告人には「無罪推定」がはたらいていることを忘れてはいけません。
しかし、これら重大犯罪が起訴され刑事裁判になれば、マスコミ報道で取り上げられることも多く、世間は被告人に対して「犯人」という印象を持つでしょう。
裁判員裁判の裁判員に選ばれた方たちには、有罪無罪を検討する際、マスコミの情報に影響されることなく、法廷に提出された証拠のみを基礎に、冷静に判断することが求められます。
アトム法律事務所で弁護した裁判員裁判の実例
アトム法律事務所は、刑事事件の加害者側の弁護活動に注力する事務所であり、裁判員裁判の解決実績も豊富です。
ここでは、過去に弁護した裁判員裁判の事例を抜粋してご紹介します。
実例①強盗致傷の裁判員裁判で無罪判決
路上で被害者女性を倒す等の暴行を加えて頭部打撲等の傷害を負わせ、現金約数千円とカバン等を強盗したとされたケース。依頼者は犯人性を否認。強盗致傷の事案。
弁護活動の成果
一貫して犯人性を否認。犯人でないことを示す証拠の収集のため証拠開示請求を行うなどして主張・立証を尽くした結果、裁判員裁判で無罪判決を獲得した。
最終処分
無罪
実例②強制わいせつ致傷の裁判員裁判で執行猶予つき判決
路上で被害者女性を倒して両膝挫傷等の傷害を負わせ、陰部を直接触る等のわいせつ行為をしたケース。強制わいせつ致傷の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談が成立。弁論で量刑傾向などを示す等して粘り強く主張・立証を行い、裁判員裁判で執行猶予つきの判決を獲得した。
最終処分
懲役3年、執行猶予5年(保護観察付)
実例③罪名を変更させ裁判員裁判を回避した事例
コンビニ万引き後、逮捕を回避するため、追いかけてきた店長に暴行を加え、全治2週間の傷害を負わせたケース。当初、「強盗致傷」で捜査を受けたが、最終的には「窃盗罪と傷害罪」での起訴となった。あわせて別の機会におこなった万引きも起訴された。
弁護活動の成果
当初、強盗致傷事件として捜査が進められていた。そのままの罪名では裁判員裁判になることが確実であるところ、本件の行為態様からして強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪が成立するにとどまる旨、検察官に主張し、裁判員裁判を回避。
あわせて被害店舗・被害者に対して謝罪と賠償を尽くして示談が成立。
刑事裁判では、粘り強く主張・立証を行い、執行猶予付き判決を獲得。
最終処分
懲役2年、執行猶予3年
実例④示談成立により裁判員裁判を回避・不起訴の事例
従来より性的関係のある知人に対し、傷害を負わせたり、性行為におよぶよう求めたりしたケース。強制性交等致傷の事案。
弁護活動の成果
強制性交等致傷(現 不同意性交等致傷)は、起訴されれば裁判員裁判になる。
被害者に対して謝罪と賠償を尽くした結果、示談が成立。
最終処分
不起訴
裁判員裁判の弁護活動のポイントは?
裁判員裁判で伝えるポイント①反省をきちんと表明
重大な刑事事件をおこしたことが事実である場合、真摯に反省していることを、被害者のみならず、裁判員に対してもきちんと伝わるように主張する必要があります。
たとえば被害者との示談成立は、自身が反省していること、更生の可能性があること、被害が回復したことなどを示す事情となり、刑罰の軽減に影響があります。
そして裁判官であれば「被害者との示談成立は刑罰が軽くなる事情である」と反射的に判断でき、その事情をくんで検討してくれます。
しかし裁判員の場合は、裁判実務の経験がないため、反省や更生の意欲が上手く伝わらないおそれがあります。そのためこの点十分留意して、刑事裁判にのぞむ必要があります。
裁判員裁判で伝えるポイント②市民感覚での合理性
裁判員裁判において無罪を争う・量刑を争う場合など、裁判員を説得するのであれば、「そのような状況に置かれれば、こういう行動をとるのが当然だ」「日常生活をおくるなかで、そのような発言をするのは自然だ」などと思ってもらえるような主張をおこなう必要があります。
とくに自白調書や状況証拠がある場合、裁判官は有罪認定にかたむきやすく、裁判員は裁判官の意見に影響をうけやすいものです。また、法廷での検察官のプレゼンテーションで、印象操作をされないように注意をはらう必要もあります。
裁判官と裁判員の合議のなかで、裁判員のほうから市民感覚にもとづいて問題提起ができるように、刑事弁護人は分かりやすく、記憶に残る弁護活動をおこなう必要があります。
裁判員裁判の不安は弁護士に相談
裁判員裁判の対象事件を弁護士相談するメリット
過去のアトム法律事務所の解決事例をご覧いただければお分かりになるとおり、裁判員裁判の対象事件で弁護士をつけた場合、無罪判決の獲得、刑罰の軽減(執行猶予つき判決の獲得)、(罪名落ちによる)裁判員裁判の回避、不起訴などを目指せる可能性があります。
裁判員裁判対象事件の弁護士相談
- 無罪判決
- 刑罰の軽減(執行猶予つき判決の獲得)
- 裁判員裁判の回避
- 不起訴
etc.
裁判員裁判の対象事件をおこしてしまった場合は、早期の弁護活動が必須です。
刑事事件の弁護活動に力を入れている事務所に、できるだけ早く弁護士相談に行きましょう。
24時間つながる弁護士の窓口は?
アトム法律事務所では24時間つながる相談予約受付窓口を設置しています。
裁判員裁判を受けることや、重大な刑事事件をおこしてしまった悩んでいる方は、アトム法律事務所までご相談ください。
警察から呼び出しがきた、取り調べを受けた、逮捕されたなど警察介入事件の場合、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。
ご家族の方からのご相談も可能です。
是非お早目にお電話ください。



