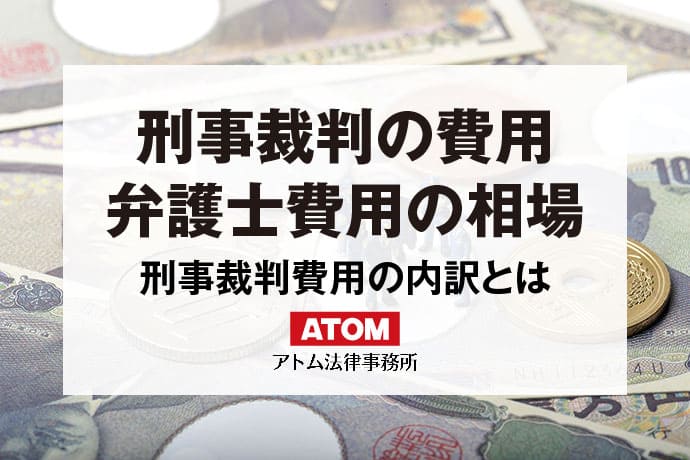
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
刑事裁判にかかる主な費用は、証人の旅費・日当・宿泊料、鑑定料や通訳費用、弁護士費用の3種類です。
刑事裁判の費用は一旦国が負担しますが、有罪判決を受けた場合は被告人に支払いが命じられることがあります。
また、私選弁護人に依頼する場合は別途弁護士費用が必要になります。
この記事では、刑事裁判の費用の具体的な内訳と金額、裁判費用をだれが払うのか、国選弁護人と私選弁護人の違いについて説明します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
刑事裁判費用の内訳は3つ
刑事訴訟費用等に関する法律によると、刑事裁判にかかる費用は、証人費用、鑑定や通訳費用、弁護士費用の3つとされています。
これらの費用は裁判所から支払われますが、被告人が有罪判決を受けた場合は、裁判所が払った費用の全部または一部が被告人に請求されることがあります。
(1)証人費用
刑事裁判において、被告人の刑が軽くなるように法廷で証言をする人を証人(情状証人)といい、証人を出廷させた場合には証人費用として旅費・日当・宿泊料が発生します。
証人費用
公判期日若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき旅費、日当及び宿泊料
鉄道賃・船賃などは実費を旅費として認められることが多いです。ただし運賃に等級がある線路や船舶を利用した場合は一定の制限が設けられています。航空賃についても相当の範囲内で実費が認められるでしょう。いずれも裁判所が判断した金額とされています。
証人の日当は、1日あたり上限8,200円と定められています。証人費用の具体的な金額は、この上限の範囲内で事案ごとに裁判所が決定します。日当の金額を決める際には、所要時間や待機時間などが考慮されます。
証人の宿泊料は上限8,700円または上限7,800円を範囲として、裁判所の認める金額が給付されます。宿泊地による区分があり、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうちの一定の地域やこれらに準じる一定の地域は上限8,700円とされています。
もっとも、家族や知人が証人となった場合は、旅費・日当・宿泊料を放棄することがほとんどのため、証人費用はかからないケースが多いです。
参考
(2)鑑定料や通訳・翻訳費用
刑事裁判において鑑定・通訳・翻訳を利用した場合には、鑑定人・通訳人・翻訳人に費用を支払います。
刑事裁判における鑑定とは、専門家が特別な知識や経験を活用して、事件の真相解明や被疑者の責任能力判断などに関する専門的な見解を提供する手続きです。
鑑定料や通訳・翻訳費用
公判期日又は公判準備において鑑定、通訳又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用
鑑定人・通訳人・翻訳人の日当は、7,800円を上限として支給されます。また、鑑定人・通訳人・翻訳人の宿泊料は、証人の宿泊料と同じく、一部地域では上限8,700円、それ以外の地域では上限7,800円の範囲で支給されます。
なお、鑑定料・通訳料・翻訳料の具体的な金額は、裁判所が相当であると認めた金額とされています。
(3)弁護士費用
弁護士費用とは、刑事事件の弁護人に対して支払う費用のことで、旅費や日当、宿泊料、弁護士報酬が含まれます。
ここでいう弁護士費用とは、私選弁護人に払う費用ではなく、国選弁護人をつけた場合の弁護士費用のことです。
国選弁護人への弁護士費用は、原則として国が負担するので無料となりますが、判決次第では被告人が支払わねばなりません。
弁護士費用
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬
国選弁護人は国が弁護人を選任する制度です。勾留後は全ての被疑者が国選弁護人をつけることができますが、資力が50万円未満の場合に限るなど一定の要件があります。
国選弁護人への報酬としては裁判1回につき6万6,000円から10万円程度が支払われます。裁判で無罪判決を獲得した場合や、身柄が釈放となった場合など、成果に応じた加算報酬も支払われる仕組みです。
関連記事
・国選弁護人をつけられる条件は?費用はかかる?私選弁護人との違いも解説
刑事裁判の費用は誰が払う?
有罪なら被告人が裁判費用を支払う
刑事裁判で有罪判決を言い渡す際、裁判所の判断により、被告人に対して裁判費用の全部または一部を負担するよう命じられることがあります。
ここでいう裁判費用とは、証人費用、鑑定料や通訳・翻訳費用、国選弁護士費用のことです。
第百八十一条 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
刑事訴訟法
被告人に訴訟費用を支払わせる場合は、判決でその旨が言い渡されます。
もっとも、被告人に資力がなく裁判費用を払えないのが明白であれば、裁判所は裁判費用の支払いを命じない場合もあります。
もちろんですが、私選弁護人に依頼している場合の弁護士費用は、被告人が支払います。
無罪なら国が被告人に裁判費用を補償する
刑事裁判で無罪判決が言い渡された場合は、国が裁判費用を負担するほか、被告人が裁判のために支払った費用を国が補償します。
補償の対象になる裁判費用とは、本人が裁判に出廷するためにかかった旅費、日当、宿泊料と、弁護士に支払う旅費、日当、宿泊料および報酬です。
ただし、弁護士の報酬は国選弁護人の費用を基準に計算されるため、私選弁護人の報酬すべてが補償されるわけではありません。
また、刑事補償法にもとづき、無罪が確定するまでの間身体を拘束されていた日数に応じて、1日あたり1,000円~12,500円の範囲で補償を受けることができます。
刑事裁判の費用を払えない場合は?
判決で命じられた裁判費用の支払いが困難な場合は、判決から20日以内に訴訟費用免除申請を提出することで支払いを免除される場合があります。
訴訟費用の免除を申請する時は、自身の資力を示す書類の提出も必要です。
刑事裁判の弁護士費用はいくら?
刑事裁判の弁護活動を私選弁護人に依頼した場合、法律相談料、着手金、報酬金といった弁護士費用がかかります。それぞれの概要と相場をみていきましょう。
相談料・着手金・報酬金
まず、弁護士に法律相談をする上で、法律相談料が必要です。
法律相談料の相場は、30分~60分で5,500円~11,000円程度といえます。
ただし、逮捕されている方のご家族や、すでに警察から呼出しを受けている方の相談では無料相談を積極的に行っている法律事務所もあります。
刑事弁護を依頼することになった場合、開始時には着手金が、依頼の終了時には報酬金が発生します。
着手金は、弁護活動を行うに当たり最初に必要となる費用です。結果にかかわらず、返金はされない性質の費用が着手金です。
一方、報酬金は結果に応じて発生するもので、良い結果が出れば高い金額設定になっているのが一般的でしょう。他にも、郵便代や交通費といった実費や、公判活動、接見、示談などで日当が発生することもあります。
弁護士と委任契約を締結する際には、かならず書面で弁護士費用の内訳が明記されているかを確認することをおすすめします。どのような費用がどの時点で発生するか、総額の費用としていくら用意しておくべきか、法律相談の際に十分な説明を聞いた上で契約の判断をすることが望ましいです。
逮捕・勾留された場合に想定される弁護士費用
逮捕・勾留された場合には、釈放に向けた弁護活動が必要になります。このような活動を「身柄解放活動」といいます。
被疑者の身柄を解放するために、弁護士は検察官や裁判官に意見書を提出したり、裁判官が出した勾留決定に不服申立てを行います。
また、検察官や裁判官に直接会い、事情を説明して釈放を求めることもあります。このような活動では書面を郵送するときに実費がかかったり、弁護士が移動するため日当や交通費が生じることが予想されます。
また、釈放がかなった場合には、その結果に対して報酬が発生する可能性があるでしょう。
逮捕後の身柄解放活動が成功した場合にはいくら発生するか、弁護士との委任契約書で確認しておきましょう。最終的な刑事事件の結論にだけ報酬が発生するわけではありません。勾留阻止、保釈許可、示談成立、不起訴獲得、執行猶予獲得、刑の減軽など、それぞれに報酬が設定されているのが一般的です。
被疑者・被告人ではかかる弁護士費用が異なる
起訴される前の被疑者段階では、釈放と不起訴処分の獲得が大きなゴールです。
場合によっては、略式起訴での罰金処分を狙い、公判請求(公開の法廷で刑事裁判を受けること)を回避する方針で弁護活動が展開されることもあります。
起訴され被告人という立場になれば、保釈、執行猶予の獲得、刑を軽くするということが弁護活動の目標になります。
被疑者段階と被告人段階では、弁護士の活動内容が異なるため弁護士費用も変わります。依頼をする前に弁護士にどのような活動をしてもらうかを確認すると同時に、それにかかる費用の概算を聞いておくようにしましょう。
また、示談金、贖罪寄付金、保釈保証金については、弁護士費用とは別のものです。要否や必要となるタイミングについては事件により異なります。随時、弁護士と相談しながら用意していくこととなります。
関連記事
・保釈金の相場はいくら?返ってくる?保釈金が用意できない時の対応
刑事裁判の弁護士費用|私選弁護人と国選弁護人
私選弁護人と国選弁護人の違いについて、主に弁護士費用の観点から解説します。
私選弁護人と国選弁護人の違い
私選弁護人とは、自分で探して依頼した弁護士のことです。
自分や自分の家族が弁護士を探すことになるため、知人友人に弁護士がいない場合はインターネットで検索することになるでしょう。
私選弁護人に弁護活動を依頼する場合は、委任契約を締結します。互いに契約内容に同意すれば、契約成立となります。私選弁護人にかかる弁護士費用は、弁護士(法律事務所)により異なりますので、個別に確認することが必要です。
国選弁護人制度は、資力の問題で私選弁護人をつけることができない場合に、国に弁護士をつけてもらうことができる制度です。資力が50万円未満であるとき、国選弁護人を希望することができます。
注意点として、国選弁護人は自分で弁護士を選ぶことができないという点があげられます。仮に刑事事件の実践経験が浅い新米弁護士がついたとしても、それを受け入れなければいけません。
刑事事件で私選弁護人を選ぶメリット
国選弁護人制度の利用では基本的に費用負担がないため、弁護士費用を支払う余裕がない人にとっては助かる制度です。ただし、どのような弁護士にあたるかわからないという点がデメリットといえます。
私選弁護士であれば、自分で希望する弁護士を選ぶことができるという点が大きなメリットです。
私選での弁護活動を行う弁護士は、前提として刑事事件に力を入れている場合が多いです。被疑者・被告人の人権を守るため、時間外の活動も率先して行ってくれることもあります。刑事事件は土日、深夜早朝、時間を選ばずに発生するものです。家族が突然逮捕されたとなると、直ちに弁護活動を開始しなければ手遅れになるケースもあります。
弁護士にはすぐに警察署に急行してもらい、被疑者本人に取調べへのアドバイスをしてもらうことが大切です。刑事弁護に熱心な弁護士を選任するには、私選弁護人をつけることがおすすめです。
関連記事
・弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?費用・メリット等の違いを徹底比較
国選弁護人から私選弁護士人への切り替えは可能
弁護士費用が工面できず、最初は国選弁護人をつけていたものの、家族の協力で金策ができたという場合があります。そのときは、国選弁護人から私選弁護人に切り替えることができます。
国選弁護人制度は、費用の支払い能力がない被疑者・被告人を救済する制度です。ですので、費用の工面ができた場合には、どの刑事手続きの段階であっても私選弁護人に変更することができます。
ただ、その反対はできません。つまり、私選弁護人を付けていた状態から国選弁護人に切り替えることは許されていません。私選弁護人を選任している時点で、費用負担に耐えられる資力状態であると認定され、国選弁護人制度の利用条件から外されてしまいます。
関連記事
・国選弁護人を解任したい…解任方法と私選弁護人への切り替え手続き
弁護士費用と弁護士の力量|契約前に注目すべきポイント
刑事事件の結果は被告人の人生を左右するものです。最後に、どんな弁護士を選ぶべきかというポイントや弁護士の力量、契約前の注意点について解説します。
刑事事件は弁護士の経験値・実績に注目する
弁護士を選ぶ際に注目すべき点を3つまとめておきます。もちろん人によって気になることは違うと思いますが、この3つを押さえておけば間違いないでしょう。
- 刑事事件の経験値が高い(実績豊富)
- フットワークが軽く仕事が早い
- 連絡・報告がこまめにある(連絡がとりやすい)
反対に、依頼者が持つ弁護士に対する不満で多いことは、この3点の裏返しになります。的確な回答をしてもらえない(経験値が低い)、動きが遅く不安になる、なかなか担当弁護士に連絡がとれず進捗状況がわからない、という点です。結果とプロセスの両方を重視し、誠実な依頼者対応をしてくれる弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事裁判の結果は弁護士により違う
刑事裁判を行う上で、弁護士の力量は結果に反映されます。弁護士は法律の専門家であり、弁護士資格を有している以上、その知識や能力は一定の水準以上であることが担保されています。しかし、実際に刑事裁判で要求されることは証人尋問の技術であったり弁号証(弁護士が提出する証拠)の選択判断です。
刑事裁判では最後まで裁判官の心証はわからないものです。検察官の意見にどう反応するか、被告人との打合せは万全か、細かなことまで気を配る必要があります。一つ一つに誠意をもって対応をしてくれるかは、弁護士により異なります。刑事事件は人生を大きく変えうる局面ですので、どの弁護士に担当してもらうかは重要です。
弁護士費用は法律相談の中で見積りをとる
私選弁護人をつけるといっても、やはり弁護士費用は気になることです。法律相談の中で見積りの提示を求め、不明点は遠慮なく聞いて確認しておきましょう。あとから「こんなはずではなかった」ということがないよう、契約時に不明点をなくしておくことが大切です。
アトム法律事務所では、契約時は必ず契約書を2部作成し、1部を依頼者に保管いただいています。
決して低い金額の契約ではないため、契約内容を十分にご理解いただき、安心してご依頼いただけるようにしています。



