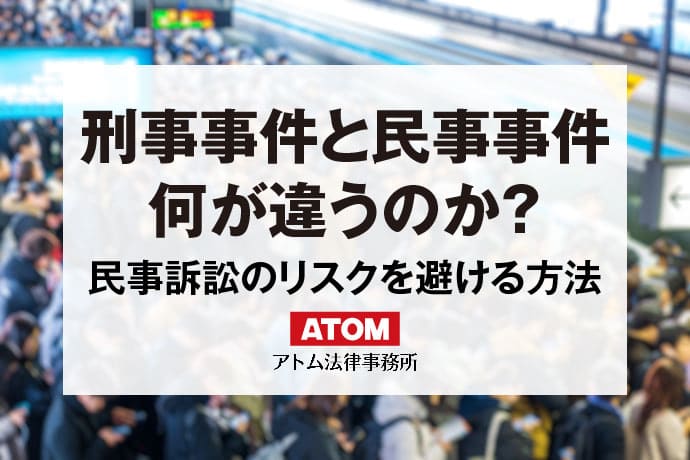
「刑事事件と民事事件の違いが分からない」「自身のトラブルが刑事と民事どちらに当てはまるのか知りたい」といったお悩みを抱えている方は多いでしょう。
刑事事件と民事事件の違いは、主に争う当事者とトラブルの対処法です。刑事事件は罪を犯した個人と国家(検察官)の争いとなる一方、民事事件は私人間(個人や法人)の損害賠償の争いとなります。
同じ事件でも刑事と民事の両方が問題となることもあるので、その違いを理解しておくことが重要です。
被害者のいる刑事事件では、基本的に刑事と民事の両方が問題となります。裁判で刑罰を受けたにもかかわらず、後日被害者から民事訴訟を起こされるということもあり得ます。
そこで、刑事事件を解決する中で、後の民事事件化を防ぐ方法について刑事事件の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士がお伝えします。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
刑事事件と民事事件の大きな違いは「争う当事者」
刑事事件は国と個人の争い
刑事事件(刑事裁判)とは、罪を犯したとされる個人に対して、国家(検察官)が裁判所に処罰を求めるものです。
ここで重要なのは、刑事事件は「犯罪の疑いがある個人 vs 国家(検察官)」という構図であり、争点は「どのような刑罰を科すか」という点にあります。
刑事事件は「加害者 vs 被害者」という対立ではないことに注意してください。
刑事事件に関するお悩みには、以下のような例が挙げられます。
刑事事件のお悩み
- 不起訴になりたい/前科をつけたくない
- 逮捕・勾留されたくない
- 警察の取り調べにどう対応すればよいか知りたい
- 刑罰を軽くしたい/執行猶予をつけたい
これらはすべて刑罰や刑事処分に関する不安、または捜査機関(警察・検察)への対応に関する悩みです。刑事事件のお悩みは、刑事事件に注力している弁護士に相談するのが適切でしょう。
なお、被害者への示談や賠償・謝罪などの「被害者対応」についてのお悩みは民事上の問題ですが、刑事処分の結果にも大きく影響します。そのため、通常は「被害者対応」も含めて刑事事件の相談として取り扱われます。
民事事件は私人間の争い
民事事件(民事裁判)とは、「人 vs 人」、「会社 vs 会社」、「人 vs 会社」など、私人間の紛争を解決する手続きを裁判所に求めるものです。
「犯罪について国が刑罰を科すかどうか」という問題以外の、民間人同士のトラブルについてはおよそほとんどが民事事件と考えて良いでしょう。国や地方自治体を訴える争いも、広い意味では民事事件に含まれます。
民事事件に関するお悩みには、以下のような例が挙げられます。
民事事件のお悩み
- 損害賠償や慰謝料を請求したい
- 貸したお金が返ってこない
- 交通事故などで示談をしたい
- 離婚や相続をめぐるトラブル
- 会社をクビと言われてしまった
民事事件は、私人同士の権利と義務の関係を調整する機能を果たし、究極的にはお金の問題といえます。
犯罪に関するトラブルであっても、被害者が加害者に損害賠償や慰謝料を請求すること、逆に言えば加害者が被害者と示談をしたり賠償をすることは民事上の問題です。
詐欺事件などで、犯人が逮捕されたとしても、自動的に騙し取られたお金が返ってくるわけではありません。犯人からお金を返してもらうためには、民事事件として請求する必要があります。
なお、窃盗事件の盗品など所有者が明らかな物品で警察が押収したものについては、刑事手続きの中で警察から返してもらうことができます(刑事訴訟法123条)。
刑事事件と民事事件のその他の違い
当事者の違い|訴訟できる人は?
何かしらのトラブルに見舞われた場合、刑事事件と民事事件のどちらにすべきなのか、という疑問を持たれる方がよくいらっしゃいます。
刑事事件と民事事件は両立します。ただし、そのうち被害者が当事者として関与できるのは民事事件についてだけです。
刑事事件は、罪を犯した人と国家の間の関係ですので、基本的には被害者が関与することはできず、被害者が訴訟を起こすこともできません。刑事事件では、訴訟を起こせるのは検察官だけです(刑事訴訟法247条)。
もっとも、直接の当事者でないとはいえ、被害者の処罰感情は刑事処分の判断に強く影響します。たとえば、被害者が民事事件の示談に応じれば、刑事事件では処分が軽くなるなどの影響を与えることがあります。
民事事件では、誰でも訴訟を起こすことができます。
訴えた側を「原告」、訴えられた側を「被告」といい、両者が当事者になります。原告と被告の違いは、どちらが権利の請求等をするかだけで、良い悪いはなく、誰でも原告にも被告にもなりえます。
関連記事
適用される法律の違い
刑事事件で適用される法律では、「犯罪にあたる行為と刑罰」が定められています。
刑法が典型ですが、それ以外にも道路交通法や覚せい剤取締法等の、特別法と呼ばれる国が定めた法律があります。また、都道府県が定めた青少年保護育成条例などの条例も、広い意味の刑法に含まれます。
捜査や刑事裁判など、刑事手続上のルールは刑事訴訟法に規定があります。
民事事件で適用される法律では、刑法のように「この行為をしたら犯罪になり、このような刑罰を与える」などという規定はなく、私人間のルールが定められています。
民法を代表例として、会社法、労働法、租税法など、社会における分野に沿って様々な法律が規定されています。民事裁判についてのルールは民事訴訟法に規定があります。
手続きの違い
刑事事件では、警察や検察に、手続きを遂行する際の逮捕・勾留など、一般人の権利を制約する大きな権限が付与されています。検察官が訴訟を起こして裁判が開かれれば、裁判官により必ず有罪か無罪が言い渡されます。そのため、当事者である検察官と被告人が和解することはありません。
また、刑事裁判に被告人が出廷しない場合は裁判を開くことはできません。裁判所は強制的に被告人を出廷させる手続きをとることになります。
民事事件では、原告または被告が証拠保全のための手続きを取ることができるものの、刑事事件ほどの強力な権限や強制力はありません。また、刑事事件が判決により解決するのに対し、民事事件は訴訟を起こした前でも後でも、当事者同士の和解で事件を解決し終結させることができます。
民事裁判に当事者が出廷しなかった場合、相手の言い分が100%認められます。
関連記事
刑事事件と民事事件の違いまとめ
刑事事件は、法律に違反する行為(犯罪)に対して、警察や検察が捜査を行い、裁判所が刑罰を決める手続きです。たとえば、窃盗や暴行などの犯罪行為がこれに当たります。目的は、社会の秩序を守るために、違反者に罰を与えることです。
一方、民事事件は、個人や企業同士のトラブルを解決するための手続きです。たとえば、お金を貸したのに返してもらえない場合や、契約違反があった場合などが該当します。刑罰はなく、主に損害賠償や権利の確認などが争点となります。
| 刑事事件 | 民事事件 | |
|---|---|---|
| 内容 | 罪を犯した者に、国が刑罰を科す手続き | 当事者同士の利害の調整を図る手続き |
| 当事者 | 被疑者・被告人 vs 国(検察官) | 私人 vs 私人 |
| 訴訟提起 | 検察官による「起訴」のみ | 誰でも訴えることができる |
| 法律 | 刑法・刑事訴訟法など | 民法・会社法・労働法・民事訴訟法など |
| 手続き | ・強制力のある捜査ができる ・起訴後は判決で決まる | ・刑事事件ほどの強制力はない ・裁判となっても和解で終了することが多い |
| 裁判の帰趨 | 検察官が、被告人の犯罪事実を証明できるかどうかで決まる | 「どちらの主張がより、真実らしいか」で決まる |
もし、ご自身の直面している問題が刑事事件なのか民事事件なのかわからない場合には、「犯罪について、逮捕や刑罰、警察・検察相手への対応が心配事であれば刑事事件」、「請求・交渉の相手が一般人であったり金銭の問題なのであれば民事事件」と思っていただければ、おおよそ間違いはないと思います。
刑事事件でも民事事件として訴訟されることがある?
刑事事件と民事事件の両方が問題となる事件
被害者がいる(損害が発生している)犯罪は、基本的に刑事事件と民事事件の両方が問題となり得ます。
犯罪行為によって怪我や精神的苦痛などの被害を受けた人は、加害者に対して、被った被害の損害賠償を請求する権利があります。
しかし、刑事手続では被害者との間の賠償関係は解決されません。罰金刑となった場合であっても、罰金は国に納めるものであって被害者の損害の賠償として支払われるものではありません。
「犯罪について国がどういう刑罰を科すか」という刑事上の問題と「加害者-被害者間の賠償問題」という民事上の問題は別物なのです。そのため、刑事事件が終了しても、損害賠償や慰謝料などの民事上の請求は免れません。被害者が訴訟を起こせば、刑事裁判だけでなく民事裁判にもなる可能性があります。
具体的なケース
「交通事故で人身事故を起こし、過失運転致傷罪で罪に問われて判決で拘禁刑を受けた。しかし、被害者の怪我の治療費などの損害賠償の問題が解決していないので、民事訴訟を起こされた。」
「痴漢で罰金刑になった。しかし、痴漢の被害で被った精神的苦痛を損害とする慰謝料を支払う義務があったので、別途民事訴訟を起こして請求された。」
刑事事件と民事事件で異なる手続き
刑事事件と民事事件は、その目的も内容も全く異なる手続きです。そのため、並行して行うことも可能ですし、同じ出来事について刑事事件と民事事件で異なる事実認定がされる可能性もあります。
一般的には民事訴訟を提起する場合は、刑事事件の結果が出た後である事がほとんどです。
なぜなら、刑事事件では「疑わしきは罰せず」の原則のもと極めて厳格な事実認定がされていますので、刑事事件で認められた事実はそのまま民事でも認められやすいからです。一部の重大犯罪では、被害者の民事訴訟の負担を軽減するため、「損害賠償命令制度」が設けられています。
一方で、刑事事件で罪に問われなかったとしても、民事裁判では犯罪があったと認定される可能性はあります。
民事事件ではどちらがより真実らしいかという観点から審理がされ、反論しなければ相手の主張がそのまま認められるなど、裁判で事実として認定されるために必要な証明の程度が大きく違うのです。
損害賠償命令制度とは?
刑事事件の被害者が、民事上の請求を刑事裁判の中で行うことは原則できません。ただし、殺人・傷害・強制性交等など一部の重大事件では、刑事事件の裁判を担当した裁判官が、引き続き民事上の損害賠償請求を審理する手続きが導入されています。この手続きを「損害賠償命令制度」といいます。
損害賠償命令制度では、刑事事件で利用された事件の記録を、民事事件の損害賠償請求の審理でもそのまま利用することができます。原則4回以内で審理を終了して損害賠償額を決め、裁判官が損害賠償命令を出します。刑事事件と同じ裁判官が担当するので審理がスムーズに進むメリットがあります。
刑事裁判の成果を利用する制度ですので、無罪判決が出た場合には損害賠償命令の申立ては却下されます。もっとも、その場合も通常の民事訴訟を提起することは可能です。
被害者から民事訴訟を起こされるとどんなリスクがある?
刑事事件以外に民事訴訟を起こされると、解決まで長期化するリスクがあります。
民事訴訟では、何も返答しなければ相手の請求通りの判決となってしまうため、返答や反論をする必要があり、訴訟に対応せざるを得ません。また、そのために弁護士に依頼するとなるとその費用負担も生じます。
刑事事件で示談金を払って解決したと思っていても、適切な示談ができていなければ、民事上の問題は解決していないと言われ損害賠償を請求されて二重払いのリスクを負う可能性もあります。このようなリスクを防ぐには、弁護士に示談をしてもらうことをお勧めします。
民事事件の訴訟を防ぐためにはどうすべき?
民事事件の訴訟を防ぐためには、刑事事件の中で示談を締結し、民事上の損害賠償に関する問題も一挙に解決することが有効です。示談とは、当事者間の合意を言いますが、示談の中で損害賠償や精神的苦痛に対する慰謝料などをすべて含む解決金を示談金として払い、金銭問題を解決するのです。
具体的には以下のような記載(清算条項)をおこない、後日の民事訴訟のリスクをなくすことができます。
- 加害者は被害者に対して示談金として金○○円を払う
- 加害者と被害者は、本示談書に定めるほか何らの債権債務がないことを確認する
刑事事件の示談について詳しく知りたい方、示談書のサンプルをご覧になりたい方『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』の記事をご覧ください。
被害者が示談を拒否し、刑事・民事両方の責任を強く求めている場合
被害者との示談の成立は、刑事事件において重要な意味を持ちます。なぜなら、被害の回復がされ、被害者も事件を許しているのであれば、重い刑事罰を科す必要はないと考えられるからです。
ただし、示談はあくまで民事上の合意ですので、当事者間で合意がなければ成立はしません。示談には応じず、強く処罰を求めるという被害者はたくさんいます。
そういったケースでは弁護士が入ることで、当事者間の公平という観点から、適切な金額で被害者感情にも配慮しながら冷静に示談交渉を行うことができるため、示談締結の可能性を高めることができます。
被害者側としても、示談を拒否した場合には弁護士を雇って民事裁判を起こさなければ慰謝料の支払いを受けられないリスクがあるため、交渉次第では示談に応じてもらえる可能性があります。
ひとつの事件には民事事件と刑事事件の両面がある?
事例(1)性犯罪
ケース(被害者側の視点)
電車内で痴漢の被害に遭ったが、その場で犯人を捕まえて駅員に引き渡した。警察にも話を聞かれて事情を説明し、被害届を提出した。絶対に許せないので、犯人に痴漢の慰謝料を請求したい。
このような性犯罪に関する事件の場合、加害者側の今後の流れとして、以下のような展開が考えられます。
加害者側の視点
| 民事事件 | 被害者から示談金を請求された。 今後、示談交渉が上手くいかなければ、民事裁判をおこされる可能性がある。 |
| 刑事事件 | 迷惑防止条例違反の痴漢容疑で、警察や検察から取り調べを受けた。 示談がまとまらなければ、起訴されて罰金刑になるおそれがある。 |
このような事件の場合、以下のような解決法が考えられます。
解決の視点(一例)
- 民事事件の解決法
謝罪と誠意を尽くし被害者と示談を成立させる。民事裁判を回避して、示談交渉で解決する。 - 刑事事件の解決法
示談成立の事実をもって、検察官を説得。不起訴処分で刑事事件が終了となる。
事例(2)交通事故
ケース(被害者側の視点)
停車中に追突されるという交通事故被害にあった。症状は軽いむち打ちで、通院が必要に。
おおごとにはしたくなかったが、相手方の保険会社の対応も冷たく、思い切って人身事故届を提出した。これで加害者には刑事処分がくだされるだろう。
いまも治療費や車両の修理費については、保険会社が間に入って話し合いが続いている。相手が100%悪い事故なのに、何かにつけて責任逃れをされてしまう。
このような性犯罪に関する事件の場合、加害者側の今後の流れとして、以下のような展開が考えられます。
加害者側の視点
| 民事事件 | 相手が急停車したために追突してしまったので、請求額全額をすべて自分が支払うのは納得できない。保険会社の担当者には、しっかりと示談交渉を続けてもらいたい。 しかしその反面、被害者の処罰感情が強くなってしまい、検察官の刑事裁判をおこされてしまうのではないかと不安だ。 |
| 刑事事件 | 過失運転致傷という犯罪に問われ、罰金前科がつく可能性がある。 保険会社は刑事弁護をしてくれないので、交通事故の刑事弁護に強い弁護士を見つけたい。 |
このような事件の場合、以下のような解決法が考えられます。
解決の視点(一例)
- 民事事件の解決法
保険会社をとおして、示談交渉をおこなう。
保険会社担当者や刑事弁護人の付添いのもと、適宜の方法で謝罪をおこなう。 - 刑事事件の解決法
保険で賠償見込みである旨を、検察官に報告。不起訴処分で刑事事件が終了となる 。
事例(3)詐欺
ケース(被害者側の視点)
フリマサイトで商品を購入し、代金を振り込んだが商品が送られてこない。詐欺だと思い、警察に相談した。どうにかお金を取り返したい。
このような性犯罪に関する事件の場合、加害者側の今後の流れとして、以下のような展開が考えられます。
加害者側の視点
| 民事事件 | きちんと反省しているので、被害者に対して賠償したい。 示談交渉を始めたいが、被害者の感情がおさまらず連絡さえままならない。 |
| 刑事事件 | 詐欺は、初犯でも拘禁刑の実刑判決がくだされると聞いた。 家族もいるので、どうにか不起訴や執行猶予付き判決を目指すことはできないだろうか。 |
このような事件の場合、以下のような解決法が考えられます。
解決の視点(一例)
- 民事事件の解決法
刑事弁護人に依頼して、被害者に連絡をとってもらう。自分の代わりに謝罪をいれ、示談交渉に取り組んでもらう。 - 刑事事件の解決法
被害弁償、示談交渉、再犯防止策への取り組みについて検察官や裁判官に伝え、不起訴や執行猶予付き判決をめざす。
まとめ
刑事事件の弁護活動とともに民事事件も解決できる?
ひとつの事件には、民事事件と刑事事件の両面があります。
刑事事件の被害についての示談交渉は、刑事弁護人が関与することができます。
示談交渉がまとまれば、刑事事件で不起訴になることも多いもので、民事と刑事の両方を一挙解決できる可能性があります。
示談はお相手がいることなので、絶対的に成立するとは断言できませんが、アトムの弁護士は誠意ある対応を心がけ、日々、示談交渉に取り組んでいます。
示談成立に至らなかった事件でも、示談交渉に取り組んできた過程や、再発防止に真摯に取り組んでいることなど、あなたに有利な情状をもとに、刑事弁護に尽力します。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選び・示談に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
丁寧に対応してくれ分からないことにはすぐに答えてくれました。
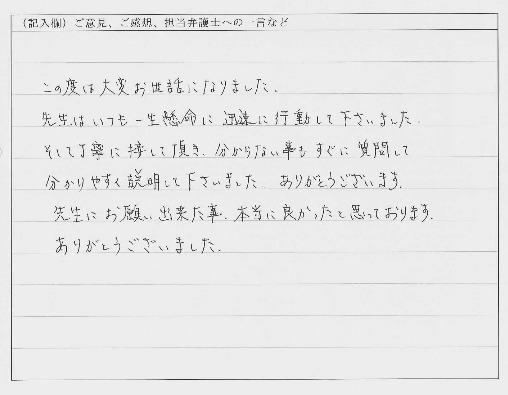
(抜粋)先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。ありがとうございます。
的確なアドバイスと迅速な対応で依頼して本当に良かったです。
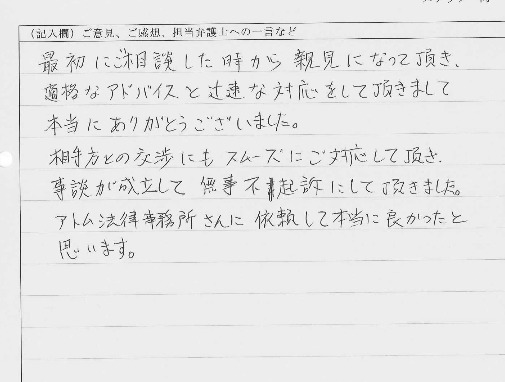
(抜粋)相手方との交渉にもスムーズにご対応頂き、示談が成立して無事不起訴にして頂きました。アトム法律事務所さんに依頼して本当に良かったと思います。
24時間相談ご予約受付中!刑事事件のご相談はアトム法律事務所まで
アトム法律事務所では24時間365日、弁護士相談のご予約受付中です。
警察から取り調べを受けた、逮捕されたなど警察介入事件では、初回30分無料で相談可能です。
刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。まずはお気軽にお問い合わせください。
ご連絡お待ちしています。


