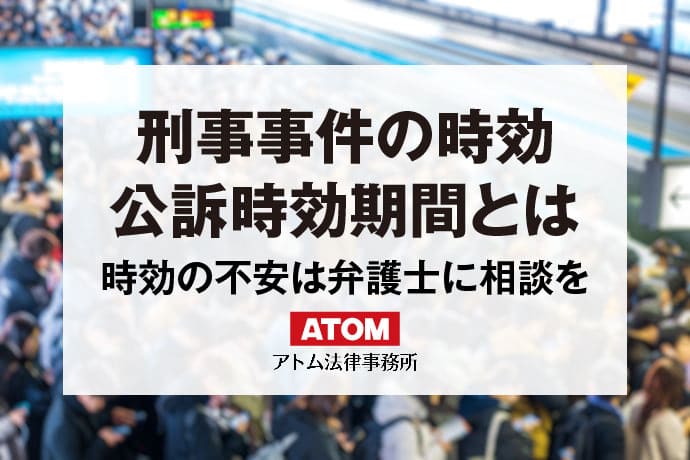
刑事事件を起こした場合、時効の完成が気になる方が多いと思います。ここでいう「時効」とは起訴されなくなる「公訴時効」のことです。
この記事では、公訴時効についてわかりやすく解説します。刑の時効、消滅時効、告訴期間についても詳しくご説明します。また、逮捕を回避する方法についても解説します。
この記事を読めば、時効に関する疑問や不安が解消するはずです。ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
刑事事件の公訴時効とは?
公訴時効とは?
公訴時効とは、犯罪発生後、法律の規定する一定期間が経過すると起訴されなくなる制度です。
時効が完成した事件について検察官が起訴しても、裁判所は免訴判決を言渡します(刑事訴訟法337条4号)。免訴判決とは、有罪か無罪か判断せず刑事裁判手続を打ち切る判決のことです。
公訴時効が存在する理由は、「時の経過によって処罰感情が薄くなる」「証拠の散逸により公正な裁判を実現できなくなる」など様々な観点から説明されます。
公訴時効が成立した有名な未解決事件として、三億円事件やグリコ森永事件などがあります。これらの事件について仮に犯人が見つかったとしても、刑事裁判にかけることはできません。
凶悪犯罪の公訴時効が廃止・延長された
公訴時効について、平成22年に大きな改正があり、殺人罪など凶悪犯罪の公訴時効が廃止・延長されました。
たとえば、殺人罪の公訴時効は、平成22年改正前は25年でしたが、改正後は公訴時効が撤廃されました。
この改正の背景には、被害者遺族を中心に、殺人等の人を死亡させた罪については時の経過による処罰感情の希薄化等の公訴時効制度の趣旨が当てはまらないという指摘がありました。こうした指摘を受け、法務省設置の法制審議会において、時効制度改正の必要性が検討された結果、平成22年の大幅な改正に至りました。
平成22年の改正内容は、施行日である平成22年4月27日以前に犯された犯罪であっても、その時点で公訴時効が完成していない事件には適用されます。
たとえば、平成15年9月1日に殺人事件を起こした場合、平成22年4月27日時点で25年経っていないので、改正後の法律が適用されます。つまり、どれだけ時間が経過しても殺人罪で訴追される可能性があるということです。
公訴時効を一覧表で解説!
現時点で規定されている公訴時効期間は、以下の表のとおりです。公訴時効は、人を死亡させたかどうか、法定刑の重さはどのくらいかという観点から規定されています。
人を死亡させた罪であって拘禁刑の刑に当たるもの(刑事訴訟法250条1項)
| 法定刑の上限 | 時効 | 具体例 |
|---|---|---|
| 死刑 | なし | 殺人罪、強盗殺人罪 |
| 無期の拘禁刑 | 30年 | 不同意わいせつ致死罪、不同意性交等致死罪 |
| 長期20年の拘禁刑 | 20年 | 傷害致死罪、危険運転致死罪 |
| その他 | 10年 | 業務上過失致死罪、自動車運転過失致死罪 |
人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるもの以外の罪(刑事訴訟法250条2項、3項)
| 法定刑の上限 | 時効 | 具体例 |
|---|---|---|
| 死刑 | 25年 | 現住建造物等放火罪 殺人未遂罪 |
| 無期の拘禁刑 | 20年 | 不同意わいせつ致傷罪 不同意性交等致傷罪 |
| 長期15年以上の拘禁刑 | 10年 | 強盗罪、傷害罪 |
| 長期15年以上の拘禁刑 | 15年 | 不同意性交等罪 監護者性交等罪 |
| 長期15年未満の拘禁刑 | 7年 | 窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪 盗品有償譲受け罪 |
| 長期15年未満の拘禁刑 | 12年 | 不同意わいせつ罪 監護者わいせつ罪 児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為に係るもの) |
| 長期10年未満の拘禁刑 | 5年 | 未成年者略取及び誘拐罪 横領罪 |
| 長期5年未満の拘禁刑 若しくは拘禁刑又は罰金 | 3年 | 暴行罪、侮辱罪 過失傷害罪、過失致死罪 名誉毀損罪、器物損壊罪 |
| 拘留又は科料 | 1年 | 軽犯罪法違反 |
※なお、次の犯罪については、重い方の刑を基準に上記の表に従って公訴時効が適用されます(刑事訴訟法251条)。
(1)2つ以上の主刑を併科する犯罪
例)盗品有償譲受け罪(刑法256条2項)の法定刑は「10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金」なので、重い方の「10年以下の拘禁刑」を基準に公訴時効は7年となる。
(2)2つ以上の主刑中にその1つを科すべき犯罪
例)殺人罪(刑法199条)の法定刑は、死刑または拘禁刑なので、重い方の「死刑」を基準にし公訴時効は適用されない。
関連記事
・痴漢事件の時効を弁護士が解説|刑事の時効と民事の時効の違いとは?
・窃盗罪の時効|弁護士が解説する公訴時効と示談
・詐欺の時効は何年?受け子、出し子をしてしまった…逮捕前に相談を
・暴行の時効は何年?刑事の時効と民事の時効とは?
公訴時効の起算点はいつ?
時効のカウントは「犯罪行為が終わった時」からスタートします(刑事訴訟法253条1項)。
公訴時効制度は被疑者の利益のために設けられたものであるため、初日を1日目としてカウントし、末日が休日でもその日が時効満了日になります(刑事訴訟法55条1項但書、同条3項ただし書)。
たとえば、2019年9月1日に窃盗行為をした場合、時効の起算日は2019年9月1日、時効期間は7年なので、2026年9月1日になった時点で公訴時効が完成します。
ただし、犯罪の種類によって起算点のとらえ方が異なります。
傷害致死罪などの結果的加重犯は、死亡結果が生じた時点から時効が進行します。
業務上過失致死罪も被害者死亡の時から時効が進行します(最高裁判所昭和63年2月29日決定)。
監禁罪などの継続犯は法益侵害の状態が解消した時点から進行します。
起算点はいつか、時効満了日はいつかといった問題に答えるには、法律の正しい知識が必要です。少しでも不安に思う方は、弁護士に直接相談することをおすすめします。
公訴時効は停止する
法律の規定する時効の停止事由があると、時効のカウントは一時停止します。これを時効の停止といいます。停止事由がなくなれば、再び時効が進行します。停止事由は以下のとおりです。
公訴時効の停止事由
- 公訴を提起された場合(刑事訴訟法254条1項)
→管轄違いの裁判、公訴棄却の裁判が確定すると再び時効が進行する。 - 共犯の1人が公訴を提起された場合(刑事訴訟法254条2項)
→当該事件の裁判が確定すると再び時効が進行する。 - 犯人が国外にいる場合(刑事訴訟法255条1項)
- 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかった場合(刑事訴訟法255条1項)
※なお、告訴状・告発状の提出、被害届の提出、逮捕・勾留のみでは公訴時効は停止しません。
公訴時効と似た制度
刑の時効
刑事事件に関係する時効には、「刑の時効」という制度もあります。
刑の時効とは、刑の言渡しを受けた者が、判決確定後、一定期間のその執行を受けないことにより刑罰権が消滅する制度です(刑法31条)。
刑の時効期間は以下の表のとおりです。
なお、日本の場合、刑の時効完成により刑が執行できないという事態は非常に少ないのが現状です。
刑の時効期間(刑法32条)
| 確定した刑 | 刑の時効期間 |
|---|---|
| 死刑 | なし |
| 無期拘禁刑 | 30年 |
| 10年以上の有期拘禁刑 | 20年 |
| 3年以上10年未満の拘禁刑 | 10年 |
| 3年未満の拘禁刑 | 5年 |
| 罰金 | 3年 |
| 拘留、科料、没収 | 1年 |
告訴期間
公訴時効と間違えやすいのが「告訴期間」です。
告訴は、被害者が、捜査機関に対し被害の事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を意味します。通常、告訴が受理されると捜査が進み、検察官に事件が送致された後、起訴・不起訴の判断がされるという流れになります。
告訴がないと起訴できない犯罪を「親告罪」といいます。親告罪は、告訴期間を経過すると告訴できなくなります。
親告罪の例としては、器物損壊罪、名誉毀損罪、侮辱罪の他、一定の親族間での窃盗罪や詐欺罪などが挙げられます。
親告罪の告訴期間は、「犯人を知った日から6か月」です(刑事訴訟法235条本文)。
なお、令和5年の時効制度改正によって、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)や不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の公訴時効が延長されました。
消滅時効(民事事件の時効)
刑事事件の被害者は、財産的損害や精神的損害など様々な被害を受けます。これらの損害を加害者に請求する権利は「不法行為に基づく損害賠償請求権」と呼ばれます。
損害賠償請求権は、法律に規定された一定期間を経過すると消滅します。これが「消滅時効」と呼ばれる制度です。
消滅時効期間が経過すると、被害者は損害賠償を請求することができなくなります。
以下に消滅時効期間をまとめましたので、参考にしてください。生命・身体に損害を与えたかどうかで消滅時効期間が異なるので注意してください。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)
| 起算点 | 消滅時効期間 |
|---|---|
| 損害及び加害者を知った時 | 3年 |
| 不法行為の時 | 20年 |
生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民法724条の2)
| 起算点 | 消滅時効期間 |
|---|---|
| 損害および加害者を知った時 | 5年 |
| 不法行為の時 | 20年 |
公訴時効が不安な方は弁護士に相談!
公訴時効が気になっている方へ
公訴時効が気になっている方へお伝えしたいのは、「時効完成を待つより、まずは弁護士に相談してみましょう」ということです。
逃げ隠れした後に逮捕された場合、悪質性が高いと評価されるおそれがあります。また、自分では時効が成立したと思っていても、別の罪名の容疑で逮捕されるケースもあります。
時効完成を待つのは決して得策ではありません。時効について少しでも不安に感じる方は、一人で悩まず弁護士にご相談ください。
示談により逮捕・勾留、起訴の回避が期待できる
弁護士に依頼すれば、示談成立により逮捕・勾留の回避が期待できます。早期の示談成立によって、刑事事件化を防げるケースもあります。
示談が成立すると不起訴になる可能性も高くなります。不起訴になれば前科はつきません。
示談書の中に示談金以外の損害賠償は支払わないという条項を入れることもできます。示談は刑事だけでなく、民事上の問題解決にもつながる有効な手段なのです。
アトム法律事務所の弁護士は、被害者の心情にも十分配慮しながら、効果的な示談を締結できるよう全力を尽くします。
自首に関する不安を解消できる
時効が気になっている方の中には、逮捕が不安で自首に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。そんな方は、ぜひ弁護士を頼ってください。
弁護士は、自首に同行して逮捕を回避するよう捜査機関を説得します。ご本人がいくら「逃亡しません」と言っても、認めてもらうのは中々難しいものです。しかし、弁護士が具体的な根拠を示すことで、逃亡しないという主張に説得力を持たせることができます。
アトム法律事務所の弁護士は、「自首すべきかどうか」「自首するとして取調べでどのように話せばよいか」といった疑問に対し、事案の個別性をふまえて丁寧にお答えします。
自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。時効完成を待って不安な日々を過ごすより、まずは一度弁護士にご相談ください。
関連記事


