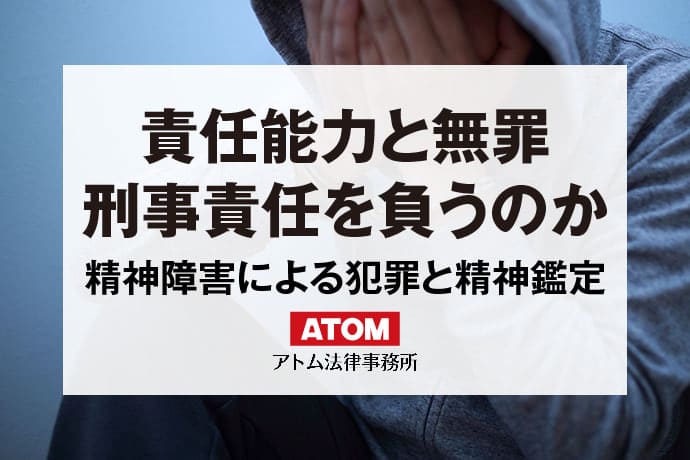
刑事事件では、被告人に刑事責任を問えないため、無罪となるケースがあります。無罪となる理由は、刑法が「善悪の判断ができず、自分をコントロールできない人に、責任(刑罰)は負わせられない」と定めているからです。
刑法39条には「心神喪失者の行為は、罰しない」という規定があります。これがいわゆる「責任能力がないと無罪」になる法的根拠ですが、具体的にどのような基準で判断されているのか、正確に知っている人は多くありません。
この記事では、刑事事件で責任能力がないと無罪になる理由、「無罪となる心神喪失」と「刑が減軽される心神耗弱」の違いなどを分かりやすく解説します。
責任能力がないと無罪になるのはなぜなのか
精神の障害などで責任能力がないと判断された場合には、罪を犯しても無罪になります。では、なぜ責任能力がないと無罪になるのでしょうか。それは、犯罪が成立するための要件を知ることで理解できます。
犯罪が成立するための3つの要件
刑法において犯罪が成立するためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。
犯罪が成立するための3つの要件
- 構成要件該当性(やったこと) 「人を刺した」「物を盗んだ」など、法律が規定する犯罪行為の形に当てはまるか
- 違法性(悪さ) 正当防衛や緊急避難など、やむを得ない事情がなかったか
- 責任(有責性) 責任があるか(責められない事情がないか)
ある行為が犯罪かどうかの判定は、「構成要件該当性→違法性→責任」の順で行われます。
そのため、構成要件該当性や違法性が認められても、責任がないと判断されて犯罪が成立しないことがあるのです。刑事事件では、責任があることが犯罪成立の前提条件となっています。
責任があるかどうかは「責任能力」で判断される
犯罪が成立するためには、責任(有責性)が必要です。その責任は、行為時に「責任能力」があったかどうかで判断されることになります。
責任能力とは、行為者が自分の行為の是非・善悪を判断し、その判断に従って行動を制御する能力をいいます。単に病気や精神障害を持っているか否かではなく、以下の2つの能力が揃っている状態を指します。
責任能力の定義
- 事理弁識能力
自分のしたことが「良いことか悪いことか」を判断する能力 - 行動制御能力
その判断に従って、自分自身の衝動や行動をコントロールする能力
このどちらか一方でも欠けていれば、「責任能力がない」または「著しく低い」と判断される傾向にあります。
たとえば、誰かに無理やり腕を掴まれて他人を殴らされた場合、その人に「殴った責任」を問えないのと同様に、病気による幻覚や妄想に支配され、自分を全くコントロールできない状態で起きた行為については、「本人を非難して処罰することはできない(責任を問えない)」と考えます。
実務で重要なのは「程度」と「因果関係」
実務上、「どちらがどの程度欠けているか」「犯行時にその障害がどれほど影響したか」を総合評価され、責任能力があるか判断されます。
「欠けている」と言っても程度差があり、さらに重要なのが、以下の要素です。
- その能力低下が犯行時にどの程度影響したのか
- 障害と犯行の結びつき(因果関係)
たとえば、統合失調症を患っていても、普段は安定していて、犯行が計画的で合理的なら責任能力ありとされ得ます。一方、衝動性が強く犯行が突発的で、病的要因が支配しているなら心身喪失になり得るということです。
責任能力の有無はどのように判断されるのか
刑事事件では「加害者が当時、責任能力があったのかどうか」が争点になることがあります。責任能力の有無を判断するために行われるのが、精神科医などによる「精神鑑定」です。
精神鑑定には事件が起訴される前に行われる「起訴前鑑定」と、起訴された後に行われる「起訴後鑑定(公判鑑定)」の2種類があります。
起訴前鑑定
起訴前鑑定は、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断する目的で行われます。(1)簡易鑑定と(2)本鑑定の2パターンがあります。
簡易鑑定は、通常の勾留期間中に実施される鑑定です。勾留期間とは、逮捕に引き続く身体拘束期間で、検察官が起訴・不起訴を決定するまでの最長20日間をいいます。
一方の本鑑定は、通常の勾留期間とは別に鑑定留置の期間を設けて、およそ2か月かけて実施される鑑定です。
鑑定結果をもとにして、検察官が被疑者に対して刑事責任能力があるかどうかを判断します。刑事責任能力があると判断され、証拠が十分にそろうと起訴される可能性は高まるでしょう。
一方で刑事責任能力がないとされた場合には不起訴となります。もっとも、令和4年版犯罪白書によると、心神喪失による不起訴の割合は0.3%であり、まれなケースと考えておきましょう。
起訴後鑑定(公判鑑定)
起訴後鑑定(公判鑑定)は、裁判官が被告人の刑事責任能力の有無を認定するために用いられます。
検察に起訴されてから公判が開始されるまでには公判前整理手続きが行われます。
公判前整理手続きの目的は、争点および証拠の整理です。被告人側から責任能力の問題が提起された場合に、裁判所の判断で起訴後鑑定(公判鑑定)が認められます。
また、裁判員裁判では審理期間も限定されており、適切な時期に鑑定結果を入手しなくてはなりません。
そこで検察官、被告人もしくは弁護人の請求により又は職権によって、公判前整理手続きの段階で鑑定を行うことが認められています。規定した裁判員法に基づいて50条鑑定ともいわれる方法です。
精神鑑定の実施時期による違い
| 起訴前鑑定 | 起訴後鑑定 | |
|---|---|---|
| 簡易鑑定 | あり | なし |
| 実施の決定者 | 検察官 | 裁判官 |
| 結果の認定者 | 検察官 | 裁判官 |
「心神喪失(無罪)」と「心神耗弱(減刑)」の境界線
鑑定の結果、責任能力の程度によって判決は「心神喪失(無罪)」と「心神耗弱(減刑)」の大きく2つに分かれます。
心神喪失者(無罪)
心神喪失とは、統合失調症などの重い精神障害により、善悪の判断能力や行動をコントロールする能力が全く失われている状態を指します。
この場合、自分の行為を悪いことだと認識できなかったり、悪いと分かっていても衝動を抑えられなかったりするため、その人を非難することはできません。 そのため、たとえ殺人などの重大な事件を起こしたとしても、無罪の判決が下されます。
心神耗弱者
心神耗弱とは、心神喪失の状態には至らないものの、精神の障害によって、善悪の判断能力や行動をコントロールする能力が著しく低くなっている状態を指します。
能力が全くないわけではないため、責任を問うことはできますが、その能力が健康な人と比べて著しく低い状態であったことを考慮し、法律によって必ず刑が軽くなります(これを「刑の減軽」と言います)。
心神喪失者と心神喪失者の違い
| 心神喪失者 | 心神耗弱者 | |
|---|---|---|
| 意味 | 善悪の判断ができない状態 | 判断力や行動抑制力が著しく低下した状態 |
| 刑事責任 | なし(処罰されない) | 刑が減軽される |
心神喪失者に無罪判決が出た後はどうなる?
「責任能力がないため無罪」と聞くと、無罪判決後すぐに自由の身になると感じる方もいるかもしれません。しかし実際は、「無罪判決=即時釈放」とはなりません。特に重大事件では、医療観察法に基づく厳格な対応が取られます。
無罪判決後も「医療観察法」に基づく手続きが行われる
放火、不同意わいせつ、殺人などの事件を起こし、重大な精神疾患が認定された場合、再発や再犯を防ぐために「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」【通称:医療観察法】に基づく措置が取られます。
無罪判決や不起訴処分が確定した後は、検察官が地方裁判所に対し「審判」の申し立てを行います。審判では、裁判官と精神科医の合議体が、精神鑑定や生活環境調査などをもとに、今後の処遇を決定します。
審判の結果、医療が必要と判断されると、以下のいずれかの措置が取られます。
- 指定医療機関への入院(多くは閉鎖病棟での強制入院)
- 通院治療
医療措置を必要としないと判断された場合は、入院・通院のいずれも不要となることもありますが、重大事件の場合はほとんどが入院措置となります。
つまり、無罪判決が出たからといって、すぐに何の制約もなく社会に戻るわけではなく、社会の安全にも配慮しながら、専門家のサポートのもとで社会復帰を目指す仕組みが整えられているのです。
入院・通院の期間と社会復帰
入院措置がとられた場合でも、6か月ごとに審判が行われ、退院の可否や入院継続の必要性が判断されます。
退院後も原則として3年間は精神科への通院が義務付けられます。審判で不要と判断されない限り、通院は継続されます。病状が悪化した場合は再入院となることもあります。
責任能力と犯罪の成立に関するよくある質問
Q.泥酔時は心神耗弱者になる?
飲酒によって普段よりも攻撃的になったり、衝動的な行動を起こしてしまうことがあります。なかには何をしたか記憶がないという方もいるほどです。
泥酔時は心神耗弱状態にあったものとして刑の減軽を主張するケースも多くあります。
しかし、アルコールの影響等により心神喪失・心神耗弱に陥って犯罪行為をしたとしても、原因となる物質の摂取時に責任能力があったのであれば完全な刑事責任を問えるという「原因において自由な行為」という考え方のもと、刑事責任能力は完全にあったと判断されることもあります。
関連記事
・酔っ払いが事件を起こした時の責任能力は?逮捕後の対応で不起訴も!
Q.覚醒剤などの「薬物」を使用して幻覚が見えていた場合はどうなりますか?
多くのケースで「有罪(完全責任能力あり)」と判断されます。自ら進んで違法薬物を使用した結果、幻覚や妄想に襲われて事件を起こした場合は、飲酒と同様に、原則として責任能力が認められます。
薬物の影響で精神障害が慢性化している場合などは慎重に判断されますが、「薬をやっていたから許される」という単純な話ではありません。
Q.14歳未満の未成年者も責任能力がないって本当?
刑法第41条では、「14歳に満たないものの行為は罰しない」と定められています。そのため、14歳未満の少年(触法少年)による行為は、責任能力がないため、犯罪とはなりません。
14歳未満が犯した事件は、物事の良い・悪いを判断する能力や、その判断に基づいて行動を抑制する能力が一般的に未熟であることが考慮されます。
年少者特有の精神状況と、成長過程にあり価値観や行動が変化しやすい(可塑性)ことに鑑み、政策的に不処罰としているのです。
ただし、児童相談所へ送られて処遇が判断され、場合によっては家庭裁判所へと送致される可能性はあります。家庭裁判所に送致されると、少年審判が行われ、最適な処分が決定します。
関連記事
・触法少年とは?逮捕・処分されることはない?定義・年齢を弁護士が解説
Q.「精神疾患がある=無罪」ですか?
精神疾患がある=すべて無罪、というわけではありません。刑事責任が問えるかどうかは、その人の「責任能力」があるかによって判断されます。
たとえば軽度のうつ病や不安障害など、思考や判断の能力が著しく低下していない場合は、通常と同じように起訴され、処罰の対象となります。
刑事責任能力が争われた裁判例
知的障害、人格障害、神経症性障害、発達障害、その他統合失調症や気分障害など様々な精神障害がありますが、病気自体が罪を免れる理由にはなりません。
精神障害があることを理由に無罪とされるのではなく、精神障害に起因して、事件当時に刑事責任能力がないと認定されたときに無罪とされます。
最後に、これまでに刑事責任能力の有無が争点とされた刑事事件の判例の一部を抜粋します。
心神喪失で無罪判決となった判例(傷害致死)
この事件は、生後1か月の実子を床に投げつけるなど頭部に衝撃を与える暴行を加え、急性硬膜下血腫により死亡させた傷害致死の事案でした。弁護側は、被告人が統合失調症を発症しており、幻聴や被影響妄想等に支配されていたとして心神喪失状態を主張しました。
起訴後の精神鑑定の結果を踏まえ、裁判所は、本件行為をした時点では統合失調症による幻聴等の圧倒的な影響下にあり、正常な精神作用が働く余地が残されていなかったものとし、心神喪失により無罪と言い渡しました。(傷害致死被告事件(横浜地方裁判所 令和元年(わ)第1231号))
心神喪失で無罪判決となった事例(常習累犯窃盗)
本件は、常習的に窃盗を繰り返していた被告人が再び複数回の窃盗を行った事件でした。弁護側は、被告人が犯行当時心神喪失状態にあり、現在も訴訟能力を欠いていると主張しました。
裁判所は精神鑑定を踏まえ、被告人が血管性認知症と慢性の統合失調症を患っており、記憶保持の困難などから訴訟能力がなく、回復の見込みもないと認定しました。また、犯行時には行動を制御した上で、犯行を抑止することができなかったとの合理的な疑いを払拭することはできないとして心神喪失と判断しました。
これらを理由に、手続停止ではなく実体判断による迅速な解決が被告人に最も有利とし、無罪判決を言い渡しました。(常習累犯窃盗被告事件(神戸地方裁判所 令和元年(わ)第290号))
心神喪失ではなく心神耗弱となった判例
被告人が親族の居宅に火を点け、居宅の一部を焼損させた事件でした。被告人は犯行当時アルコール離脱せん妄状態にあったとして、弁護側は心神喪失状態による無罪を主張しました。裁判においては精神鑑定の結果などを元に、犯行当時の行動には合理性も認められることから、あくまで心神耗弱状態であったと認定し、被害者側が被告人を許している事情も考慮して懲役3年執行猶予4年を言い渡したのです。(現住建造物等放火被告事件(横浜地方裁判所 令和3年(わ)第1221号))
心神喪失や心神耗弱状態ではなく有罪となった判例
本屋にて販売価格合計2万2,572円の書籍等を窃取した事件でした。弁護側は解離性同一障害に罹患しており、本件行為を別の人格が行ったものと主張し、本人には故意や不法領得の意思がないこと、また心神喪失の状態のため無罪と訴えました。
精神鑑定の結果や本件当時の言動等より、被告人は解離性同一障害に罹患していないとし、裁判所は心神喪失ならびに心神耗弱状態はないとして懲役1年執行猶予3年を言い渡しました。(窃盗被告事件(静岡地方裁判所 令和2年(わ)第286号))
まとめ
本記事では、責任能力と無罪の仕組みについて解説しました。
責任能力とは、行為者が自分の行為の是非・善悪を判断し、その判断に従って行動を制御する能力をいいます。心神喪失(責任能力が全くない状態)と判断されると無罪に、心神耗弱(能力が著しく低い状態)と判断されると刑が軽くなります。
しかし、これは決して犯罪を容認するものではありません。
裁判では、専門家による精神鑑定を通じて「本当に責任能力がなかったのか」が厳しくチェックされます。そして万が一、心神喪失で無罪となった場合でも、その後の社会復帰は「医療観察法」によって厳重に管理されます。
法律は「処罰」できないケースに対し、「治療と管理」という別の枠組みで社会の安全を守っているのです。



