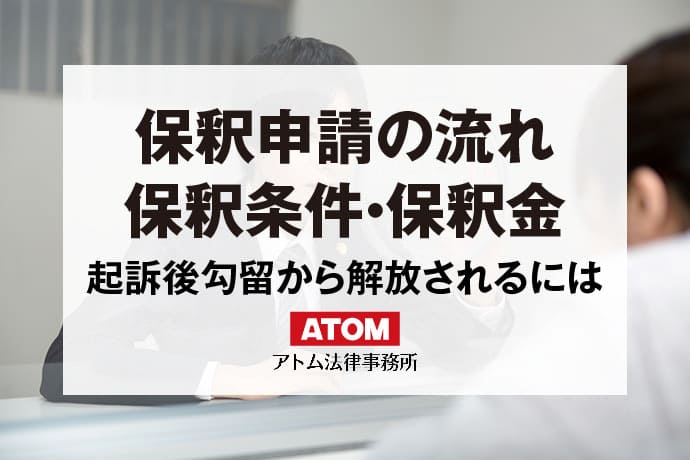
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
被疑者が逮捕・勾留されている事件で起訴された後は、被告人として勾留が続くことになります。被告人の勾留は起訴から刑事裁判が開かれるまで原則2か月程度続きますが、事件の内容によっては年単位で勾留され続ける可能性もあるでしょう。
このような被告人勾留と呼ばれる長期の身柄拘束から解放されるためには「保釈申請」を行う必要があります。保釈は起訴後に申請できますが、一定の条件をクリアしたうえで保釈金の納付が必要です。
この記事では、どのような場合に保釈が認められるのか、申請から保釈金を納付する手続きの流れ、保釈申請が却下された場合の対処法などを解説します。釈放までにかかる流れをあらかじめ知っておくと、いざという時に早期の釈放を目指すことができるでしょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
保釈申請(保釈請求)とは?
保釈とはそもそもどのような制度なのか、保釈申請が認められる条件、保釈申請できる人などについて解説します。
保釈は起訴後の勾留から解放される制度
保釈とは、起訴後の被告人の段階で行われる「被告人勾留」という身柄拘束から解放されるために、一定金額の保釈金を預けることを条件に釈放してもらう手続きです。
通常、逮捕・勾留によって身柄を拘束されていた被疑者が起訴されると、被告人として勾留が続くことになります。しかし、保釈が認められれば、刑事裁判が終わるまでは一時的に元の生活に近い状態に戻ることができるのです。
保釈申請は、起訴された後ならどのタイミングでもできます。ただし、裁判官の許可が必要であり、保釈金を納めなければなりません。
逮捕後、勾留が続いている場合でも、起訴後には「保釈」という釈放のチャンスがあるため、身柄解放を目指す場合は、保釈申請を検討することが重要です。
保釈の種類は3つ
保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3種類があります。
保釈の種類
- 権利保釈
原則認められる保釈のこと。ただし、重い罪を犯したり重罪の前科や常習性がある・証拠隠滅のおそれがある等の例外に該当する場合は認められない。 - 裁量保釈
権利保釈以外の場合に裁判官が認める保釈のこと。 - 義務的保釈
勾留が不当に長い場合に許可しなければならない保釈のこと。
保釈申請すると、まず権利保釈できるケースか裁判所に検討されます。権利保釈が認められないケースであれば、裁量保釈できるケースか検討されることになるでしょう。
さらに、権利保釈も裁量保釈も認められなければ、義務的保釈が検討されます。しかし、義務的保釈が認められる可能性は非常に低いです。
3つの保釈の違い
| 権利保釈 | 裁量保釈 | 義務的保釈 | |
|---|---|---|---|
| 原則 | 認められる | 認められない | 認められない |
| 例外 | ・罪が重い ・重罪の前科や常習性がある ・証拠隠滅のおそれがある など | 裁判官の裁量 | 勾留が不当に長い |
保釈申請が許可されるための条件
保釈申請が許可されるためには、 「死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑」にあたる重罪でないこと、法定刑の上限が10年を超える罪の前科がないこと、常習性がないこと、証拠隠滅やお礼参りのおそれがないこと、氏名・住所が明らかなことが条件です。
なお、ここでいう「お礼参り」とは、被害者や証人に報復行為をすることを指します。具体的には、被害者や証人に対する脅迫・暴力・嫌がらせなどが該当します。
上記の条件に当てはまれば、必要的保釈であるとして権利保釈は原則認められます。上記の条件に当てはまらなくても、被告人が病気で治療が必要であったり、仕事上どうしても被告人が必要であったりして裁判官が職権で釈放を認める場合(裁量保釈)や、勾留が不当に長期化し認めなければならない場合(義務的保釈)があります。
権利保釈が認められる条件
| 認められやすい | 認められにくい | |
|---|---|---|
| 犯罪・前科 | 軽い | 重い |
| 報復・証拠隠滅 | 危険なし | 危険あり |
| 氏名・住所 | 明らか | 不明 |
保釈申請できる人
保釈申請は、誰でもできるわけではありません。保釈申請ができるのは、被告人本人・その弁護人・法定代理人(未成年の場合の両親等)・保佐人(判断能力が不十分な人の権利を守るために、慎重な判断が必要な場面で判断や同意等する人)・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限られます(刑事訴訟法88条1項)。
保釈申請は、裁判所または裁判官に対して「保釈請求書」という書面を提出して行います。本人やご家族も保釈申請できるとはいえ、実際は自力で保釈請求書を作成し提出することは難しく、弁護人が行うのが通常です。
なかには国選弁護人が保釈請求をしてくれないというケースもあるため、心配な場合は確認してみましょう。
保釈申請を弁護士が行うメリット
| 弁護士 | 本人・家族 | |
|---|---|---|
| 申請 | できる | できる |
| 手続き | スムーズ | 難しい |
【注意】逮捕中は保釈申請できない
被疑者として逮捕・勾留されており、事件が捜査中の起訴前の段階では保釈申請できません。保釈は、検察官に起訴されてから初めて請求できるようになる制度だからです。
逮捕・勾留中は保釈申請ができないため、弁護士に依頼して勾留されないように意見書を出してもらったり、勾留された場合は「準抗告」という不服申し立ての制度を利用して釈放を目指すことになります。
ご家族が逮捕・勾留による身柄拘束を受けており、一刻も早く解放してあげたい場合は、弁護士相談がおすすめです。
起訴後の保釈申請から保釈までの流れと手続き
起訴後に保釈申請してから実際に保釈されるまでの流れは以下の通りです。

流れに沿って、手続きについて詳しくみていきましょう。
(1)起訴後に保釈申請を行う
保釈申請は、裁判所に「保釈請求書」を提出して行います。
保釈請求書は、裁判所の刑事部を宛先にして、事件名や被告人を特定する事項(住所・氏名・生年月日)のほか、保釈を請求するという「請求の趣旨」と、保釈が認められるべきという「請求の理由」を記載し、申請する申立人と被告人との関係を明らかにして署名押印します。
また、弁護人を除く被告人以外の人が申立てる場合は、申立て権者の証明のため「戸籍謄本」が必要です。添付資料がある場合は、保釈請求書とあわせて提出します。
なお、保釈申請は口頭による申請も可能とされていますが、通常は書面を提出して行います(刑事訴訟法規則296条)。
保釈申請に必要な書類は?
保釈申請には、保釈請求書に加えて、身元引受人の「身元引受書」や、釈放された後に住む場所の「住民票」、家族や友人が被告人を監督することを記載した「上申書」、すでに示談が成立している場合は「示談書の写し」などの書類が必要です。
ご家族が保釈による釈放を望む旨を記載した「嘆願書」も提出することもあります。
これらの書類は、保釈による釈放後、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示すのに有効です。
(2)裁判官面接・検察官意見が行われる
弁護士などから保釈が申請されると、保釈許可の決定の前に裁判官が検察官の意見を求めます。検察官は、保釈を認めてよいという「相当」、保釈すべきでないという「不相当」、裁判官に任せるという「しかるべく」の3つのどれかを答えますが、通常は不相当とするでしょう。不相当の場合、理由も書面で添付されます。
弁護人も希望する場合は、保釈について担当裁判官と面接することができます。上記の検察官意見を閲覧できるのは通常、保釈の判断後なので、面接前に検察官の意見を知ることができません。なお、面接で裁判官から保釈金額に関する話がでれば、保釈される可能性が高いといわれています。
(3)保釈許可決定がなされる
裁判官は、検察官意見、弁護人面接を経て保釈を認めるかどうか決定します。その際は、保釈金の金額に加え、釈放後の住居や旅行の制限などの条件も決めて付されます。裁判所にもよっても異なりますが、保釈請求当日に保釈されることは少なく、翌日や2~3日後になることもあるでしょう。
保釈が不許可になった場合は「準抗告」により不服を申し立てることが可能です。逆に、保釈が許可された場合でも、検察側によって不服を申し立てられる事があるので油断できません。
準抗告では、担当裁判官以外の3人の裁判官に判断されます。準抗告で保釈不許可決定が覆れば保釈金を払って釈放されますが、保釈許可決定が覆ると釈放されません。
(4)保釈金の納付を行う
保釈金は、現金で納付するのが原則です。ご家族が自ら裁判所に出向いて納める必要はなく、弁護人がご家族から預った保釈金を裁判所に納付するのが通常でしょう。保釈金を納付する際、保釈金の返還先口座を記入した書面も提出し、被告人が逃亡等せず裁判を終えると、保釈金は指定口座に全額還付されます。
なお、最近は、事前登録することで、保釈金を銀行やネットバンキングで電子納付できるようになりました。刑事裁判所の管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による(刑事訴訟法第2条)とされ、遠方の裁判所になることもあるので、電子納付によってスピード対応が可能となったのです。
保釈金の相場はいくら?
芸能人や政治家の事件では、保釈金が数千万から数億円になり話題になることもあります。しかし、一般的な刑事事件の保釈金の金額は、150万円から300万円程度が相場です。
ただし、犯罪の事情によって保釈金の額は大きく変わります。たとえば、同じ窃盗事件でも万引きかひったくりかで金額は異なりますし、大麻所持の場合は大麻の量や営利目的であったかどうかなどの事情が影響するのです。
保釈金の額は、犯罪の性質や事情、証拠、被告人の性格や資産を考慮して、被告人の出頭を保証できる金額とされています(刑事訴訟法93条2項)。具体的には、刑罰が重く犯情も悪い場合や、事件を争っている場合、高収入の場合等は高額になりやすく、初犯の場合は再犯に比べ低額になりやすいです。
保釈金の相場
| 一般人 | 有名人・政治家など | |
|---|---|---|
| 必要な保釈金 | 高くない | 高い |
| 保釈金の相場 | 150~300万円 | 数千万~数億円 |
※一般人でも刑罰が重いと高額な保釈金が必要な場合あり
より具体的な保釈金相場については関連記事『保釈金の相場はいくら?返ってくる?保釈金が用意できない時の対応』が参考になりますので、あわせてご覧ください。
(5)被告人が釈放される
保釈許可の決定を受けて弁護人が裁判所の出納課に保釈金を納付し、領収印が押印された書類を担当部署に提出すると、裁判所から検察庁に連絡が行き、その日のうちに被告人は釈放されます。ケースにもよりますが、保釈金を納付してから2~3時間はかかることが多いようです。
保釈許可の決定が出る時間帯は裁判官の事件量等によって変わりますが、通常は13時以降になります。当日中の釈放を希望する場合は、事前に保釈金を弁護人に預けておくことをおすすめします。
なお、釈放時に被告人の私物は紙袋で渡されますが、量が多いと一人で運べないので、ご家族などが迎えに行かれると安心です。
保釈申請が却下された・保釈金が足りないときの対処法
保釈申請通らない・却下されたなら不服申立て
保釈申請が却下され、不許可になった場合は「準抗告」という手続きで不服を申し立てることができます。準抗告は、裁判官も間違った判断をすることもあるので、別の裁判官によってその判断の是非を問うものです。保釈の場合は、保釈請求を却下した裁判官以外の3人の裁判官によって見直されます。
準抗告が認められ、当初保釈請求を却下した裁判官の判断が誤りだったとされると、保釈請求が認められます。また、一度保釈が認められなかった場合でも、裁判で証拠が全部出された後ならば証拠隠滅のおそれがなくなった等として、後日請求し直すことで、保釈が認められる場合もあるでしょう。
保釈金が足りないなら日本保釈支援協会の利用
保釈金が足りないからといって、保釈をあきらめる必要はありません。保釈金の代わりに保証書を納める方法もありますが、裁判所の代納許可が必要で積極的には認められていないのが実情です。
そのような場合は、保釈保証金の支援を目的とする有志の団体である「日本保釈支援協会」を利用することもできます。
日本保釈支援協会は、被告人以外の申請によって罪名や前科が審査され、500万円を上限に保釈金を立替えてくれます。裁判が終わり保釈金が戻れば保釈金を返金します。手数料(立替手数料+事務手数料)は150万円で5万円程度です。
保釈申請に関するよくある質問
保釈申請が通る確率は?
令和4年版の犯罪白書「6 勾留と保釈」によれば、令和3年度における保釈率は地方裁判所で31.4%、簡易裁判所で17.6%となっています。
平成25年度における保釈率は地方裁判所で約20%であったことから、保釈率は昔に比べると増加傾向にあります。しかし、保釈が認められるのは3人に1人未満と、決して容易ではありません。
保釈申請は身元引受人が絶対に必要?
保釈申請において身元引受人は絶対必要な条件ではありません。ただし、身元引受人がいなければ、保釈申請は認められないのが通常です。
保釈申請を認めてもらう可能性を高めるためには、身元引受人になってくれる人を見つけるべきでしょう。
一般的に、身元引受人は家族や親族にお願いすることが多いです。もっとも、保釈後に被告人を監督でき、保釈の条件を守らせられる人であれば、職場の上司や知り合いでも身元引受人になれます。
身元引受人の具体的な役割や身元引受人になれる人の条件については『身元引受人の条件や必要な場面とは?逮捕されたら家族ができること』の記事をご覧ください。
保釈申請は即日認められる?保釈決定までの日数
保釈申請をしてから審査を経て保釈の決定が出るまでにかかる日数は2~3営業日、長くても1週間というのが通常です。
保釈決定が出ると、すぐに保釈金を納付すれば、その数時間後には釈放されるため、釈放されるまでに要する日数も同程度と考えて構いません。
保釈金の納付時期にリミットはないので、保釈金の準備に時間がかかっても、保釈の決定が取り消されることはありません。
早く保釈で釈放されたい場合は、原則裁判所の営業時間である17時~17時半頃までに納付します。保釈金が納付されれば、どんなに夜遅くても釈放されなければなりません。
保釈後は自由に生活できる?保釈中の注意点
保釈されると、通勤や通学など、基本的には自由に日常生活を送ることができます。家族と過ごせる上、弁護人とも密に面談して裁判に備えられるので、保釈には非常に大きなメリットがあります。
ただし、裁判前の身なので、裁判所に指定された条件に違反しないという一定の制約はあります。
保釈中の注意点
保釈中は、指定された条件に違反しないよう注意して過ごさなければなりません。
たとえば、裁判所が指定した制限住居で生活すること、裁判所から呼び出されたら出頭すること、逃亡や証拠隠滅をしたり関係者と接触しないこと、海外旅行または3日以上の旅行は事前に裁判所の許可を受けることなどです。
これらに違反すると保釈が取り消され保釈金も取り上げられるので注意してください。
保釈申請は弁護士に依頼するべき?
保釈申請は弁護士でなくてもできますが、保釈してほしい場合は弁護人に依頼することをおすすめします。
保釈は、保釈金さえ払えば認められるものではありません。保釈金は逃亡や証拠隠滅しないことを担保するものでしかないので、保釈申請では逃亡等をしないことを裁判官に理解してもらう必要があります。
具体的には、保釈が許可されるかを判断する事情となる、刑罰や犯行態様、前科、有罪の可能性、被告人の財産や就労状況、身元引受人の有無等を踏まえ、弁護人を通して、犯情の説明をしたり、身元引受人のサポート体制を整えるなどして、証拠隠滅やお礼参りのおそれがないことを説明することが重要です。
起訴や保釈申請でお困りの場合は弁護士に相談
起訴後の保釈を検討されている場合は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
保釈が認められる可能性は一般的に低いとはいえ、弁護士であれば少しでも保釈の可能性が高まるよう適切に手続きを進めることができます。また、刑事事件に慣れた弁護士が対応するので、保釈のスケジュール感を熟知しており、保釈申請もスムーズに行えるでしょう。
アトムの解決事例(1)
家宅捜索で覚醒剤の所持が発覚し、その後の尿検査などで使用も露見した。覚醒剤取締法違反の事案。
弁護活動の成果
起訴後に受任。即座に保釈請求を行ったところ認容され、拘置所からの早期解放を実現。また、薬物依存症の治療を開始したことなどを十分に伝え、執行猶予付き判決を得た。
アトムの解決事例(2)
工事現場から複数回にわたり、物品を盗んだ。窃盗と建造物侵入等の容疑で逮捕起訴され、後に覚醒剤の使用も発覚。
弁護活動の成果
国選弁護人から切り替える形で受任。被害の弁済を行い、薬物依存症の治療も開始した。保釈が認容されたほか、執行猶予判決により実刑を回避した。
なお、起訴される前であれば、不起訴を獲得できる可能性も残っています。不起訴になれば刑罰を受けることも前科が付くこともありません。弁護士が対応にあたれば、そもそも不起訴の獲得を目指して行動することができるでしょう。
いずれにせよ、刑事事件では弁護士の存在が欠かせません。アトム法律事務所では、警察が介入している事件では無料相談を実施しています。刑事事件を起こしたら、気軽に弁護士にご相談ください。
無料相談の予約受付は24時間いつでも対応中です。今すぐつながる窓口をご利用ください。
アトムを選んだお客様の声
保釈を目指すなら、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。
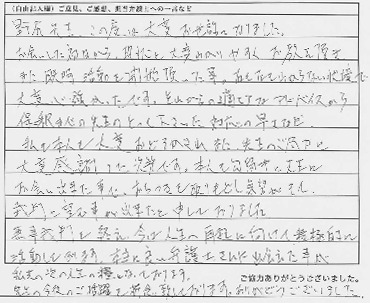
(抜粋)お会いした初回から、状況を大変わかりやすくお教え頂き、また、即時活動を開始頂いた事、右も左もわからない状況大変心強かったです。それからの適切なアドバイスから、保釈までの先生のとってくださった対応の早さなど、私も本人も大変おどろかされ、また、先生のご尽力に大変感謝した次第です。落ち着きもとりもどし希望がもて、裁判に望む事が出来たと申しておりました。



