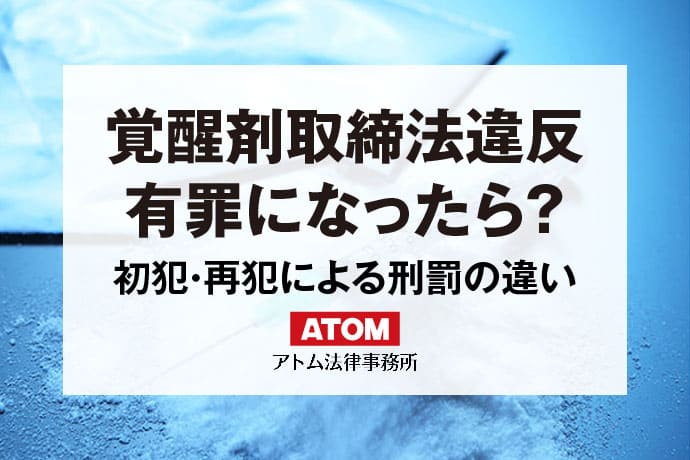
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
覚醒剤取締法違反で有罪となる人は後を絶ちません。覚醒剤は非常に依存性が高いことから、何度も懲役刑を言い渡される人も多いです。
覚醒剤事件で執行猶予を得られるのは、主に初犯で所持量が少ない場合です。2回目(再犯)の場合は実刑となり、刑務所に行く可能性が高まりますが、前科からの期間や特別な事情によっては例外もあります。
覚醒剤取締法違反で有罪になった場合の懲役・刑期は、使用・所持で「10年以下の懲役」です。
初犯であれば懲役1年6月・執行猶予3年が相場ですが、再犯になると実刑(懲役2年前後)となる可能性が高く、回を重ねるごとに刑期は6月ずつ加算されていくことが多いです。
この記事では、覚醒剤で警察に捜査された方や、ご家族が覚醒剤で逮捕されてしまった方に向けて、覚醒剤取締法違反の刑罰や初犯・再犯による量刑の違いなどについて解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
覚醒剤取締法違反の刑罰は?
覚醒剤取締法では、「使用」「所持・譲渡・譲受」「輸出入・製造」の行為が処罰対象として規定されています。実務上は、使用と所持で処罰されることが多いです。
覚醒剤使用の刑罰は?
覚醒剤使用の刑罰は、「10年以下の懲役」です。
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤取締法41条の3
覚醒剤取締法上の「使用」とは、自分自身で注射する方法が典型的ですが、炙って吸引する行為も使用に当たります。
また、他人に注射することも、他人に注射してもらうことも使用に該当する可能性があります。
覚醒剤所持・譲渡・譲受の刑罰は?
覚醒剤所持や覚醒剤譲渡・譲受の刑罰は、「10年以下の懲役」です。
覚醒剤を売買してお金を稼ぐ営利目的で所持・譲渡などすると、「1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」が科せられます。
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤取締法41条の2
覚醒剤取締法上の「所持」とは、物を管理できる状態にあることです。覚醒剤を携帯している場合はもちろん、自宅や自動車に隠している場合や他人に預けている場合も所持に当たる可能性があります。
覚醒剤輸入・輸出・製造の刑罰は?
覚醒剤を、日本もしくは外国に輸入し、日本もしくは外国から輸出し、または製造した場合、「1年以上の有期懲役」に処せられます。
有期懲役は原則として20年が上限であることから、1年以上20年以下の範囲で懲役刑となります。
営利目的で輸入、輸出、または製造した場合は、「無期もしくは3年以上の懲役」に処せられます。情状によっては「無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」となる場合もあります。
覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(略)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤取締法41条
近年では、航空機による覚醒剤をはじめとした違法薬物の密輸入が増えています。
海外からの違法薬物の密輸に関わった場合、覚醒剤取締法上の輸入罪や関税法違反の罪に問われるおそれがあります。甘い気持ちで誘いに乗らないよう十分注意しましょう。
覚醒剤の態様と刑罰
| 営利目的 | 非営利目的 | |
|---|---|---|
| 所持・使用等 | 1年以上の懲役 | 10年以下の懲役 |
| 製造・輸出入 | 無期若しくは3年以上の懲役 | 1年以上の懲役 |
※営利目的の刑罰は情状により罰金併科
覚醒剤の初犯・再犯の量刑は?
覚醒剤事件を起こした場合、一番気になるのは「実刑判決をうけて刑務所に行くことになるのか」ということでしょう。
ここでは、初犯と再犯の場合に分けて量刑相場を解説します。
覚醒剤取締法違反の初犯は懲役何年?
覚醒剤の使用・所持
覚醒剤の使用や所持で有罪となった場合、初犯であれば懲役1年6月に執行猶予3年の判決を言い渡されることが多いです。
もっとも、これは使用量や所持量が少量のケースに限られます。所持量が多く、自己使用目的ではなく営利目的が疑われるケースなどでは、初犯でも実刑になる可能性が高いでしょう。
覚醒剤の譲渡・譲受
覚醒剤の譲渡や譲受の場合も、初犯であれば懲役1年6月に執行猶予3年の判決を言い渡されることが多いです。ただし、営利目的譲渡の場合、初犯であっても実刑判決になる可能性が高いです。
覚醒剤の製造・輸出入
覚醒剤の製造・輸出入の場合は、営利目的での犯行がほとんどです。営利目的の製造・輸出入の事案では、初犯であっても実刑判決を受ける可能性が極めて高くなります。
令和元年の犯罪白書によると、営利目的での覚醒剤製造・輸出入では、執行猶予がついたのはわずか0.9%でした(総数108人)。
覚醒剤取締法違反の2回目(再犯)は懲役何年?
覚醒剤の再犯を犯すと、懲役何年になるのか気になるでしょう。ここでいう「再犯」とは、刑法上の「再犯」とは異なり、再び犯罪をすることと定義して解説していきます。執行猶予中の再犯と、執行猶予後の再犯をそれぞれ見ていきましょう。
なお、刑法上の「再犯」は、①懲役の執行が終わった日、または②懲役の執行の免除を得た日、これら①②の日の翌日から、5年以内にさらに罪を犯して有期懲役に処された場合を意味します(刑法56条1項)。
(1)執行猶予中の再犯の場合
執行猶予中に覚醒剤事件を起こした場合、前刑と今回の刑を合わせた期間、服役しなければならない可能性が非常に高いです。
たとえば、前刑で懲役1年6月執行猶予3年、今回懲役2年が言い渡された場合、3年6月の期間、懲役刑になるということです。
執行猶予中に再び覚醒剤事件を起こしてしまうと、次に掲げる3つの要件をすべて満たさない限り、実刑になります。
- 1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けること
- 情状に特に酌量すべきものがあること
- 前科について保護観察が付けられ、その期間内にさらに罪を犯した場合でないこと
覚醒剤事件で1年以下の懲役を言い渡される可能性は極めて低いので、要件1を満たす可能性はほぼないでしょう。
要件2.3については、『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事で詳しく解説しています。
要件をすべて満たすことは非常に困難であるため、実刑になるケースが多いでしょう。
(2)執行猶予後の再犯の場合
執行猶予期間を満了した場合であっても、再び覚醒剤取締法違反に問われれば、懲役2年前後の実刑となる可能性が高いです。一般的には、2回目・3回目と回数を増すごとに6月ずつ刑期が長くなります。
たとえば、覚醒剤取締法違反の2回目は懲役2年、3回目は懲役2年6月、4回目は懲役3年といった具合です。
とくに執行猶予の満了後5年以内は、実刑となる可能性が高いでしょう。短期間で覚醒剤事件を繰り返す場合、社会内での更生は難しいと判断されやすいです。
再び執行猶予がつく可能性もゼロではない
覚醒剤取締法違反の再犯の場合、判決から10年程度空けば、執行猶予がつく可能性はゼロではありません。
実際に芸能人が覚醒剤所持で起訴された事件で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡され、その約10年後に再び同種事件で起訴され、懲役2年、執行猶予3年が言い渡されたケースがあります。
もっとも、覚醒剤取締法違反の再犯で執行猶予を獲得するのは、ハードルが高いです。刑事事件に強い弁護士と方針を立てながら、再び罪を犯さないこと、更生に向けた取り組みを粘り強く主張していくことが大切です。
覚醒剤取締法違反で逮捕されやすいケース
覚醒剤事件は、現行犯逮捕される場合がほとんどです。または、共犯者の供述などから仲間が特定され、後日、令状に基づいて通常逮捕されることもあります。
現行犯逮捕されるケース
覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕される典型例は、職務質問で覚醒剤の所持が発覚したケースです。
警察は路上や車内で挙動が不審な者を発見すると、職務質問を行います。職務質問では、所持品検査や尿検査が実施されることがあります。
不審な粉末などが発見されると、簡易検査または尿検査が実施されます。陽性反応が出ると現行犯逮捕されることになるでしょう。
また、警察が自宅にやってきて捜索差押令状に基づく家宅捜索が行われることもありえます。検査の結果、陽性反応が出ると現行犯逮捕されます。
尿検査を拒否できるか知りたい方は『尿検査で薬物の陽性反応が出たら逮捕される?尿検査は拒否できる?』の記事をご覧ください。
通常逮捕されるケース
覚醒剤の密売人による供述や携帯電話の受発信履歴、または宅配便の配達記録などから被疑者が特定されるケースもあります。この場合、逮捕令状に基づき通常逮捕されることになります。
関連記事
・覚醒剤で逮捕されたら実刑?逮捕のきっかけや刑罰について解説
覚醒剤で逮捕されたら弁護士を呼ぶべき?
逮捕されると警察で取調べを受けます。取調べでは一人で取調官と向き合うことになります。
何をどう話せば自分に有利になるのか全くわからないまま、取調べのプロである警察官と向き合うのは精神的に厳しいでしょう。
とくに覚醒剤などの薬物事件は、組織的に行われている可能性があるため、入手経路や関与した人物などを厳しく追及されることになります。
これを乗り切るためには、弁護士に早期に依頼し取調べの対応法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、逮捕後は当番弁護士を呼べば1回無料で接見に来てくれます。しかし、当番弁護士を自分で選ぶことはできないため、刑事事件の経験豊富な弁護士が来てくれるとは限りません。
また、国選弁護人は勾留されないと付きません。したがって、刑事事件に慣れた弁護士に一刻も早く接見してもらうには、私選弁護士を依頼しましょう。
関連記事
・弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?費用・メリット等の違いを徹底比較
覚醒剤に関するよくある質問
Q.覚醒剤取締法違反ってどんな犯罪?
覚醒剤の「使用」「所持・譲渡・譲受」「輸出入・製造」をすると、覚醒剤取締法違反となります。
実務では、使用と所持で処罰されるケースが多く、初犯でも逮捕や起訴の可能性がある犯罪です。
Q.覚醒剤ってそもそも何?
覚醒剤取締法における「覚醒剤」とは、以下のものを指します。
1.フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
2.1で掲げる物と同種の覚醒剤作用を有する物であって政令で指定するもの
3.1及び2のいずれかを含有するもの
覚醒剤は、シャブ、スピード、アイスなどの通称で呼ばれることもあります。
覚醒剤の常習者や売人はビニール袋を加工して作ったパケという小さい袋に覚醒剤を小分けにしていることが多いです。
Q.覚醒剤で逮捕された後の流れは?
逮捕されると最寄りの警察署に連行され、取り調べが行われた後、留置場で生活することになります。
逮捕からの身体拘束は最大72時間(3日間)、それに続く勾留は最大20日間続く可能性があります。覚醒剤事件は、共犯者との口裏合わせなどの危険から勾留されることが多いです。
しかし、保釈が認められれば、釈放され日常生活を送ることが可能になります。保釈は、起訴後に申し立てることができます。
関連記事
・逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説
Q.覚醒剤で保釈される方法は?
保釈が認められるのは簡単ではありません。しかし、初犯の場合、弁護士に依頼して証拠隠滅のおそれなどがないことを説得的に主張すれば、保釈が認められることが期待できます。
保釈されると、病院や自助グループのプログラムに参加することもできます。保釈中に治療実績を積めば、更生の意欲があると裁判官にわかってもらうことにもつながります。
早期に弁護士に依頼し、覚醒剤と完全に手を切るための土台をしっかりと築き上げていきましょう。
関連記事
Q.覚醒剤で執行猶予はつく?
覚醒剤取締法違反の場合、全部執行猶予が難しい場合でも、薬物法上の一部猶予制度が適用される可能性があります。
薬物法上の一部執行猶予の要件
- 刑法上の一部執行猶予の対象にならない者。つまり、初入者や準初入者にあたらない者
- 刑法上の要件に加え、刑事施設における処遇に引き続き薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施することが必要かつ、相当であること
- 保護観察が必要的に付されること
覚醒剤の執行猶予について不安がある方は、弁護士に相談して、一部執行猶予が適用される可能性があるのか確認してみてください。
覚醒剤事件を取り扱うアトムの実績・口コミ
覚醒剤事件のアトムの解決実績
覚醒剤取締法違反(初犯)
約1年前から覚醒剤を日常的に購入し使用していた依頼者が、警察から家宅捜索を受け、尿検査によって覚醒剤の使用が発覚したケース。覚醒剤取締法違反の事案。
弁護活動の成果
保釈が認容され、起訴後早期に釈放された。薬物依存症の治療経過を提示など情状弁護を尽くした結果、執行猶予付きの判決となった。
身柄拘束
逮捕・勾留
最終処分
懲役1年6か月執行猶予3年
覚醒剤取締法違反(再犯)
売人から覚醒剤を購入し使用を繰り返していたとされるケース。売人が逮捕されたことから発覚し検挙された。なお依頼者は同種の前科があり執行猶予中だった。覚醒剤剤取締法違反の事案。
弁護活動の成果
保釈請求が認められ早期釈放が叶った。
身柄拘束
逮捕・勾留
最終処分
懲役1年6か月
覚醒剤事件でアトムを選んだお客様の声
覚醒剤取締法違反に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、薬物事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。
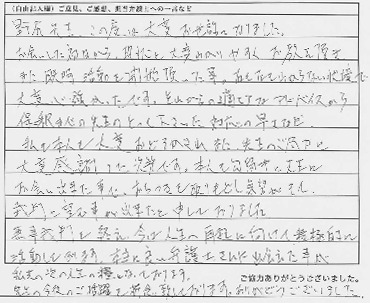
(抜粋)初回から、状況を大変わかりやすくお教え頂き、また、即時活動を開始頂いた事、右も左もわからない状況大変心強かったです。それからの適切なアドバイスから、保釈までの先生のとってくださった対応の早さなど、私も本人も大変おどろかされ、また、先生のご尽力に大変感謝した次第です。落ち着きもとりもどし希望がもて、裁判に望む事が出来たと申しておりました。
先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。
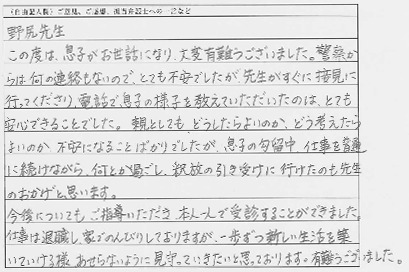
(抜粋)とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。
刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要です。
早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。
まとめ
覚醒剤取締法違反の対応は弁護士に相談
覚醒剤取締法違反は、初犯であっても重い処罰が下される可能性がある犯罪です。
再犯の場合は、初犯以上に重たい処罰が予想され、実刑になる可能性が高まります。
覚醒剤事件は被害者が存在しないため、刑事処分の軽減を狙うには、警察の取り調べに適切・誠実に対応したり、薬物依存を解消する行動をとったりする必要があります。
弁護士抜きでは、いずれも間違った対応をしてしまう恐れがありますし、自分で考えるよりも刑事事件の解決を得意とする弁護士に聞いてしまったほうが早いので、警察から捜査された場合には、すぐに弁護士までご相談ください。
アトム法律事務所は、覚醒剤をはじめとした薬物事件の解決実績が豊富な、刑事事件に力を入れている法律事務所です。
覚醒剤の使用や所持などでお困りの方は、お気軽にご連絡ください。
24時間対応中!弁護士相談のご予約はこちらから
アトム法律事務所では24時間365日、夜間・早朝を問わず、相談予約受付中です。
ご都合のよろしいお時間におかけいただければ、専属スタッフが弁護士相談のご予約をおとりします。
警察から呼び出しがきた、警察署で取り調べを受けた、逮捕されたなど警察介入事件では、初回30分無料で弁護士相談可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしています。



