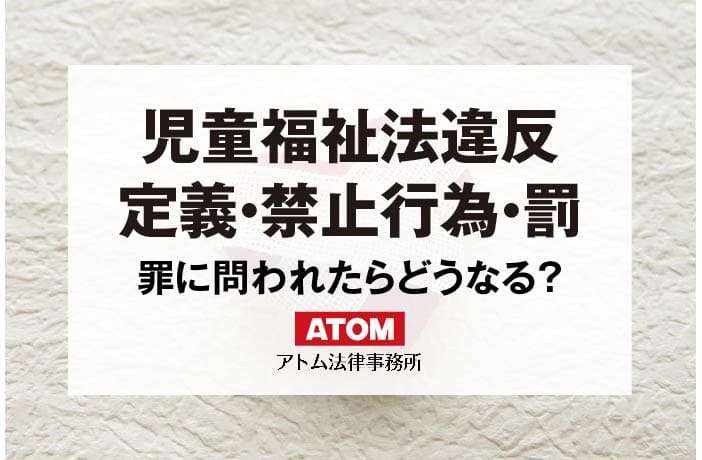
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
児童とわいせつな行為や性交をした場合、各都道府県の淫行条例(青少年保護育成条例)、児童買春禁止法・児童ポルノ禁止法、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪に抵触するほか、本記事で解説する「児童福祉法違反」に該当する可能性があります。
児童福祉法違反の中でも特に、本来なら児童を守るべき立場にある者がその影響力を行使して淫行をさせた場合、重たい処分が科されます。
また、児童の健全育成を目的とする法律である児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為のほか、児童を不当に使役する行為も禁止しています。
もしも児童福祉法違反の罪に問われてしまった際には、早急に弁護士までご相談ください。迅速な行動と被害者への真摯な対応が今後の人生を左右します。弁護士はそのためのお手伝いができます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
児童福祉法違反とは?定義・禁止行為と刑罰
児童福祉法違反とは、学校の教諭と生徒との間の性行為や、女子生徒の売春あっせんなどで、よく問題になる犯罪です。
児童福祉法は、児童にとって有害となる複数の行為を禁止したり制限したりする法律です。その中でもとりわけ、児童を守るべき立場である大人が支配力を利用して児童にわいせつ行為をする点について厳しく取り締まっています。
児童福祉法違反の定義や、禁止行為・刑罰を詳しくみていきましょう。
社会全体で児童を守るための法律
児童福祉法は、児童の健全な育成を目的として制定された法律です。成長途上にある児童は心身ともに未熟なため、大人から不当に扱われたり、不適切な行為を強要されたりしてしまいかねません。そういった状況から、社会全体で児童を守るために児童福祉法があるのです。
児童福祉法の理念については、同法の1条および2条に示されています。
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
児童福祉法
なお、児童福祉法で示されている「児童」とは18歳未満の者を指し、男女の区別なく対象となっています。
児童に淫行させる行為は重く罰せられる
児童福祉法では違反行為がいくつか定められており、その中でも特に児童に「淫行」を「させる」行為については重く処罰されることになります(児童福祉法34条1項6号)。
児童福祉法違反になる「淫行」とは、性行為やそれに類似する行為のことをいいます。具体的には、児童との性交・児童の身体を性的な目的で触る・児童に自慰行為を強要するなどの行為が淫行にあたります。
そして、淫行を「させる」というのは、児童に対して事実上の支配力をおよぼし、淫行を強いることを意味します。
何人も次に掲げる行為をしてはならない。
児童福祉法34条1項6号
六 児童に淫行をさせる行為
実際に、児童福祉法違反で主に問題となるケースは、本来なら児童を守るべき立場にある者が児童に対して不当に影響力を行使して淫行させるケースです。たとえば、学校の教員や塾講師、児童館の職員といった本来なら児童を守るべき立場にある者が、上位的・指導的な立場を利用して淫行をさせるものを指します。
言い換えると、児童に対して事実上、影響力のない者が児童に淫行をさせた場合、児童福祉法違反とはならないのです。もっとも、児童福祉法違反にならないだけで、他の法律や条例違反には該当します。他の法律や条例違反については後ほど解説していますので、このままご覧ください。
また、風俗店において児童を働かせたケースにおいても、この児童淫行罪の一種となり、児童福祉法違反に問われることがあります。
心身ともに未熟であることに乗じた児童に対する性的搾取は厳しく取り締まられるのです。
児童福祉法違反における児童淫行罪の刑罰
児童福祉法34条1項6号に違反する児童淫行罪の刑罰は、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」が定められています(児童福祉法60条1項)。
心身の発達していない児童に対し、立場上の影響力を行使してわいせつな行為をさせることは特に悪質とみなされ、性犯罪の中においても痴漢や盗撮などに比べると重い罪が科されるといえます。
実務上、児童福祉法違反で刑事裁判になった場合、罰金刑になることは少なく、懲役刑の実刑判決になるケースも多いものです。
児童福祉法違反の淫行の公訴時効は12年なので、それまでは刑事裁判にかけられる可能性があります。
児童福祉法違反に問われるおそれがある場合は、刑事事件化の回避、不起訴、執行猶予を目指すための対策を考え、実行にうつす必要があります。
関連記事
・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?
児童福祉法で禁止されるその他の行為
児童福祉法では淫行の他に、以下のような項目についても禁じています。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六 (略)
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
児童福祉法34条1項1号~5号、7号~9号
児童福祉法違反のその他の行為における刑罰
児童淫行罪以外の罪、すなわち、児童福祉法34条1項1号~5号、7号~9号に違反する行為の刑罰は、「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科」が定められています(児童福祉法60条2項)。
児童福祉法違反と関連するその他の犯罪
児童福祉法だけでなく、児童はさまざまな法律や条例で保護されています。たとえ児童福祉法に違反する行為でなくても、その他の犯罪に該当する可能性があるのであわせて確認しておきましょう。
なお、ひとつの行為で児童福祉法違反とその他の犯罪に該当する場合、刑罰が重い方が適用されます。
淫行条例違反(青少年保護育成条例違反)
淫行条例(青少年保護育成条例)とは、18歳未満の青少年を保護し、健全な育成を目的として自治体ごとに定められている条例です。児童に対してみだらな性交や性交類似行為を行う淫行をはじめ、不健全と書類の販売規制なども規定されています。
淫行条例は自治体ごとに内容や罰則が異なりますが、東京都が規定する淫行行為に関する淫行条例違反は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰に処せられる可能性があります。
淫行条例で規定されている淫行は、たとえ本人同士の同意があったとしても罰せられる点に注意してください。
関連記事
児童買春・児童ポルノ禁止法
児童買春・児童ポルノ禁止法の正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。児童買春、児童ポルノに関する行為の処罰や、児童の保護のための措置を定めた法律です。
児童買春
児童にお金・プレゼントなどの対価を渡したり、対価を渡す約束をしたりして、性交や性交類似行為をした場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」の刑罰に処せられる可能性があります。
関連記事
児童ポルノ
また、児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童のわいせつな姿を映した画像や映像を所持・保管・提供・製造・陳列したりすることを禁止する法律でもあります。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反となる行為態様は様々ですが、たとえば、自分の性的好奇心を満足させる目的で児童ポルノの所持や保管をした場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰に処せられる可能性があります。
また、児童の性的姿態を撮影する等して児童ポルノを製造した場合、その刑罰は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
関連記事
・児童ポルノの逮捕事例や逮捕後の流れ。単純所持もバレる?見ただけで逮捕?
・児童ポルノ事件で弁護士をお探しの方へ|刑事事件に強いアトム法律事務所
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪とは、18歳未満の児童を監護する者が監護者としての立場や影響力を利用して性交等やわいせつを行う犯罪です。監護者とは、児童と同居する実の親や親族、親の再婚相手などで、実際に児童を監護する立場にある者をいいます。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は「5年以上の有期拘禁刑」の刑罰に処せられる可能性があります。
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪とは、暴行や脅迫などをして相手をねじふせるなど、性行為に同意できない状況下で、相手の同意なしに性交等やわいせつを行う犯罪です。
ただし、「児童が13歳未満の場合」や、「児童が13歳以上16歳未満の場合に、行為者であるあなたと児童の年齢差が5歳以上あるとき」は、児童が性行為に同意していたとしても、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪に該当することになります。
- 13歳未満
- 13歳以上16歳未満(行為者と児童の年齢差が5歳以上)
不同意性交等罪は、性交、口腔性交、肛門性交、膣への陰茎以外の挿入をした場合に成立し、法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。
不同意わいせつ罪は、体を触る、キスをするなどのわいせつ行為をした場合に成立し、「6ヶ月以上10年以下の有期拘禁刑」の刑罰に処せられる可能性があります。
関連記事
・不同意性交等罪とは?構成要件・旧強制性交等罪との違い、罰則をわかりやすく解説
・不同意わいせつ罪とは?構成要件・旧強制わいせつ罪との違い・刑罰を分かりやすく解説
・不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?
児童福祉法違反は逮捕される可能性がある
児童福祉法違反は、児童の健全な育成を妨げたり、児童の権利を踏みにじったりする悪質度の高い犯罪とされているので、逮捕される可能性が高いです。
逮捕されると長期間の身体拘束が続く可能性があるので、逮捕の流れもおさえておきましょう。
被害届がなくても児童福祉法違反は逮捕される可能性あり
児童福祉法で禁止される行為のほとんどが親告罪ではありません。親告罪とは、被害者やその法定代理人等の告訴がなければ、検察官が起訴できない犯罪のことをいいます。
したがって、児童福祉法違反のほとんどに関しては、犯罪が明るみになれば、被害者の被害届なしでも逮捕されたり、起訴されたりする可能性があるのです。
逮捕勾留から起訴前の身体拘束までは最長23日間
次は、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕後、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)という手続きが48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。
捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。
関連記事
児童福祉法違反を起こしたらすべき対応
児童福祉法違反により逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。
前科をつけないためには不起訴処分を得ることが重要
検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。
すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。
児童福祉法違反を認める場合も、認めない場合も、弁護士に依頼すれば、状況に応じた適切な対応が期待できるでしょう。
- 児童福祉法違反を認める場合の弁護活動
逮捕・勾留される可能性が高いため、逮捕回避や早期釈放に向けて、捜査に協力する姿勢や反省を示したり、被害児童への謝罪や示談の状況などを捜査機関に説明したりする - 児童福祉法違反を認めない場合の弁護活動
18歳未満であることを知らずに淫行をさせたり、真剣交際をするうえでの性交であったりした場合などは、故意がなかったことを捜査機関に示す
いずれにしても、不起訴処分を目指す場合は、刑事事件を扱った経験が豊富な弁護士を選任することが重要です。
刑事事件の弁護士の選び方については、『刑事事件の弁護士の選び方|弁護士は必要?』の記事でくわしく解説しているので、あわせてご覧ください。
釈放や不起訴の可能性を高めるためには示談が重要
不起訴処分を得るためには、被害者との間に示談を締結することが重要です。
示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。
なお、児童福祉法はあくまで青少年の健全な育成のための法律であり、被害者個人の法益保護を目的とするものではありません。しかし、被害者との間に示談を締結することは重要な意味を持ちます。
また、性犯罪においては被害者は加害者に対して非常に強い恐怖心を抱いていることが考えられ、児童の場合においてはなおさらであるといえます。そうしたこともあり、加害者が直接被害者と接触し示談を締結することはほぼ不可能であるといえます。
このようなケースであっても、経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情に最大限配慮した対応を行い、適切に示談を締結することを目指すことが可能です。
関連記事
・刑事事件の示談の流れ│加害者が示談するタイミングや進め方は?
示談以外にも通院や家族の監督などの対応が重要
児童福祉法違反により逮捕された場合、示談以外にも性依存症を治療・カウンセリングするための通院や、再犯を防ぐための家族による生活状況を監督する環境を整えることなども重要です。
ここまでに解説したものは、捜査機関や被害者へ対する対応方法でしたが、これらは児童福祉法違反を起こした本人が自分の罪と向き合うためのものになります。
弁護士がついていれば、通院状況や監督状況を検察官・裁判官に対して丁寧に説明してもらえるので、不起訴や執行猶予につながる可能性が高まるでしょう。
性犯罪事件でどういった弁護士を選ぶべきか知りたい方は『性犯罪に強い弁護士|アトム法律事務所』をご覧ください。
児童福祉法違反で前科をつけないためには早期に弁護士へ相談を
児童福祉法違反で、不起訴の可能性を高め、前科の回避を目指すには、児童側との示談が欠かせません。そして、適切に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが非常に重要です。
逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。
そのため、児童福祉法違反事件においてはできる限り早い段階で弁護士に相談することが大切であるといえます。
児童福祉法違反、淫行事件でお悩みの方は、刑事事件の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士まで、是非お早目にご相談ください。



